 スクイージングとは? 禁忌は? 排痰効果の上がる方法【写真解説】
スクイージングとは? 禁忌は? 排痰効果の上がる方法【写真解説】
- 公開日: 2014/6/9
この記事を読んでいる人におすすめ

体位ドレナージとは?方法・実施時間・コツ
患者さんへの侵襲の少ない排痰ケアを行っている病棟が増えています。吸引を前提にしない排痰ケアとは、一般に「肺理学療法」を中心にした排痰法です。 理学療法というと、難しそうに感じますが、メカニズムを理解し、練習してコツをつかむことで、安全に行うことができます。 ▼サチ

呼吸音の聴診 5つのポイント
▼バイタルサインについて、まとめて読むならコチラ バイタルサインとは|目的と測定の仕方、基準値について 【関連記事】 ●

第3回 いくら吸引しても痰が引けてこない患者さんへの対応
困難を感じたことがある上位に挙がった5つのケースについて、具体的な解決法を紹介します。 どこに問題があるのか、あなたの体験した吸引の「困難ケース」について、じっくり再考してみませんか? 攻略法1 吸引で取れる痰かどうか見極めよう! 音はするのに、痰が引けないとい

【動画】第7回 呼吸介助手技ータッピング(重度障害児者のケース)
タッピングは空気の入りの悪いところを探して、たたきます。実施する際は、聴診器で肺胞呼吸音を聞きながら行います。側臥位にして、背側も行うとよいでしょう。 タッピングのポイント 1 聴診器を使って、空気の入りが悪いところを探す 2 空気の入りの悪いところ
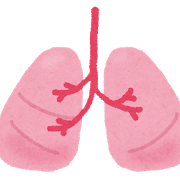
異常呼吸の種類と原因|チェーンストークス呼吸・クスマウル呼吸・ビオー呼吸など
多呼吸や過呼吸、チェーンストークス呼吸など、異常な呼吸状態のとき患者さんに何が起こっていると推測できるかを解説します。 【関連記事】 ● バイタルサインとは|目的と測定の仕方、基準値について ● 異常呼吸音(副雑音)の種類とアセスメント ● 呼吸音の聴診 5つ
カテゴリの新着記事

【呼吸状態の評価】緊急入院してきた痰の多い患者さん
呼吸状態の評価の仕方は、患者さんの症状や疾患などにより、みるべきポイントやケアの仕方も異なります。呼吸状態を評価する際は、基本となるフィジカルアセスメント、バイタルサイン、検査データを確認するだけではなく、得られた情報を組み合わせて評価し、呼吸状態にあったケアを提供す
-
-
- 【動画】第9回 呼吸介助手技ー介助ハッフィング(重度障害児者のケース)
-
-
-
- 【動画】第8回 呼吸介助手技ーバウンシング(重度障害児者のケース)
-
-
-
- 【動画】第7回 呼吸介助手技ータッピング(重度障害児者のケース)
-
-
-
- 【動画】第6回 呼吸介助手技ーリフティング(重度障害児者のケース)
-




