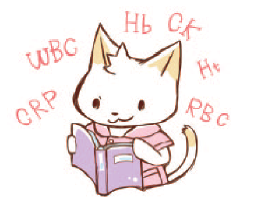 虚血性心疾患の検査データはココを見る!(CK-MBの基準値など)
虚血性心疾患の検査データはココを見る!(CK-MBの基準値など)
- 公開日: 2015/2/3
虚血性心疾患の看護に必要な検査データをピックアップしました。
虚血性心疾患とは?
心筋に酸素と栄養を供給している冠状動脈が狭窄・閉塞し、心筋に酸素と栄養が供給されなくなった状態を虚血性心疾患といいます。
虚血性心疾患の原因
- ● 動脈硬化(高血圧、脂質異常症、糖尿病、加齢、閉経後などが危険因子となります。)
- ● 冠状動脈の痙攣
虚血性心疾患の種類
- ● 急性心筋梗塞
- ● 労作性狭心症
- ● 異型(冠攣縮性)狭心症
- ● 不安定狭心症
続いて虚血性心疾患の検査データの見方を解説します。
虚血性心疾患の検査データはココを見る!
1 心電図検査
心電図検査では、ST部分・T波に注目します。
超急性期では、まずT波が上昇します。
次にST波が、
- 上昇したら、心筋梗塞
- 下降したら、狭心症
を疑います。

佐藤紀子 ほか監「看護に役立つ病態生理とアセスメント」エス・エム・エス、2013、より引用一部改編
2 心エコー検査
心エコー検査では、心筋壁の動きに偏りがないかを確認します。
3 心筋マーカー
心筋梗塞の鑑別に有効なマーカーとして、心筋障害マーカーがあります。発症後だけではなく、治療後の再狭窄を確認するためにも有効な指標です。
■心筋マーカーの特徴と基準値(※急性心筋梗塞の場合)
- ● CK・・・発症後数時間で上昇し、1日でピークに達し、3~4日で正常値に戻ります。基準値は、男:50~230U/l 女:50~210U/l
- ● CK-MB・・・発症後12~24時間でピークに達します。基準値は7.5ng/ml以下
- ● 心筋トロポニンT・・・二峰性の上昇を示すのが特徴で、第1ピークは発症から12~18時間 第2ピークは90~120時間(3~5日)となります。基準値は0.014ng/ml以下
4 凝固能検査
虚血性心疾患の標準的な治療である経皮的冠動脈形成術(PCI)を行う場合、血栓形成を抑制するために、抗血小板薬やヘパリンを投与するため、凝固能検査は欠かせません。
凝固能は以下の5項目を見ます。
- ● FDP定量・・・血栓が形成されたあと、一時線溶が働きてFDPが生成されます。基準値は5.0μg/ml以下
- ● Dダイマー・・・血栓から二次線溶によってできるフィブリン分解産物のことです。身体のどこかに血栓ができると、高値になります。基準値は1.0μg/ml以下
- ● PT・・・血液が凝固するまでの時間を測定する検査です。延長している場合は出血傾向、短縮している場合は血栓症が疑われます。基準値は0.90~1.31%です。
- ● APTT・・・ヘパリンの量の調節の指標です。基準値は26~28秒
- ● INR・・・ワルファリン効果の指標です。基準値は1.0±0.1
5 腎機能能検査
虚血性心疾患の標準的な治療である経皮的冠動脈形成術(PCI)を行う場合、造影剤を使用します。造影剤によって腎機能が低下する患者さんがいるため、腎機能検査は欠かせません。
(『ナース専科マガジン』2014年10月号から改変利用)
参考になった
-
参考にならなかった
-
カテゴリの新着記事

狭心症で心臓カテーテル治療(PCI)を受ける患者さんに関する看護計画
狭心症で心臓カテーテル治療(PCI)を受ける患者さんに関する看護計画 狭心症は何らかの要因によって冠動脈が狭窄することで血流が乏しくなり、その先にある心筋細胞が虚血になる病態です。一時的な虚血に応じた症状が見られるため一過性の胸部症状が典型的です。今回は狭心症として心臓カ
2025/4/28
-
-
- 狭心症患者さんの食事指導に関する看護計画|脂質異常症の治療が必要となった患者さん
-
-
-
- 骨折が生じた患者さんの看護計画
-
-
-
- Rubenstein分類
-
-
-
- CCS分類(Canadian Cardiovascular Society functional classification)
-







