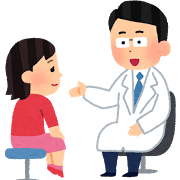 第1回 いったい、 PEGのどこがいいの?【PR】
第1回 いったい、 PEGのどこがいいの?【PR】
- 公開日: 2017/10/2
このシリーズでは、小児医療のなかで、胃瘻、特にPEGをどのようにとらえていくべきかを考えます。
消化器内科と小児外科という異なる専門領域からの取り組みを通して、PEGへの理解を深め、今後を展望します。第1回はPEG・在宅医療研究会会長の上野文昭先生が、成人、なかでも高齢者医療におけるPEGの位置づけ、わが国のPEG普及の道のりを研究会発足20年の歴史を交えて紹介します。PEGという選択をするうえで、治療計画の出発点として、まず何を考えるべきかにも触れました。
在宅胃瘻栄養管理における問題点の検討
私は消化器内科医師として、長年にわたり成人、特に高齢者の経皮内視鏡的胃瘻造設術(percutaneous endoscopic gastrostomy:PEG)に携わってきました。よりよい医療のために今後PEGをどのように展開していけばよいのか考えてみたいと思います。
現在のところ、内科・外科を問わず、ほとんどの医師はPEGに対する認識が十分とはいえません。PEGの注目点はendoscopic(内視鏡的)に実施できるという部分です。つまり内視鏡的に行う胃瘻(gastrostomy)がPEGであって、“PEG=胃瘻”ではありません。PEGは優れた方法だと考えられていますが、そもそも胃瘻が優れた治療であるからこそ、PEGも優れた手技だとされているのです。
胃瘻は、今から100年以上前の1894年に、外科的胃瘻術が完成したことから次第に臨床に普及しました。1970 ~ 80年ごろになると、内科医師が低侵襲治療手技として内視鏡を用いた手術を積極的に行うようになり、内視鏡的乳頭括約筋切開術や内視鏡的粘膜切除術といった数々の手技が開発されました。PEGもその1つなのです。
PEGは最初、小児に実施された手技でした。開発コンセプトは、①全身麻酔や開腹を必要とせずに、②造設部位を確実に決めることができ、③周囲臓器に影響を与えることなく、④胃壁を確実に腹壁に固定できる、というものでした。門田俊夫先生とともに国内では初めて、イントロデューサー原法によりPEGを行い、成功しました。
現在では優れたさまざまなデバイスが登場していますが、当時はPEGのカテーテルキットはまだ開発されておらず、膀胱瘻用のキットを用いました。こうして、日本初のPEGが実施されはしたものの、その後なかなか浸透しませんでした。というのも胃瘻そのものには100年以上の実績がありましたが、日本における評価はまだ低い時代だったからです。内視鏡医は興味を示しましたが、他の医師の関心は薄く、患者さんや家族は“お腹に穴をあけるなんて”と驚き、強い拒否感を示す傾向にありました。また当時の保険診療では長期の入院と輸液管理が認められており、医療経済から考えてもPEGの普及は難しい状況でした。
たとえPEGを実施したとしても、医療はいわゆる縦割りで、施行医である消化器科と他の診療科間の連携不足により、胃瘻を有効に使用することができず患者さんと家族の期待に応えられないことが多かったのです。しかし21世紀に入ると日本の医療に変化がみられました。総合診療の概念が浸透して縦割りによる障壁が減り、同時に胃瘻に対する認識も医学的に優位なものへと変わっていったのです。加えて、社会的に在宅医療・緩和医療が重視されるようになり、診療報酬の面からも早期退院と胃瘻の造設が収益をもたらすようになりました。そしてPEGは徐々に普及していきました。
こうしたPEGの普及に先駆けて、1996年に発足したのがHEQ(Home Health Care, Endoscopic Therapy and Quality of Life)研究会(現在はPEG・在宅医療研究会、2009年9月改称)です。PEG等の内視鏡治療を用いた在宅医療の推進、および患者さんのQOL向上を達成することを目指しています。年1回の学術集会開催、「在宅医療と内視鏡治療」誌発行、各種委員会活動も盛んに行っています。会員数は600名を超え、内科・外科・神経内科といった複数の診療領域にわたり、いま日本で熱心にPEG診療に携わる医師が名を連ねています。ちょうど研究会から学会へと準備を進めているところです。
PEGの適応は多角的に考える
日本でも浸透してきたPEGですが、これに伴い適応についてマスコミからのバッシングを受けるようにもなりました。PEGの適応は小児では比較的明確になっていますが、高齢者、特に不可逆的な神経障害のある患者さんの場合、本当にPEGを行ってしまってよいのかは課題なのです。患者さんが自発的に摂食できなくなったときどうするか? このことを改めて考えたいと思います。
もちろん一律には決められません。患者さんの年齢、疾患、食べられない理由、回復の見通し、他疾患の有無、生命予後、本人と家族の希望、これらをすべて考えたうえで、最適な方法を選ぶ必要があります。
仮に、認知症が進行して摂食意欲が低下し、介助をしても経口摂取は困難という高齢患者さんがいたとしましょう。治療計画の出発点として、まず何を考えるでしょうか。
栄養療法と投与経路に関する考え方として、アメリカ静脈経腸栄養学会(American Society forParenteral and Enteral Nutrition:ASPEN)が提示しているアルゴリズムがよく用いられています。これは、自発的栄養摂取が不可能で摂食意欲・嚥下機能が低下している患者さんの場合、消化管機能によって、経腸栄養(経鼻胃管または胃瘻・腸瘻)か静脈栄養(末梢静脈栄養または中心静脈栄養)のどちらかを選択するというものです。

ただ、摂食意欲・嚥下機能の低下や消化管機能を評価する以前の問題として、受動的な栄養補給をすべきなのか、それともしないほうがよいのかについて考えるべきでしょう。何も“しない”か、何か“する”か。どちらが患者さんや家族にとってよいのか――ここが治療計画の出発点だと考えています。とかくPEGに熱心に取り組んでいる医師がこのことを忘れがちです。そもそも日本人は情緒的で、論理的に考えるのが苦手であるため、“しない”という選択肢をとらない人が多いのです。
何も“しない”は1つの立派な選択肢です。これをないものとして、何かを“する”前提で治療を組み立ててしまうと、必ずしも適切ではないPEGを行ってしまう可能性があり、まわりまわってPEGに対するバッシングにつながりかねません。
何も“しない”も選択肢としてきちんともっていれば、治療計画の際に迷いが少なくなるでしょう。そして何か“する”ことになったときには、自信をもってPEGを実施できるのではないでしょうか。








