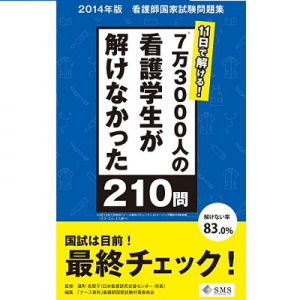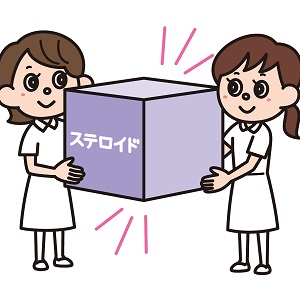 ステロイドがどうしていろいろな疾患で用いられているのかわからない!
ステロイドがどうしていろいろな疾患で用いられているのかわからない!
- 公開日: 2019/2/24
臨床で幅広く使用される「ステロイド」ですが、その働きや副作用などについてきちんと理解できていますか? 「重症時に使用される強い薬剤」といったイメージのもと、医師の指示のまま何となく使用してはいませんか? 今回は、ステロイドについての困りごとを解決しながら、その基本を確認していきましょう。副作用や患者さんの不安に悩むことなく、ステロイド療法をサポートできる看護師になりましょう。
解決の糸口はココ
●副腎皮質ステロイド(ステロイド)が本来もっている生理的な働きに注目しよう
●適応が、抗炎症作用、免疫抑制作用を要する疾患・症状であることを確認しよう
ステロイドがどのように生まれるのかを知っておきましょう
副腎皮質からは、主に糖質代謝にかかわる糖質コルチコイドと、電解質代謝にかかわる鉱質コルチコイド、加えて少量の性ホルモンが分泌されています。糖質コルチコイドは、副腎皮質グルココルチコイドあるいは副腎皮質ステロイドと呼ばれ、抗炎症作用と免疫抑制作用をもっています。この糖質コルチコイド(以下、ステロイド)を化学合成したものが、合成ステロイド(表1)となります。

身体が何らかのストレス刺激を受けると、視床下部では副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRF)が産生されます。これに下垂体が反応して、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を分泌。その刺激によってステロイドが分泌されます。一般成人で副腎皮質から分泌されるステロイドの量は、コルチゾール換算で通常10mg/日、プレドニゾロン換算で2.5mg/日です。ただしストレスがかかると、その何倍ものステロイドが分泌されます。
◆check◇ ステロイドの作用機序はこう考えられている
ステロイドについては、およそ70年間にわたり研究され続けてきましたが、本当の意味での作用機序はいまだにわかってはいません。現在は次の2 つの作用機序が提唱されています。
ステロイドは、分子量が300~500前後の低分子であるため、拡散によって細胞内に取り込まれます。細胞質内にはステロイド受容体( ステロイドに特別に結びつく蛋白)があり、ステロイドはこれと結合します。ステロイドと結合した受容体は、活性化し細胞核内に入って、さらに受容体が結びつきやすい配列をもったDNAと結合します。そしてDNAがもっている情報をメッセンジャーRNA(mRNA) に伝え、そのmRNAは蛋白を合成するためのDNA情報を提供します(転写)。つまり、ステロイドが結びついた受容体が、転写の働きを調節することになります。この調節機能によって、一部の抗炎症蛋白の転写が促進され、さらにほかの働きをもった蛋白のmRNAを増やして、多くの生理作用が引き起こされることになります(図左)。
もう一方は、炎症性サイトカインの転写に直接関係するという考え方です。細胞膜にある炎症性サイトカインの受容体に、サイトカインが結合すると、AP-1やNF-κBというような転写に作用する因子が働くようになります。この転写因子が核内のDNAに働きかけ、転写を盛んにして、別のサイトカインを産生するようになります。このように、細胞内の炎症性の転写因子が増えると、それが二次的に働くようになり、炎症の連鎖を生み悪循環となるのです。ステロイドと結合した受容体は、このAP-1やNF-κBの働きを阻害し、炎症性の転写を抑制します。これにより、抗炎症作用が得られるというものです(図右)。
多くの機能にかかわっているため、さまざまな疾患・病態で使われます
ステロイドは、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、水・電解質代謝、骨・カルシウム代謝、免疫抑制作用、抗炎症作用などの働きを有するほか、神経系、循環器系など生体の多くの機能にかかわっています。生命維持のためには必須のホルモンなのです。
このようにステロイドは、生理作用も薬理作用も多様で、広範囲に効果が認められます(表2)。例えば、関節リウマチの場合、抗リウマチ薬といわれる一群の薬剤を使用しますが、それらは基本的にリウマチの炎症のみに効果を発揮します。しかし、ステロイドは、多くの炎症に効果が期待できます。膠原病や関節リウマチ、アレルギー疾患の炎症、また末期がんの悪液質による炎症、湿疹による炎症などを適応としています。
また、免疫抑制作用についても、免疫を抑えなければならない疾患に対し広く使われています。免疫抑制薬のように免疫抑制作用のみではなく、強力な抗炎症効果を有していることも強みです。
ステロイドを必ず使用すべき適応症は、副腎不全、ステロイド離脱症候群、ショックで、重要臓器障害を有する膠原病諸疾患もほとんどが適応になります(表3)。
ステロイドのように、最強で即効性のある抗炎症作用と免疫抑制作用の両方の効果をもっている薬剤はそれほど多くありません。そのため、多くの疾患・病態で用いられることになるのです。
参考文献
● 浦部晶夫,他編:今日の治療薬 2016年版.南江堂.2016,p.246-53.
この記事はナース専科2017年12月号より転載しています。