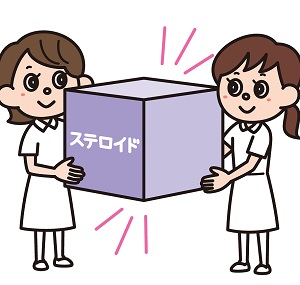 ステロイドの副作用が出た! どうしたらいいのかわからない!
ステロイドの副作用が出た! どうしたらいいのかわからない!
- 公開日: 2019/3/3
【関連記事】
● ステロイド外用剤の副作用についてうまく説明できない!
● 患者さんがステロイド使用に不安を訴えている!
解決の糸口はココ
●ステロイドの過剰により生じる生理的作用との関連をみていこう
●投与量による副作用のリスクを知っておこう
●特に注意が必要な副作用を覚えておこう
副作用は投与量が多くなるにしたがって強く出るようになります
ステロイドは、副作用が強調されがちですが、もともとは安全なものです。何といっても、副腎皮質から分泌されるホルモンで、本来私たちの体内に存在するものだからです。しかし、普段私たちの体内で分泌されている量では、薬剤として期待する抗炎症作用と免疫抑制作用が得られないことも多く、それ以上の量を使用しなければならないときに、副作用が出現します。
投与量は、期待する作用によって異なり、例えば、抗炎症作用を目的とする場合は、プレドニゾロン5mg/日以下でも効果が認められます。一方、免疫抑制作用となると、15mg/日未満では十分な作用が見込めません。そのため、疾患や病態によって、投与量が異なることになり、副作用が生じる程度も変わってきます。
また、長期投与となると副作用の出現は否めません。急激な減量や中断で副腎不全が生じるほか、副作用の範囲は広く、多くの臓器にさまざまな障害が出ることになります(表1)。
「副作用の特徴的症状=クッシング症候群」と覚えましょう
ステロイドの副作用の特徴は、クッシング症候群の場合と同様の症状が出現するということです。クッシング症候群は、原因はさまざまですが、副腎皮質ステロイドの一種であるコルチゾールの分泌過剰が原因です。コルチゾールと同様の作用をもつ合成ステロイドを使用するということは、体内のコルチゾール量が過剰になることと同じで、そのためにクッシング症候群と同様の症状が出現することになります。
ステロイドには、多くの身体的作用があります。そのため、目的以外の作用については副作用となってしまいます。クッシング症候群の特徴的症状でもある中心性肥満など外見上の変化などもみられます。
ステロイドの副作用は、投与量にもよりますが、症状によって発現時期が異なります。投与日からすぐに予防や観察が必要なものから、しばらくしてから症状が現れ注意を要するものまであります(表2)。そのため、おおよその発現時期を念頭に置きながら、その対症法(表3)を把握しておくようにすることが求められます。
主な副作用は次の通りです。
[骨粗鬆症]
ステロイドは骨芽細胞の機能を低下させるため、骨形成が抑制されます。さらに破骨細胞の分化・活性化の促進や性腺機能低下、二次性副甲状腺機能亢進などで骨吸収が促進され、骨が脆くなってしまいます。これが骨粗鬆症です。これによって骨折のリスクが高まり、高齢者では寝たきりの大きな原因の1つとなります。場合によっては、外科手術ができずに合併症などで全身が弱くなり、死に至ることもあります。
ステロイド性骨粗鬆症は、全身投与での合併症として発症頻度が高く、プレドニゾロン換算で5mg/日以上であれば明らかに起こるとされます。投与量が多くなると、その分骨折リスクが高くなるため、十分な注意が必要です。
「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン2014年版」(日本骨代謝学会)では、プレドニゾロン換算5mg/日以上で3カ月以上の使用が予定されている患者さんに対しては、一次予防として、ビスホスホネート製剤や活性型ビタミンD3製剤などの投与が検討されます。
[糖尿病などの代謝異常]
ステロイドには、インスリン抵抗性が増大する作用があるため、それに伴い、血糖値の上昇が認められます。また、コレステロール値上昇などの脂質異常、肥満傾向といった症状が現れます。
糖尿病既往のある人では病状が悪化、耐糖能異常がある人は糖尿病を発症することがあります。症状の悪化により、場合によっては重篤な状態になる副作用で、症状によっては、インスリン投与になります。患者さんにステロイド投与を検討する際には、糖尿病の既往の有無、家族歴、年齢や肥満度などを確認し、リスクを予測するようにしましょう。
また、多くはステロイドの投与を開始してから3カ月以内で発症するので、投与前に空腹時血糖値やHbA1cを測定して、耐糖能異常の有無を確認するようにします。治療が長期にわたる場合には、「糖尿病診療ガイドライン2016」(日本糖尿病学会)などに従って、血糖コントロールを行い、しっかりとモニタリングすることが大切です。
[消化管障害]
ステロイドによる胃酸分泌亢進や粘膜保護作用の抑制などが消化管障害の原因と考えられています。症状は、潰瘍、出血、穿孔などで、胃や十二指腸に多くみられます。
自覚症状に乏しく、ステロイド投与開始後1カ月以降に生じることが多く、吐血や下血といった症状が突然現れます。一般に発症頻度は低いのですが、体力が低下しているがん患者さんや呼吸器疾患による低酸素状態などで身体が弱っているケースでみられることがあり、重症化します。
リスクが高いと考えられる場合は、予防として胃粘膜保護薬の投与を行い、定期的な便潜血検査や必要に応じて上部消化管内視鏡検査によって副作用の有無を確認し、早期発見に努めます。
[副腎不全、ステロイド離脱症候群]
ステロイドを投与すると体内のコルチゾール量が増えることと同じになるため、逆に副腎皮質からのコルチゾールの分泌が抑制され、副腎自体の機能も低下します。そのため、いきなりステロイドの使用を中止すると、副腎機能がすぐに戻らず、副腎不全に陥ることがあります。さらに、副腎皮質機能低下によって、全身倦怠感、脱力感、食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、頭痛、不穏などの症状が現れたり、時にはショックや意識障害によって死に至ることもあります。
プレドニゾロン換算で10mg/日以上で3年以上の長期にわたる投与や、総投与量が1500~7000mgになる場合には、ほぼすべての症例で視床下部、下垂体機能の抑制が起こるといわれています。
初期治療後は、1~2週間で10%をめどに徐々に減量していき、ステロイド離脱症候群の発症を予防します。前述のような症状が現れた場合には、すぐにステロイドの大量投与を行うことになります。
[精神障害]
精神障害は、ステロイドが脳内の受容体に作用して起こると考えられています。最も多いのは軽躁状態ですが、これはあまり問題にはならないことが多く、注意したいのはうつ状態です。ほかに不眠、不安などの症状が出現します。
うつ状態は、ステロイドを高用量投与した数日後から出現するとされています。なかには自殺のおそれのある患者さんもいるので、症状がみられたら精神科の受診を促し、対応してもらいましょう。
[感染症]
プレドニゾロン10mg/日以上もしくは総投与量700mg以上で免疫力が低下し、感染症の発症リスクが高くなるといわれています。細胞性免疫も液性免疫も低下し、ブドウ球菌、大腸菌、さらに真菌やウイルスといった多くの病原体への感染リスクが高くなります。免疫が抑制されると、健常な人では発症しない病原性の弱い病原体でも発症することがあり、日和見感染症と呼ばれます。
そのため、インフルエンザや肺炎球菌など不活化ワクチンがあるものは、ワクチン接種で感染対策を行います。逆に、麻疹などの弱毒生ワクチンは、ステロイドによって免疫が落ちているために疾患発症のリスクがあり、接種は禁忌です。
◆check◇ 患者さんの服薬(投薬)状況から副作用出現のリスクがわかる
ステロイドは、その効果も副作用も用量依存性に出る薬剤です。そのため、副作用の発生頻度や重症度は、その投与量と使用期間に応じて高まります。
通常体内で分泌されるコルチゾールは10mg/日、プレドニゾロン換算で2.5mg/日です。ステロイド受容体の感受性は個人差もありますが、基本的に通常の分泌量の倍量を超えるステロイドの投与があるケースでは、副作用出現の可能性があります。常に、使用量を確認して、さまざまな副作用を念頭に置いてケアしていくことが大切です。
参考文献
● 川合眞一,編:研修医のためのステロイドの使い方のコツ.文光堂,2009.
● 浦部晶夫,他編:今日の治療薬 2017年版.南江堂,2017.
この記事はナース専科2017年12月号より転載しています。
【関連記事】
● 高齢者、小児、妊婦のステロイド使用時の注意点がわからない!
● ステロイドの使用をやめるときはどうすればいいの?
● ステロイド療法中の患者さんが手術適応になった!|ステロイドカバーとは











