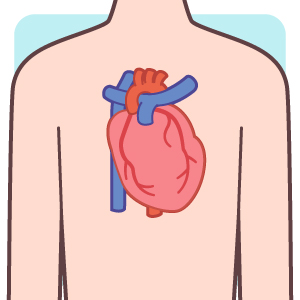【連載】ICU・HCU看護のQ&A! 皆さんの疑問にお答えします!
 循環動態が不安定な患者さんの急変対応について知りたい!
循環動態が不安定な患者さんの急変対応について知りたい!
- 公開日: 2025/8/29
些細な変化を見逃さない
急変対応の第一歩として求められるのは、些細な変化に気づく観察力です。
循環動態が不安定な患者さんは、心不全で血圧が低下している場合や弁膜症で致死的な不整脈が出やすい状態であることなどが考えられます。血圧低下や脈拍の速さだけでなく、四肢冷感、皮膚の湿潤や色調の変化、尿量の減少、意識レベルの低下など、さまざまな徴候がみられるようになります。
明らかな変化ではなく、「いつもと何か違う」といった微細な変化であっても見逃さないことが大切で、頻回な観察を重ねて状態把握に努め、場合によっては医師に報告したうえで適切に介入していくことで、急変を未然に防げる可能性が高くなります。
日々の観察を機械的に行うのではなく、前日や数時間前と比べてどのように変化しているかを意識しながら、患者さんに接する姿勢が重要です。
チームで連携して初期対応を実施
万が一、急変が起きた場合は、ABC〔A:Airway(気道)、B:Breathing(呼吸)、C:Circulation(循環)〕の初期評価とそれに基づく介入が必要になります。具体的には、A:気道が開通しているか、B:呼吸をしているか、C:循環動態は安定しているかを迅速に評価し、酸素投与、静脈路の確保、輸液や昇圧薬の準備、除細動や気道確保の準備など、チームで連携しながら適切な初期対応を行っていきます。
循環動態が不安定な状態の患者さんが急変した際に起こるパターンとしては、出血性ショック、敗血症性ショック、心原性ショックなどが考えられ、それぞれ原因と対応が異なります。
出血性ショックは、外傷や消化管などからの出血により、大量の血液が失われることで起こります。血圧低下、頻脈、冷汗、四肢冷感、意識障害が進行していくため、輸液・輸血を行いながら止血のための介入が必要になります。
敗血症性ショックの主な原因は細菌感染です。発熱や頻脈、頻呼吸がみられるようになり、次第に血圧が低下していきます。抗菌薬投与前に培養検体を採取するとともに、輸液やノルアドレナリンなどを投与し、循環動態をサポートします。
心原性ショックの原因としては、急性心筋梗塞や不整脈などが挙げられ、頻脈、血圧低下、頻呼吸が生じます。呼吸困難や肺水腫を伴うときはカテコラミン投与のほかに、必要に応じて利尿薬を併用し、状態の安定化を図ります。場合によっては、補助循環装置の導入が検討されます。
看護師としては、迅速に情報を集めてアセスメントし、適切な準備・介入を行うことが重要です。
患者さん家族への配慮
患者さんが急変した際に忘れてはならないのが、患者さんの家族に対する配慮です。入院して間もない時期や家族の面会時間帯に急変が生じた場合は、状況を端的に伝えて不安の軽減に努めます。急変現場から一度離れてもらったあともそのままにせず、適宜声かけを行って様子を確認し、心情に寄り添います。
また、HCUの場合、大部屋(例:4人部屋)もありますが、大部屋で急変が生じた場合は、周囲の入院患者さんに対する配慮も必要です。人手がある場合は、他の部屋へ一時的に移動してもらうといった対応をとれるとよいでしょう。