記事一覧
15件/4076件
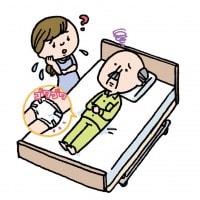
「おむつの重ね付けが基本的にNG」な5つのワケ
「おむつの重ね付けが基本的にNG」のワケ 臨床では、テープおむつやパンツおむつなどの(アウター)中に尿取りパッドを入れて、尿取りパッドだけを取り換えるという方法を多く行っていますが、中には多く尿を吸収しようと何枚もの尿取りパッドを重ねて使用しているケースがあります。

【虐待】医療者に求められる役割とは?
今回は子どもの虐待について、解説します。 生活の中に広く存在する虐待 近年度々報道される子どもへの虐待のニュースを耳にして、心を痛めている方は多いでしょう。 しかし、すべての虐待から見れば、それらはほんの一部にすぎません。 虐待とは、家庭のような密室環境の中で

第14回 みね子、もっと勉強しておけばよかったと思うこと、の巻
日勤が終わり、勉強会をしているSAKURAとスガオ。そこへ、同じく日勤が終わったみね子が通りかかり…。 お疲れさまでーす。お先に失礼します。 くまみー、いいところに通りかかったわね! 絶対、呼び止められると思いましたよ。今日はなんですか? 仕事

呼吸器アセスメント―触診・打診の部位、聴診時の音
▼酸素療法についてまとめて読むならコチラ 酸素療法とは?種類・目的・適応・看護 アセスメントは、患者さんとの会話やケアを通じて全身の状態に目を向け、五感をフルに活用することが大切です。ここでは系統別にフィジカルアセスメントのテクニックをまとめました。普段行って

第4回 どうする? 吸引後にSpO2が上がらない患者さん(その2)
今回は、みなさんがどうアセスメントしたのか、コメントを見ていきましょう。ナース専科マガジン7月号では公開しきれなかったコメントを掲載していきます。 前回記事はこちら どうする? 吸引後にSpO2が上がらない患者さん(その1) 事例 重症心身障害者の患者さんで、

認知症・認知機能障害の看護ケア|原因、症状、アセスメントのポイント
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下のアセスメント方法を紹介します。今回は「認知症・認知機能障害」です。 (2017年7月4日改訂) 認知症・認知機能障害の基礎知識 主な原因疾患は? 認知症の原因疾患に
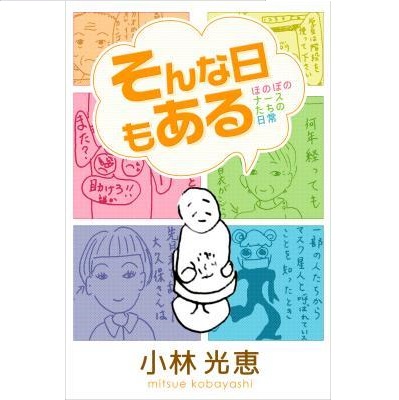
「おたんこナース」原案者・小林光恵さんが描く「看護あるある」が電子書籍に!
元看護師で「おたんこナース」の原案者:小林光恵さんの新著「そんな日もある ~ほのぼのナースたちの日常~」が、電子書籍でリリースされました! 「そんな日もあるさ」と、明日をむかえる前にクスっと笑って次にすすめる、そんな4コママンガ全52作品が収録されています。 作品紹介

第6回 予防から回復までのリハビリテーションの流れ
がんのリハビリテーションでは何を行い、看護師はどのようにかかわることができるのでしょう。看護師に求められる役割、国立がん研究センター東病院の皆さんに話を聞きました。 各段階のリハビリの特徴 がんのリハビリは、病期と治療によって4段階の流れがあり、目的も異なってきま
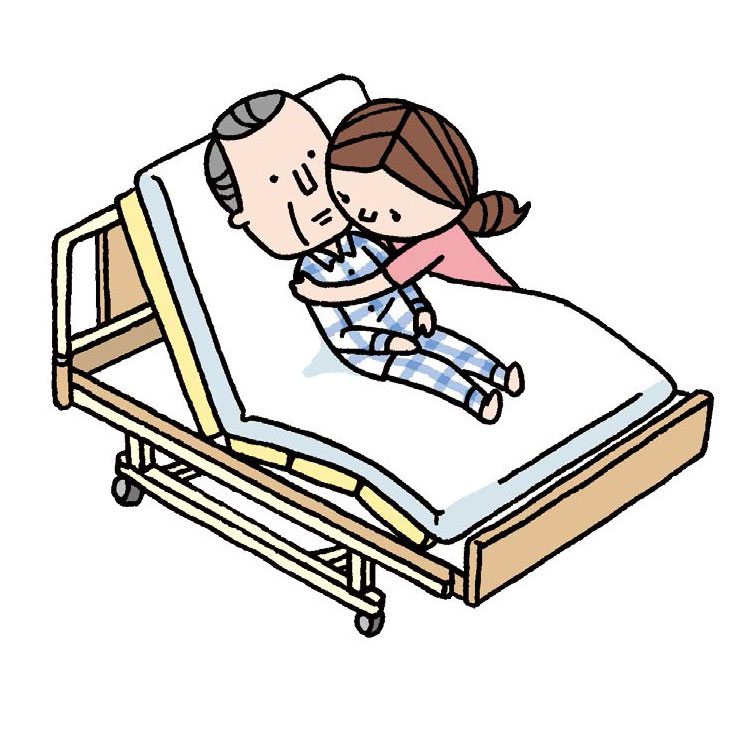
【褥瘡予防】ポジショニングを行うときの6つの注意点
褥瘡の発生リスクを高める要素である「体圧」。これを軽減することができれば、看護ケアにも余裕が生まれます。 効果的なポジショニングを行うことによってうまく体圧をコントロールできれば、褥瘡の発生や悪化を減らすことができます。 覚えておきたいポジショニングを行う際の6つの注
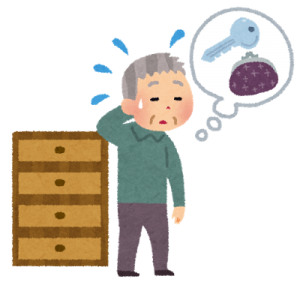
加齢が認知機能へもたらす「5つの悪影響」
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下について解説します。今回は、「加齢がもたらす悪影響」です。 【関連記事】 認知症・認知機能障害の看護ケア|原因、症状、アセスメントのポイント 影響1 記憶力が低下する

【急性膵炎】検査値の看護への活かし方
検査値が何を示しているのか、また検査データを踏まえてどのような看護を行えばいいのか、実際のデータをもとに読み解いてみましょう。今回は、「急性膵炎」です。 事例 入院中の患者さん(男性、77歳)、主訴・症状は以下のとおりでした。 背部・腹部の激しい痛み 検査デー

【薬剤性劇症肝炎】検査値の看護への活かし方
事例 入院中の患者さん(女性、40歳)、主訴・症状は以下のとおりでした。 黄疸 全身倦怠感 検査データ[入院時] 血液一般検査 RBC(万/μl):280 Hb(g/dl):7.3 Ht(%):20 WBC(/μl):6000 棹状核

【看護倫理・事例】第3回 医師にひどい言葉をぶつけられたケース
日々の看護のなかに意外に多く潜んでいる倫理的問題。それらの解決のためには、まず、倫理的な違和感に気づくセンスが必要です。今回は、医療者間に潜んでいる力関係に関するケースをもとに、センスを磨く練習をしていきましょう。 ▼看護師のコミュニケーションとマナーについて、まと
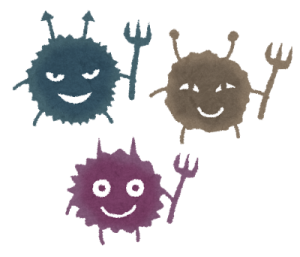
第3回 ナースの業務改善や医療費の負担削減にも貢献!
経口摂取が難しい患者に対する栄養療法の1つ「経腸栄養」。効率よく栄養を摂取できることに加えて、管理が簡便なことから、医療現場だけでなく介護施設でも重宝されています。しかしその反面、合併症の頻度が多く、医療者を悩ませてきました。 そこで今回は、合併症の代表例である「下痢」

【感染性心内膜炎】検査値の看護への活かし方
検査値が何を示しているのか、また検査データを踏まえてどのような看護を行えばいいのか、実際のデータをもとに読み解いてみましょう。今回は、「感染性心内膜炎」です。 事例 持続する発熱で来院した患者さん(男性、57歳)、主訴・症状は以下のとおりでした。 持続する発熱


