摂食・嚥下障害
摂食・嚥下障害関連の記事の一覧です。
嚥下は「先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期」の5つの期に分けられます。摂食・嚥下障害は、これら一連の流れのどこかに問題が起きている状態です。嚥下機能を評価するには、運動機能の検査である反復唾液嚥下テスト(RSST)、改訂水飲みテスト(MWST)、食物テスト(FT)などがあります。そのほか、 食物をかき込むような切迫的な摂食や不適切な介助法ではないかなど、食事場面の観察も必要です。
摂食・嚥下障害 記事カテゴリ
「摂食・嚥下障害」の記事一覧
10件/40件
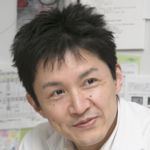
第5回 摂食嚥下リハビリテーションー嚥下訓練と食支援
本連載では、摂食嚥下障害を初めて学ぶ方も理解できるよう、摂食嚥下障害の基本とともに、臨床症状や実際の症例を通じて最新の嚥下リハ・ケアの考え方を解説します。 「嚥下リハ」とはどんなもの? 摂食嚥下リハビリテーション(嚥下リハ)というと、どういうことがイメ
2016/1/18
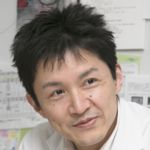
第4回 誤嚥と誤嚥性肺炎の予防―不顕性誤嚥を例に
本連載では、摂食嚥下障害を初めて学ぶ方も理解できるよう、摂食嚥下障害の基本とともに、臨床症状や実際の症例を通じて最新の嚥下リハ・ケアの考え方を解説します。 「ムセ」=誤嚥性肺炎? 「これまで一度も誤嚥をしたことがない」という人はいないでしょう。食事中に
2016/1/11
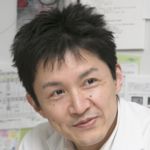
第3回 摂食嚥下障害の検査-嚥下造影検査(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)
本連載では、摂食嚥下障害を初めて学ぶ方も理解できるよう、摂食嚥下障害の基本とともに、臨床症状や実際の症例を通じて最新の嚥下リハ・ケアの考え方を解説します。 摂食嚥下障害の検査にはどんなものがある? 臨床でスタンダードに用いられている摂食嚥下機能の検査に
2016/1/4
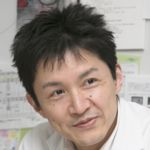
第2回 摂食嚥下障害の原因となる疾患
本連載では、摂食嚥下障害を初めて学ぶ方も理解できるよう、摂食嚥下障害の基本とともに、臨床症状や実際の症例を通じて最新の嚥下リハ・ケアの考え方を解説します。 摂食嚥下障害の原因疾患とは? 摂食嚥下障害(嚥下障害)は「病名」ではありません。そう言われると違
2015/12/28
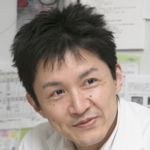
第1回 摂食嚥下障害とは
本連載では、摂食嚥下障害を初めて学ぶ方も理解できるよう、摂食嚥下障害の基本とともに、臨床症状や実際の症例を通じて最新の嚥下リハ・ケアの考え方を解説します。 はじめに みなさんの病棟・外来に摂食嚥下障害(嚥下障害)の患者さんはおられませんか? おそ
2015/12/21

嚥下訓練とは? 摂食・嚥下訓練の目的・対象・実施ポイント
がんのリハビリテーションでは何を行い、看護師はどのようにかかわることができるのでしょう。看護師に求められる役割、国立がん研究センター東病院の皆さんに話を聞きました。 摂食・嚥下訓練の目的 口の中で食べ物を咀嚼し食塊を形成するためには、顎、舌、頬、歯、口
2014/7/25

【摂食・嚥下障害】ケア&対応の6つのワザ
ワザ1 日常ケアに機能訓練を取り入れる 口腔機能訓練を無理なく継続するためには、日常のケアの中にちょっとした機能訓練を取り入れていくとよいでしょう。 例えば、顔を拭くときに頬の筋肉をマッサージしたり、体位変換ごとに首の後ろや肩の部分をマッサージすることで、筋肉
2014/7/18
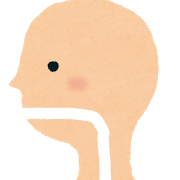
【摂食・嚥下障害】アセスメントの3つのポイント
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下のアセスメント方法を紹介します。今回は「摂食・嚥下障害」です。 1 日々のケアの中でも嚥下機能を観察する 摂食・嚥下障害は、高齢者に起こりがちです。日頃から注意す
2014/7/15
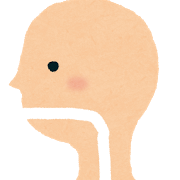
加齢が摂食・嚥下にもたらす「4つの悪影響」
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下について解説します。今回は、「加齢がもたらす悪影響」です。 影響1 嚥下筋の筋力が低下する →嚥下障害(むせ・誤嚥)/誤嚥性肺炎 嚥下では、口腔期、咽頭期、
2014/7/14

【誤嚥性肺炎を予防】摂食・嚥下障害の観察・ケアのポイント
誤嚥性肺炎の原因と症状 摂食・嚥下障害に付随して起こる可能性のある誤嚥性肺炎の原因と症状について解説します。 誤嚥性肺炎はどうして起こるの? 一番の原因は加齢による機能低下と抵抗力の低下です。 口腔、咽頭、食道などの嚥下筋力が低下して、食道に運ばれるべき食物や
2012/12/10


