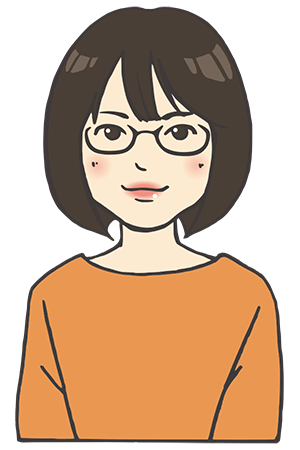摂食嚥下障害の看護|原因、検査、摂食嚥下リハビリテーション(嚥下訓練)、看護計画
摂食嚥下障害の看護|原因、検査、摂食嚥下リハビリテーション(嚥下訓練)、看護計画
- 公開日: 2022/2/28
摂食嚥下障害とは
食物を口から取り込み、食道を通って胃に送り込む一連の動きを摂食嚥下といい、次の5期に分類されます。
①先行期:視覚、嗅覚、触覚などで食物を認知し、口に運ぶ段階 ②準備期:口腔内に取り込んだ食物を咀嚼して唾液と混合し、嚥下しやすいよう食塊を形成する段階 ③口腔期:舌、頬、口唇を使い、準備期で形成された食塊を咽頭に送る段階 ④咽頭期:食塊を咽頭から食道に送り込む段階 ⑤食道期:食塊を食道から胃に送り込む段階
摂食嚥下障害とは、この一連の動きのどこかに不具合が生じた状態を指します。代表的な症状として、食物をうまく口に運べない、噛めない、飲み込めない、むせるなどが挙げられます。摂食嚥下障害による誤嚥や窒息により、生命の危機を招く可能性もあります。
【関連記事】 ●第1回 摂食嚥下障害とは
摂食嚥下障害の原因
摂食嚥下障害の原因は、大きく次の3つに分けられます。
運動障害性嚥下障害
嚥下機能に何らかの障害が起こっているもので、原因疾患として、脳血管障害、パーキンソン病、脳腫瘍、脳性麻痺、筋委縮性側索硬化症(ALS)、シェーグレン症候群、顔面神経麻痺などが挙げられます。
症状は疾患によりさまざまですが、例えばパーキンソン病の場合、先行期ではうつや認知障害による摂食障害が起こる場合があるほか、準備期では上肢の運動障害、口腔期では流涎や口渇、咽頭期では首下がりなどによる咽頭・喉頭の運動障害、食道期では上部食道括約筋の機能不全などによる嚥下障害をきたす可能性があります。
器質的嚥下障害
口腔・咽頭の腫瘍、腫瘤による通過障害・圧迫、外傷、口唇口蓋裂や食道奇形など、口腔から食道にかけて何らかの問題が生じることで、一連の摂食嚥下が機能しなくなります。
通常、口腔期では舌と軟口蓋とを密着させ、口腔内圧を高めることで咽頭に食塊を流し込みます。しかし、構造に問題がある状態では口腔内圧を十分に高めることができず、送り込みがうまくいきません。腫瘍がある部位や切除範囲によって障害の程度や表れ方が変わり、範囲が広いほど障害は重度になる可能性が高くなります。
機能性嚥下障害
運動障害や器質的異常以外の原因によって起こるものです。例えば、口内炎や急性咽喉頭炎のように摂食嚥下時に痛みを伴うもの、食欲不振や拒食症といった心因性のもの、加齢などがこれにあたります。特に高齢者では、唾液分泌量や咀嚼力の低下、口腔内常在菌叢の変化、喉頭反射・咳嗽反射の低下を認めます。呼吸器疾患などの基礎疾患をもっている患者さんも多く、誤嚥性肺炎の発症にも注意を払う必要があります。
【関連記事】 ●第2回 摂食嚥下障害の原因となる疾患
摂食嚥下機能の検査
摂食嚥下機能を評価するための検査には、X線や内視鏡を用いて実施される精密検査、ベッドサイドや在宅でも行える簡易検査(スクリーニングテスト)があります。
精密検査
嚥下造影検査(Videofluoroscopic exa-mination of swallowing:VF)
造影剤を含んだ食品をX線透視下で摂取してもらいます。口腔・咽頭・食道の動き、食べ物の動きを撮影・記録し、誤嚥の有無を確認します。VFは嚥下の瞬間を確認できるため、嚥下機能評価のゴールドスタンダートとされていますが1)、2)、被曝を伴うほか、造影剤アレルギーなどを引き起こす可能性がある点がデメリットといえます。
嚥下内視鏡検査(Videoendoscopic examination of swallowing:VE)
鼻腔から内視鏡を挿入し、安静時および嚥下時の咽頭・喉頭の動きを観察する検査です。内視鏡挿入時に苦痛が生じるものの、被曝がなく、携帯性に優れるため、ベッドサイドや在宅でも検査できる点がメリットとして挙げられます。
【関連記事】 ●第3回 摂食嚥下障害の検査-嚥下造影検査(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)
簡易検査(スクリーニングテスト)
反復唾液嚥下テスト(repetitive saliva swallowing test:RSST)
30秒間で空嚥下(唾液の飲み込み)が何回できるかを確認します。道具を使わないため、簡便かつ安全に実施できるテストです。ただし、認知症などで指示を理解することが困難な場合、意識レベルが低下している場合、常に唾液を誤嚥する場合での実施は避けます。
【手順】 ①患者さんにテストの目的を説明し、実施の同意を得る ②患者さんの喉頭隆起と舌骨に、人差し指と中指を当てる ③30秒計測し、時間内に空嚥下した回数をカウントする
喉頭隆起は1回の嚥下運動で1回上下します。高齢者の場合、一般的に3回以上で正常、2回以下の場合は嚥下機能低下を認めると評価します。
改定水飲みテスト(Modified Water Swallowing Test:MWST)
冷水を使用し、実際の嚥下状態を評価するテストです。反復唾液嚥下テスト同様、指示を理解するのが困難な場合や、意識レベルが低下しているケースでの実施は控えましょう。
【手順】 ①物品を準備する(10mLシリンジ1本、冷水入りコップ、タオル、吸引器) ②患者さんにテストの目的を説明し、実施の同意を得る ③冷水3mLを患者さんの口腔底に注ぎ、嚥下するように促す ④可能であれば、嚥下後、2回反復嚥下をするように声をかける ⑤評価基準と照らし合わせ、スコア4以上の場合は、さらに最大2回テストを繰り返す ⑥実施したテストのうち、最低スコアを結果とする
MWST評価基準
| 1 | 嚥下なし、むせるand/or呼吸切迫 |
|---|---|
| 2 | 嚥下あり、呼吸切迫 |
| 3 | 嚥下あり、呼吸良好、むせるand/or湿性嗄声 |
| 4 | 嚥下あり、呼吸良好、むせなし |
| 5 | 4に加え、反復嚥下が30秒以内に2回可能 |
【関連記事】 ●【摂食・嚥下障害】アセスメントの3つのポイント
摂食嚥下障害のリハビリテーション(嚥下訓練)
嚥下機能訓練は、患者さんの嚥下機能を評価した上で一人ひとりに適した方法を選択します。訓練には食物を用いない「間接的訓練」と、実際に食物を口に含む「直接的訓練」があります。
間接的訓練
間接的訓練は、一連の摂食嚥下行動にかかわる臓器の機能改善を目的とし、意識レベルが低い患者さんや誤嚥リスクが高い患者さんで実施されます。場合によっては、直接的訓練と並行して行われることもあります。さまざまな訓練法がありますが、ここでは、「嚥下体操」と「のどのアイスマッサージ」について紹介します。
嚥下体操
嚥下にかかわる筋肉をほぐすことを目的に実施される基礎訓練で、食事の前に行います。患者さんの覚醒を促す効果も期待できます。
【手順】 ①口をすぼめ、ゆっくり深呼吸する ②首の回旋運動を行う ③肩の上下運動を行う ④両手を頭上で組み、体幹を左右に側屈させる(胸郭の運動) ⑤頬を膨らませたり引っ込めたりする ⑥舌を前後に出し入れする ⑦舌で左右の口角にさわる ⑧強く息を吸い込む(咽頭後壁に空気刺激を入れる) ⑨パタカラ体操を行う(発音訓練) ⑩口をすぼめ、ゆっくり深呼吸する
※①~⑩を1セットとして実施する ※上記は一例。患者さんの状態に応じて、組み合わせや方法が工夫される
日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会:訓練法のまとめ(2014年版)日本摂食嚥下リハ会誌2014;18(1):57.(2022年2月25日閲覧)https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/18-1-p55-89.pdf#page=18を参考に作成
のどのアイスマッサージ
嚥下反射を誘発させるために実施します。あらかじめ凍らせておいた綿棒を水に浸し、前口蓋弓、舌根部、軟口蓋、咽頭後壁をなぞります。嚥下体操は指示理解に乏しいと実施が困難ですが、アイスマッサージは、意識レベルが低下している場合や開口困難なケースにも適しています。
直接的訓練
直接的訓練は実際に食物を口に含んで行う訓練のため、嚥下機能評価がなされた上で、適切な手技と観察のもと実施する必要があります。間接的訓練と同様、あらゆる方法がありますが、ここでは、「交互嚥下」「複数回嚥下」「一口量の調整」について紹介します。
交互嚥下
固形物と流動物のように性状が違う食塊を交互に摂食・嚥下することで、口腔内に食物が残らないようにします。口に含む量はそれぞれ同量となるように声をかけ、食事終了時には流動物や水分を最後に摂取するように促します。誤嚥を認める場合はとろみをつけます。
複数回嚥下(反復嚥下)
嚥下後に空嚥下を促し、食物の停滞を防ぐ方法です。この訓練は患者さんが空嚥下できることが前提に実施されます。食物残留の自覚がない患者さんも多く、慣れるまでは空嚥下を忘れないように適宜声かけを行います。空嚥下の回数は1回以上です。訓練者は、空嚥下で喉頭隆起がしっかり上下しているかを確認します。
一口量の調整
嚥下後にまだ食物が口腔内に残っている場合は、一口量がその患者さんにとって多すぎる可能性を考え、一口量の調整を行います。量を減らしすぎても嚥下がしづらくなってしまうため、嚥下の状態や残留量を確認しながら適量を探していきます。
摂食嚥下障害の看護
観察項目、アセスメント
摂食嚥下障害は高齢になるほど多くみられ、適切に対処しないと誤嚥性肺炎を発症し、死に至ることもあります。食事の状況や患者さんの状態などを確認・理解したうえで、身体所見や検査データを組み合わせてアセスメントを行い、摂食嚥下障害やそのリスクが高い患者さんを早期に発見することが重要です。
【主なアセスメント項目】 ・既往歴、基礎疾患(脳血管疾患、神経疾患、認知症など) ・内服歴 ・バイタルサイン ・呼吸器症状 ・嚥下障害の程度(ムセ・嗄声・咳込みなど) ・現在の食事形態と食事量 ・食物貯留の有無 ・食事時の姿勢 ・食事に要する時間 ・水分摂取量 ・排泄状況 ・血液データ ・胸部単純X線画像
摂食嚥下障害のケア
食事介助(食事スピード、一口量の調整)
食事介助の際は、時間内に食べてもらうことに意識が向いてしまい、口に運ぶペースが速くなったり、一口量が多くなってしまったりする場合があります。患者さんが嚥下したことを確認してから次の食物を口に運ぶようにし、急かせたりしないよう心がけます。また、一口量は患者さんの口に入り、咀嚼できる量に調整することが大切です。
体位の調整
食事による誤嚥が生じないよう体位を調整します。例えば、ベッド上で食事をする場合は、足底や両肘、膝下に枕やクッションを当て、姿勢を安定させます。下顎挙上位は誤嚥しやすくなるため、頭部に枕を当てて頸部前屈位を保持し、誤嚥を予防します。
口腔ケア
摂食嚥下障害の患者さんに口腔ケアを実施することは、大変重要です。口腔内を清潔に保つことができ、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。さらに、ブラッシングが刺激となり、唾液分泌の促進も期待できるため、可能であれば、食事前後に行うとよいでしょう。
【関連記事】 ●【誤嚥性肺炎を予防】摂食・嚥下障害の観察・ケアのポイント ●【図解】誤嚥を防ぐポジショニング ●食事介助の看護|観察項目・注意点・手順 ●第25回 摂食嚥下障害の臨床Q&A「口腔ケアを嫌がる患者さんにどう対応する?」 ●第26回 摂食嚥下障害の臨床Q&A「口腔ケア時のブクブクうがいでむせてしまうとき、どうすればよい?」
看護計画
「嚥下障害により食欲が低下している患者さん」を例に看護計画を紹介します。
看護問題 #1誤嚥ハイリスク状態 #2食欲低下に伴うたんぱく質・エネルギー低栄養状態
看護目標 ・誤嚥を起こさない ・食事の工夫によって食欲が回復し栄養状態が改善する
1.誤嚥を起こさない 観察計画(O-P) ・バイタルサイン ・呼吸器症状 ・嚥下障害の程度(ムセ・嗄声・咳込みなど) ・現在の食事形態と食事量 ・食物貯留の有無 ・水分摂取量 ・排泄状況 ・血液データ ・胸部単純X線画像 ・服用している薬剤の種類
ケア計画・援助計画(T-P) ・食前に嚥下訓練を実施する ・嚥下がスムーズに行えるように姿勢を調整する ・意識レベルや覚醒状態を確認した上で食事を提供する ・嚥下機能に合わせて食事形態を調整する ・患者さんの嚥下機能に合わせた食事介助 ・空嚥下を促す ・口腔ケア ・食後の頭部挙上 ・吸引
教育計画(E-P) ・誤嚥性肺炎のリスクを説明する ・嚥下訓練や口腔ケアの必要性を説明し、実施できるように指導する ・一口量を調整する ・嚥下機能に合わせて水分にとろみをつける
2.食事の工夫によって食欲が回復・維持でき低栄養状態を回避する 観察計画(O-P) ・食事量 ・水分摂取量 ・体重の変動 ・皮膚状態(弾性・乾燥など) ・食欲の有無 ・食事に対する興味や意欲の有無 ・現在の食事形態への不満の有無 ・血液データ ・服用している薬剤の種類 ・ストレスの有無 ・誤嚥性肺炎の既往 ・基礎疾患(認知症や心因性疾患の有無)
ケア計画・援助計画(T-P) ・誤嚥に対する恐怖心がないか確認する ・食事形態や使用する食材を工夫する(おいしそうな見た目、季節の食材の使用など) ・食事が楽しくなるよう、環境を整える(複数人での食事、イベントを取り入れるなど) ・適切な姿勢を保持する ・栄養補助食品の活用
教育計画(E-P) ・患者さんや家族に低栄養状態の危険性について説明する ・栄養士による栄養指導の実施 ・患者さんの嚥下機能に合わせた栄養補助食品を紹介する
参考文献
1)稲本陽子,他:高齢者の嚥下障害に対する治療指向的評価の重要性.J of Clinical Rehabilitation 2016;25(8):764-73. 2)Rofes L,et al:Diagnosis and management of oropharyngeal Dysphagia and its nutritional and respiratory complications in the elderly.Gastroenterol Res Pract.2011.カテゴリの新着記事
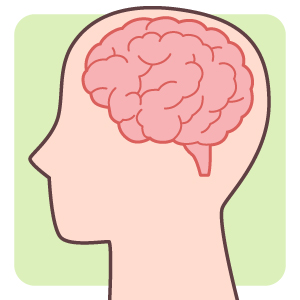
脳卒中で低下した嚥下機能を改善させるために看護師ができることが知りたい!
Q.脳卒中により低下してしまった嚥下機能を少しでも改善させるために、看護師ができることはありますか? A.嚥下機能の評価、食形態の調整、食事介助、ベッドサイド上での訓練など、看護師が日常のケアでできるアプローチは多くあります。 看護師が介入することの重要
-
-
- 加齢による誤嚥リスクがある患者さんに関する看護計画
-
-
-
- 統合失調症の看護|原因、病型、症状、治療、看護計画など
-
-
-
- 食事介助に関する看護計画|嚥下機能が低下してきている認知症患者さん
-
-
-
- 食欲不振のある患者さんへの看護計画
-