記事一覧
15件/4074件
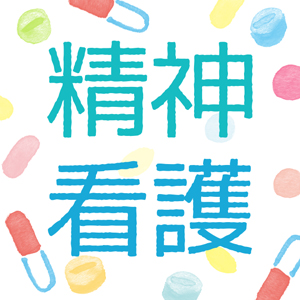
精神疾患の患者さんの家族を理解しよう
精神科看護における家族理解 看護ケアを実践するとき、家族を含めた支援を考えることはとても重要です。患者さんにとって家族の存在は大きく、日々の実践の中で重要性を感じることができるでしょう。今回は、精神科患者さんの家族ケアに必要な視点を整理します。 まずは、臨床的

60歳以上の男性の2人に1人が罹患、前立腺がん診断・治療の最前線〜がんのみを治療、機能温存によるQOLの向上を目指す〜
2018年1月31日、東海大学校友会館にて「60歳以上の男性の2人に1人が罹患、前立腺がん診断・治療の最前線~がんのみを治療、機能温存によるQOLの向上を目指す~」をテーマにプレスセミナーが行われました。演題は「前立腺内部の3次元的がん局所診断とがん局所療法(フォーカルセ
第8回 角化した部位のケア・実践
前回は足裏の角化の観察をして、ケアを選択しました。 今回は実際のケアをご紹介します。 1.角質を除去する方法 正常な皮膚はターンオーバーを行い、余分なものは自力で落としますが刺激が加わったり、ケア不足が続くと角質がかたく、厚くなり正常な働き

温罨法の手順〜根拠がわかる看護技術
▼急変対応について、まとめて読むならコチラ 急変時の対応 温罨法(湯たんぽで下肢を温める場合)の手順 湯たんぽを使用して下肢を温めることを目的とした温罨法の方法について説明します。 必要物品 湯たんぽ(ゴム製・プラスティック製
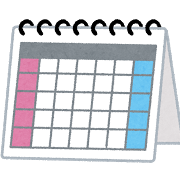
日本看護教育学学会第28回学術集会 開催のお知らせ
日本看護教育学学会は、看護教育学の発展を図り、広く知識の交流を深めることを目的としています。 開催日 2018年8月22日(水) 会場 前橋テルサホール(前橋市千代田町2丁目5番1号) テーマ 看護職者の教育役割遂行に向けた知の集積

ムンテラとは|方法とコツ
※一般的な方法を紹介しています。実施にあたっては各施設の方法にしたがってください。 ムンテラとは? ムンテラはドイツ語の「MundTherapie」から派生した略語で、医師から患者さん、もしくは家族に、現在の病状や今後の治療方針などを説明することをいいます。

【シリーズ第1弾 心電図って面白い!】 第2話 イオンチャンネルと膜電位
今日は週に一回、平手教授がC大学からE病院へ集中管理や手術の邪魔をしに、じゃなくて指導をしにやって来る日です。あらあら、今回も待ち構えているのは看護師のたくみ君と美和さんのようです。 ところでイオンチャンネルって何? たくみ君「先生、待ってました。先週
乳がん手術後の方に、下着の有用性について検証しました【PR】
グンゼ株式会社と地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンターは、乳がん術後患者のQOL向上のために、グンゼが新たに開発した下着の有用性について、共同研究を行いました。 皮膚症状について ■外科手術後患者の自覚症状 手術後の傷口に痛みを感
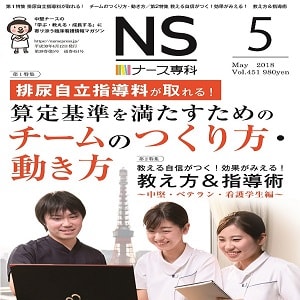
ナース専科2018年5月号『排尿自立指導料が取れる! チームのつくり方・動き方』
事例やQ&Aで排尿自立指導料がわかる! 第1特集のテーマは、「排尿自立指導料」についてです。2016年4月の診療報酬改定において「排尿自立指導料」が設置され、看護領域においても排尿ケアへの関心が高まっています。一方で、制度や排尿ケアに関する知識・技術のブラッ

希少・難治性疾患患者のQOL向上を目指して 「つながるちから ~Take Action Now~」
2018年2月1日、大手町サンケイプラザにて「2月28日は『Rare Disease Day 2018』(世界希少・難治性疾患の日) 希少・難治性疾患患者のQOL向上を目指して『つながるちから~Take Action Now~』」をテーマにプレスセミナーが行われました。講

環境整備とは|看護師が行う意義と目的、方法~根拠がわかる看護技術
【関連記事】 * 第10回【環境管理編】環境整備の実施回数は多いほどいい? * 清拭の目的と看護師が行う意義、手順 * ベッドメイキング 見直そう! 5つのポイント 環境整備の意義・目的 病室は、患者さんの治療の場であるとともに生活の場です。患者

クーリング(冷罨法)とは|目的と方法〜根拠がわかる看護技術
【関連記事】 ● 温罨法とは|目的・効果・注意点 〜根拠がわかる看護技術● 温罨法の手順〜根拠がわかる看護技術 クーリングとは クーリングとは、後頭部、鼠径部、腋窩、頸部、背部といった体幹付近、または表在性に大きな動脈のある部位や炎症部位を冷却
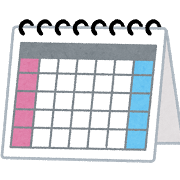
日本看護技術学会第17回学術集会 開催のお知らせ
看護師が行っているさまざまな技術について、その効果とメカニズムを科学的手法を用いて明らかにすること、また、経験的知識を発掘してその根拠を探索すること等により、さらなる看護技術の開発を目指している看護技術学会が、9月8日〜9日で学術集会を開催します。 日時

温罨法とは|目的・効果・注意点 〜根拠がわかる看護技術
関連記事 * 温罨法の手順 * クーリング(冷罨法)とは|目的と方法 温罨法とは 身体の一部に温熱刺激を与える(温める)看護技術です。患者さんの安楽・精神的安定のために重要なケアです。 どんなときに行う? 治療として医師が指

精神科患者さんに多い身体合併症を知っておこう!
精神科疾患の患者さんの身体疾患の特徴 近年、精神疾患をもつ患者さんの身体的な健康問題に注目が集まっています。精神科患者さんは、一般の人口にくらべて10年から20年程度寿命が短いという調査もあり、原因の究明や対策について議論が始まっています。 精神科患者さん


