記事一覧
15件/4080件

膀胱洗浄の目的と手順〜根拠がわかる看護技術
関連記事 * 【尿道留置カテーテル関連編】一番効果のある感染防止策は? * 陰部洗浄の目的・手順・観察項目〜根拠がわかる看護技術 膀胱洗浄とは 膀胱洗浄とは、主に膀胱留置カテーテルを留置中の患者さんを対象として、カテーテルを使用して膀胱内

タッチングとは|ケアの方法と効果〜根拠がわかる看護技術
タッチングとは? 看護におけるタッチング タッチングとは、非言語的コミュニケーションの一つで、患者さんの身体に触れることをいいます。 タッチングには、マッサージや指圧など、治療を目的とするタッチング、バイタルサインの測定や清拭、検査など処置目的のタッ

ナース専科2018年4月号『再入院&悪化を防ぐ!慢性心不全患者のセルフマネジメント支援』
事例をもとにわかりやすく解説! 第1特集のテーマは「慢性心不全患者のセルフケア支援」。再入院や悪化を防ぐために、「認定看護師はどのようにアセスメントし、支援をしているのか」、よくある事例をもとに思考過程や具体的な実践を解説します。 第2特集では、新人・若手看護
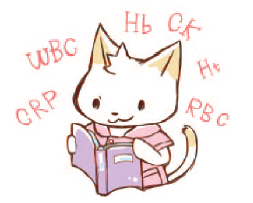
【肺炎とは?】肺炎の検査値(データ)はココを見る!
肺炎の看護に必要な検査データをピックアップしました。 (2018年3月7日改訂) 肺炎とは? 肺炎とは、細菌などが主に気道を介して肺に感染し、炎症を起こした病態です。炎症反応に伴い発熱や頭痛、悪寒、関節痛などの全身症状や、脈拍や呼吸数が増加し、脱水が起
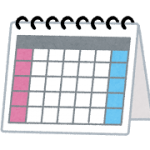
第23回日本小児ストーマ・排泄・創傷管理セミナー お知らせ
会期 2018年6月14日(木)15日(金)16日(土) 14日10時開始 16日17時終了予定 研修内容 ストーマ術前術後のケア(低出生体重児を含む)、創傷ケア(褥瘡予防・局所ケア)、 失禁ケア(尿・便失禁、自己導尿指導等) ※当セミナーは、人工
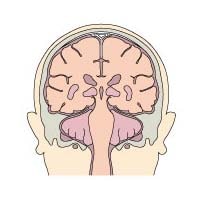
脳卒中急性期の栄養管理 嘔吐・逆流に対する乳清ペプチド消化態流動食の有用性【PR】
POINT ●早期経腸栄養の有用性は各種ガイドラインで示されており、脳卒中急性期も同様に早期経腸栄養が有用である。しかし、逆流・嘔吐を懸念するあまり積極的な開始がなされていない場合が多い。 ●脳卒中急性期の絶飲食・点滴での栄養管理により、消化管の廃用性機能障害や栄

進行乳がん治療におけるパラダイムシフトとは
11月20日、ベルサール八重洲にて「新規の乳がん治療薬、イブランス®の承認取得 本邦初のCDK4/6阻害剤で進行・再発乳がんに新たな治療選択肢 進行乳がん治療におけるパラダイムシフトとは」をテーマにプレスカンファレンスが開催されました。今回の講演では主に、CDK4/6阻害

こまち麻酔フォーラム2017 麻酔科領域の物理学と医療安全【PR】
2017年8月31日、秋田キャッスルホテル(秋田県秋田市)において「こまち麻酔フォーラム2017」が開催されました。 「麻酔科領域の物理学と医療安全」セミナーでは、東北医科薬科大学麻酔科学の河野達郎先生の座長のもと、東北大学病院麻酔科の外山裕章先生、東北大学病院薬剤部の
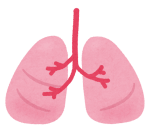
第23回3学会合同呼吸療法認定士認定講習会及び認定試験のお知らせ
3学会(特定⾮営利活動法⼈ ⽇本胸部外科学会、⼀般社団法⼈ ⽇本呼吸器学会、公益社団法⼈ ⽇本⿇酔科学会)合同呼吸療法認定⼠認定委員会は、学会認定制度による「3学会合同呼吸療法認定⼠」の認定を⾏うため、標記認定講習会および試験を下記の通り実施します。 認定講習会につ

事例:パーキンソン病患者の転倒対策における事例検討【PR】
国立精神・神経医療研究センター病院は、精神疾患、神経・筋疾患、発達障害を専門とするナショナルセンター病院であり、神経難病病棟におけるパーキンソン病患者さんの割合はおよそ7割に及びます。豊富な事例をもつ同院から、転倒対策を行った例と医療・福祉サービスを利用して在宅へ移行した
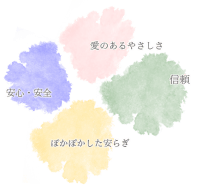
在宅での点滴の実施方法について知っておこう!
1日でも長く在宅での生活を希望されている方が増えてきました。それに伴い、在宅で実施できる医療も拡大をしてきています。近年、日本人の死因第3位が肺炎になりました。在宅療養において、肺炎や軽度感染症治療のために実施する補液や抗生剤の点滴の依頼も増加しています。 今回は、

2.睡眠時無呼吸症候群の合併症(睡眠時無呼吸症候群を放置するとどうなるか)について知ろう
今回は、睡眠時無呼吸症候群の合併症について解説します。事例のように精密検査に消極的な患者さんにどのようにアプローチをするとよいのか、睡眠時無呼吸症候群を放置するとどのような状態になるのかについて紹介していきます。 【事例】 45歳のAさんは簡

心不全による消化器症状(嘔吐、便秘など)とは?
消化器症状を、心不全と関連付けて考えることは、なかなか難しいことです。そこで今回は心不全による消化器症状とその原因について解説します。 2018年2月23日改訂 ▼心不全の看護について、まとめて読むならコチラ 心不全の看護|原因、種類、診断、治療

第2回 日本エンド オブ ライフ ケア学会学術集会
すべての人が意思表明を支えあうケア 「第2回学術集会」一橋大学一橋講堂にて開催 - エンドオブライフにむけて- 1.生活の場から発信するACP ―エンドオブライフに向けた意思表明支援― 2.元気なときからかかわるACPの実践 ―多職種による関わりから―

パーキンソン病患者が利用できる医療福祉サービス【PR】
パーキンソン病は、進行とともに姿勢保持や歩行の障害、認知機能の低下などを生じます。疾患への理解を深め、適切に看護できる人材の育成を目的に、日本パーキンソン病・運動障害疾患学会が主催となり、「PDナース研修会」が開かれています。2017年10月28日には、東京品川で行われた


