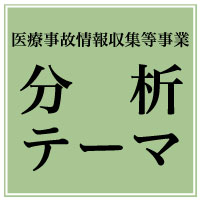【連載】知っておきたい! 在宅での必要な手技と医療機器・医療材料の取り扱い
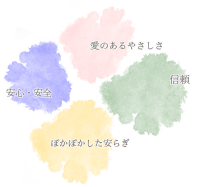 在宅での褥瘡対策とケアについて知っておこう!
在宅での褥瘡対策とケアについて知っておこう!
- 公開日: 2018/1/31
褥瘡とは
「褥瘡」とはなんでしょう。今でこそ「褥瘡」という単語は、医療従事者の間では認知されつつありますが、まだまだ一般的な言葉として浸透していません。訪問先の担当の方やご家族様に、「褥瘡って何ですか?」と聞かれることが、多くあります。「床ずれ」という単語の方が70歳以上の方には馴染みやすい言葉であるようです。相手の理解度をみながら、使用する単語は使い分けるとよいでしょう。単語自体も馴染みがないのに、一体何が褥瘡なのか正確にご存知の方はなかなかいらっしゃいません。
褥瘡とは、骨突出部位に限局する消退しない発赤からが褥瘡です。「骨ばっているところの赤くなっているところを押してみて、白くならなかったらそれは褥瘡ですよ」と、説明すると、理解されやすいです。「えっ! 赤いだけでもう褥瘡なの!?」と驚かれる方も少なくありません。看護師にとっては当然の知識ですが、正しい知識をまず提供して、知ってもらうことが看護師として大切なことです。
褥瘡発生した理由をアセスメントする
発生した褥瘡を治癒させるには、外用治療等と併せて、発生した原因をアセスメントし、改善を促すことが重要です。以下のようなこと確認するようにします。
●普段どのような体勢で過ごされているか
(座ることが多い、臥床していることが多い、テレビを観るために側臥位になっていることが多い等)
●食事量や食事内容に変化はないか
(栄養状態は低下していないか)
●排泄状況は変わりないか(失禁が増えていないか)
褥瘡発生因子となりうるさまざまな視点からアセスメントを行い、ご家族やケアマネジャーと連携をとりながら、介護サービス内容を見直したり、介護者に適切な助言をします。例えば、急にADLが低下し、臥床時間が長くなってしまった場合、今までエアマットを使用していなければ、エアマットに変更や、座位保持時間が長く坐骨に褥瘡発生した場合は、褥瘡予防用のクッションの導入をケアマネジャーに提案します。ケアマネジャーより頻繁かつ定期的に訪問する看護師のほうが、ご活用者様の変化に気付くことが多いため、情報共有をその都度漏れなく行うようにしています。早め早めの対応が、褥瘡の悪化予防にも繋がるので重要です。
褥瘡の深度に合わせたケア~急性期編~
皮膚損傷のない発赤のみの褥瘡の場合は、ワセリン塗布やフィルム材貼付の対応となります。ワセリンの塗布は急性期の褥瘡の発赤に対する皮膚保護のため、フィルム材貼付は骨突出部の褥瘡予防のために行います。
ワセリンは割と自宅にあることが多いので、自宅にあればワセリンを選択しています。気軽に手に入れやすいものなので、ワセリンは重宝するものですが、外用薬は毎日塗布する必要があるので、もし自分で塗布しにくい部位の場合、介護状況によっては、フィルム材の貼付を選択します。フィルム材は自宅にないことが多いので、その場では看護師の手持ちのものを使用し、次回の訪問までにドラッグストアで調達していただくようお願いします。フィルム材は最長一週間貼付してよいものなので、週に1回の看護師訪問の場合、仮に介護者がいらっしゃらない場合も適しています。介護状況やご本人様の希望や理解力によって、適したケア内容を提案することが大切です。
褥瘡の深度に合わせたケア~洗浄を必要とする褥瘡編~
皮膚欠損を伴う褥瘡は、創周囲を洗浄する必要があります。一般的に、「傷はイソジンやアルコール等の消毒液で消毒するもの」と、思われていることが多いです。特にご高齢の方は創部にイソジン消毒をする方が多く、現場でもよく目にします。消毒は、石鹸での洗浄が現在は有効的だとされています。
具体的な方法としては
①洗浄剤や石鹸を泡立て、創周囲にのせるように置き、やさしく洗浄する
②人肌程度のお湯で充分に洗い流す
③創部は微温湯で洗浄する
④不織布などで水分を拭き取る
という順序で行います。
①では、泡立てた石鹸を使用することが重要なので、泡で出てくる石鹸や、泡立てネットの使用をお薦めしています。泡立てネットは100円均一で手に入れることができますし、ビニール袋に少量のお湯と洗浄剤を入れて振ることで泡立てることもできます。
②で、石鹸を洗い流す際には、介護用品店で購入できる陰部洗浄用ボトルや、ペットボトルのふたにキリで穴をあけたものを使用するようにしています。ペットボトルのふたに穴をあけたものは普段いくつか持ち歩き、必要時ご活用者様にお渡ししています。
③では、創部は石鹸で洗う必要はなく、微温湯で洗い流すようにします。
④で、拭き取るものは、いらなくなった衣類や、ティッシュを使用するようにしています。ご活用者様に合わせてコスト面や簡便性を考えて、使用するものを提案します。
在宅において大事なこと
在宅は、病院という何でも物品が揃っている環境とはまるで異なりますし、常に医療職がそばにいるわけではありません。ご活用者様が自宅でその人らしく安全で安心できる生活を送るために、私たち訪問看護師が、工夫しながら、ご活用者様の理解力や経済状況や生活スタイルに合ったケア方法を提供することが、在宅ではとても大事です。
カテゴリの新着記事

臀部に発赤のある患者さんに関する看護計画
臀部に発赤のある患者さんに関する看護計画 加齢による筋力低下や原疾患によるADL低下から臀部が長時間、圧迫されると発赤が生じることがあります。そこに湿潤環境、循環不全、炎症が生じることで褥瘡が発生する可能性があるため適切に対応していく必要があります。今回は臀部に発赤がある
-
-
- スキントラブルが起きやすい患者さんのケアで気をつけることは?【PR】
-
-
-
- ワセリンを塗布していて浸軟してしまった皮膚はどうケアする?【PR】
-
-
-
- 褥瘡にポケットがある患者さんへの在宅でできるケアの工夫とは?【PR】
-
-
-
- 清潔ケアへの拒否が強い患者さんへのケア、どうする?【PR】
-