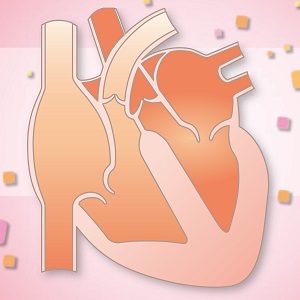 抗血栓薬の種類・作用機序と使い分け
抗血栓薬の種類・作用機序と使い分け
- 公開日: 2019/4/20
心血管イベントの原因となる各種血栓の形成は、血液の凝固系と深いかかわりをもっています。そこで抗血栓薬が凝固系の特定の場所に働きかけ、凝固を抑制していくメカニズムと使い分けを解説します。
1. 血栓症、塞栓症に使う薬とは
血栓症、塞栓症はどちらも血液が凝固することにより起こる疾患です。血栓症は血液の凝固(血栓)が起きた場所にとどまり、そこで症状をもたらすもの、塞栓症は血液の凝固(血栓)が起きたところから遊離して血流にのって別の場所に運ばれ、そこで血管に詰まり症状をもたらすものです。
血栓症、塞栓症の薬は、抗血小板薬、抗凝固薬に分けられます。病棟でしばしば遭遇するのが、心房細動で心房にできた血栓が脳動脈に詰まる脳塞栓、下肢静脈にできた血栓が肺動脈に詰まる肺塞栓です。血栓は、血小板血栓とフィブリン血栓に分けられます。血小板血栓は、血小板を多く含み色が白く見えることから、白色血栓とも呼ばれます。フィブリン血栓は、赤血球を多く含み色が赤く見えるので、赤色血栓とも呼ばれます。
血小板血栓ができる最初のきっかけは血小板の活性化です。血流の速いところではずり応力と呼ばれる物理的力が内皮や血球に働き、血流と内皮・血球の間に抵抗が生じます。
参考になった
-
参考にならなかった
-






