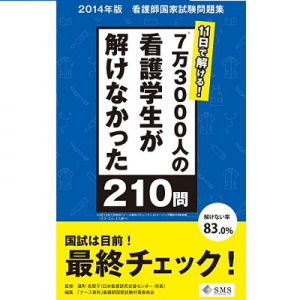関節リウマチ治療のパラダイムシフトと今後の展望~
関節リウマチ治療のパラダイムシフトと今後の展望~
- 公開日: 2019/4/24
2018年8月28日ベルサール八重洲にて、ファイザーによる「関節リウマチ」プレスセミナーが行われました。テーマは「日本初のJAK阻害剤ゼルヤンツ®の販売開始から5年 日本人3929例の全例市販後調査 中間解析に基づく安全性評価~関節リウマチ治療のパラダイムシフトと今後の展望~」。講演は産業医科大学医学部 第1内科学講座 教授 田中良哉先生と北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室 教授 渥美達也先生です。
関節リウマチ治療の変遷とJAK阻害剤の位置づけ、今後の展望ー田中良哉 先生
関節リウマチに「適切な治療」が必要な理由
関節リウマチ(以下リウマチ)は全身性の自己免疫疾患で膠原病の1つであり、日本における患者数は約70~100万人、男女比は1:4.5で、30~40代と若い世代で好発します。自己反応性Tリンパ球が自己抗体を作り、体内のさまざまな場所で炎症を引き起こしますが、その多くは関節滑膜で起こります。そのため適切な治療をしないと関節の破壊が進み、変形や痛みを感じるようになってしまいます。
一度変形した関節は元に戻ることはなく、リウマチの進行はADLやQOLを著しく低下させるため、早期に適切な治療を開始することが大切なのです。また、炎症は皮膚や肺など関節以外の場所でも起きますが、唾液腺、涙腺が破壊されるとドライアイやドライマウスを引き起こします。
関節リウマチの治療薬
以前は、リウマチがどのような疾患であるかが十分にわかっておらず、疼痛や腫脹の緩和を目的としてステロイドが使用されていました。しかし、ステロイドでは自己免疫疾患であるリウマチの進行を抑えることはできていませんでした。
その後、リウマチが自己免疫疾患であるとわかり、合成抗リウマチ薬やバイオ抗リウマチ薬(生物学的製剤)が使用されるようになり、関節破壊の抑制や症状寛解が可能となり治療が一変します。さらに、細胞内のシグナル伝達を阻害し、炎症を起こさないようにするJAK阻害薬も開発されました。
JAK阻害薬はトファシチニブといい、名前の通りJAKという酵素を阻害し、炎症を起こすシグナルを遮断します。そうすることでリンパ球の活性化を抑制し、1~12週以内に関節破壊抑制など臨床症状を改善する効果があります。合成抗リウマチ薬やバイオ抗リウマチ薬の効果が不十分な症例に使用され、同等またはそれ以上の効果があることがわかっています。2018年3月時点で88か国で承認されており、3年間で6000例の市販後全例調査で、安全性に関する成績を蓄積しています。
また、バイオ抗リウマチ薬は注射薬ですが、JAK阻害薬は内服薬である点も特徴です。
現在の関節リウマチの治療
禁忌でないかぎりリウマチが発症したら、関節が破壊される前にメトトレキサート(抗リウマチ薬)を開始します。6カ月以内に治療目標を達すれば、そのまま治療を継続し、達しなかった場合は、バイオ抗リウマチ薬または、JAK阻害薬の使用開始を検討するという流れになっています。さまざまな治療薬が開発されたことで、関節が破壊されず症状が寛解となる患者さんも増えました。
現在、治験中や申請準備をしているJAK阻害薬もありますし、別のサイトカインを抑える薬剤も発売されています。
リウマチの治療は、関節を壊さない・普通の生活を送ってもらうために、まずは徹底的に治療する、さらに安全に寛解を維持する、その先には薬を中止するという選択も見えてくるかもしれません。
ゼルヤンツ®の特定使用成績調査に基づく安全性評価ー渥美達也 先生
リウマチは、治療をしないままだと痛みと関節の変形で動くことすらままならなくなってしまう疾患です。抗リウマチ薬はリウマチ患者さんにとっては必要不可欠な薬剤ですが、強力な薬剤であり相応の副作用があります。そのため、厚生労働省の指示のもと製薬会社と日本リウマチ学会が協力し合い、全例のデータを集積して安全性を評価することが義務付けられています。2018年7月に作成された「ゼルヤンツ錠5mg 適正使用情報Vol.11」について解説します。
この度の調査では、メトトレキサート(以下MTX)でのコントロール不良な患者さんを調査対象とし、ゼルヤンツを投与したすべての患者さんをゼルヤンツ群(3929例)、ゼルヤンツ以外の対照群(1789例)に分けて比較しました。調査はゼルヤンツの発売と同時に開始され、症例数の総数は6000例、観察期間は3年で、悪性腫瘍発現についても当初から懸念されていたこともあり、投与中止例を含む全ての症例について追跡調査を行いました。
調査デザイン
■対象患者
メトトレキサート(MTX)8mg/週を超える用量を3カ月以上継続して使用してもコントロール不良の関節リウマチ患者
■ゼルヤンツ群:ゼルヤンツを投与した全ての患者
■対照群:ゼルヤンツの投与経験がなく、ゼルヤンツ以外の薬物療法を開始した患者
6ヵ月観察時の副作用発現状況
・副作用で最も多いのは帯状疱疹や肺炎などの感染症で、そのうち帯状疱疹は極端に多い
・ゼルヤンツ群3929例のうち、副作用の発現件数は1455例、うち重篤例は284例
・対照群も同様に、肺炎など免疫力の低下に伴う感染症がみられた
24ヵ月時の有害事象発現状況
・重篤な感染症、帯状疱疹は2~3ヵ月後に最も多く発現する
・間質性肺炎は1ヵ月後に最も多く発現する
・悪性腫瘍の発現率に大きな差はなく、0.94~1.55%で推移
全期間観察後の有害事象における検討
<重篤な感染症について>
・重篤な感染症の発現割合を初回投与量(5㎎または10㎎)、年齢別に分けると60~80歳代のどの年代においても5㎎/日投与に比べて10㎎/日投与のほうが発現率が高く、特に80歳代ではその他の年代の倍以上の発現率となる
・年齢を65歳未満、65歳以上で比較した場合も、5㎎/日投与に比べて10㎎/日投与のほうが重篤な感染症の発現率が高い
・重篤な感染症の発現割合が最も高い条件は「65歳以上・調査開始時点でMTXを使用していない・10㎎/日投与」である
<悪性腫瘍について>
・悪性腫瘍は61例に認められた
・ゼルヤンツの初回投与量と発現時のゼルヤンツ投与量はともに、5㎎/日よりも10㎎/日投与が過半数を超えている
・量の多さにかかわらず、調査開始時にMTXを使用していない人が最も悪性腫瘍の発現率が高い
・今回の調査で最も多い悪性腫瘍はリンパ腫(もともとリウマチ患者さんはリンパ腫になる確率が高い)であったが、そもそも症例数が少ないため、現段階でどのがんが多いということはいえない
<死亡症例について>
・死亡症例は、49例
・死亡の主な原因となった有害事象で最も多いのが感染症、次いで悪性腫瘍であった
以上がゼルヤンツ錠の安全性に関する調査の中間報告です。現時点では、発売前に懸念されていた悪性腫瘍の発現率に関しそれほど大きな影響はないと考えられています。
PMS(製造販売後調査・市販後調査)のためには、これからも適切な患者選択や薬剤の使用、データ収集を行わなくてはなりません。安全性構築のため、ゼルヤンツ錠の調査は続きます。