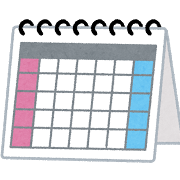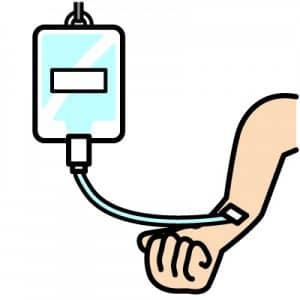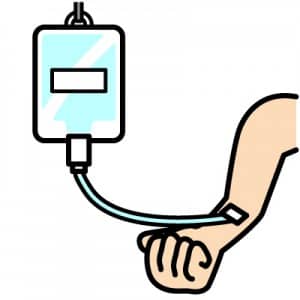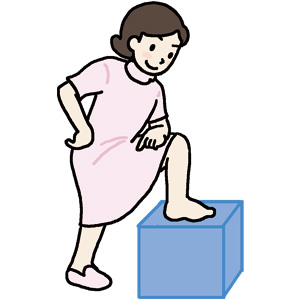 第22回 肥厚、伸びすぎた爪
第22回 肥厚、伸びすぎた爪
- 公開日: 2021/5/3
まだまだ新型コロナ感染が続いており、病院やクリニックの受診も制限があり、十分なケアができない状態が続いていますね。フットケアが必要な患者さんも定期的に受診できなくて、来られたときには大変なことになっていることも少なくありません。
更に、フットケアの技術伝達などの学習や情報を得る機会も減っています。
そこで、今回はセルフケアができなくなって長い時間が経ち、フットケアが難しくなった患者さんがいらっしゃったので症例としてご紹介したいと思います。
患者さんの状態とケア
<患者さん紹介>
80代男性 糖尿病、高血圧、脳血管障害
数年前から左半身に麻痺があり、下腿から足先まで装具を着けてゆっくり少しであれば杖歩行できる。
フットケアに関連する情報は以下のようなものでした。
初診時のフットケア(2020.11月)

装具を着けていない右足

装具を着けるときに、爪が折れたりしていた
ケアの流れ (所要時間20分)
1.観察のため足浴(泡浴)をしながら問診
痛みは感じていない、爪が伸びていることで困っていることはない。
2.観察内容
甲側
・皮膚は乾燥している。爪の周囲は角質がたくさんあり、乾燥して硬くなっている。
・爪は、変色し肥厚(白癬は検査せず)内側に巻いている。爪の中は空洞の部位がある。
足底側
皮膚は乾燥し、肥厚し、汚れている。拇趾、小趾のつけ根に小さい胼胝あり。
かかとは硬くなり、軽度ひび割れあり。出血はない。
3.実際のケア
・爪周囲の余分な角質を除去(ストローゾンデ使用)
・爪の長さを指の長さにできるだけ近くまで切る(ニッパーと爪切り使用)
4.靴下を履くときに引っかからないように先端にやすりをかける。
5、普段と同じように靴下を履いてもらい、歩いてみて痛みや、違和感がないか確認する。
装具もつけて、歩いて違和感がないか確認する。

2回目のフットケア(2020.12月)所要時間20分
ケアの流れ (所要時間20分)
1.観察
・長さは1回目終了時からほぼ変わっていなかった。
・フットケア後、疼痛、歩行など変わったことはなかった。
2.ケアの実際
・足浴(泡浴)⇒ 爪の周囲の角質除去。
・爪を指の長さで整える。 靴下に引っかからないようにやすりをかける。

以後は本人の希望があれば1カ月~2カ月に1回フットケア外来受診か、他の施設でやすりを使用して爪が伸びすぎないよう先端を定期的に削ってケアしてもらうよう説明する。
まとめ
足の皮膚の状態も、白癬、肥厚、巻き爪、胼胝、角質などケアする側からは気になることがいっぱいあって、ケアも継続したいと思うところですが、患者さんの望まれるゴールは爪を切って、靴下をスムーズに履けることでした。
高齢で一人暮らし、身の回りのことが一人でできない状態では、「安全・安楽、患者さんの生活に添ったケア」を提供することが大切だと思います。
もし、やりすぎて傷を作ってしまったり、他のケアが必要になると余分な受診をし、医療費がかかってしまうことになります。ケアについては慎重に、観察をしっかり行い、必要最低限の提供を考えなければなりません。
ケアをどこまで行えばよいか迷ったら、自分のできる範囲で患者さんの困っていることを優先して行っていけばよいと思います。患者さんとゴールを共有しましょう!!