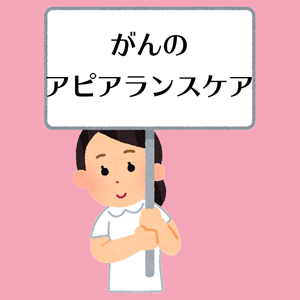どうする? 在宅での乾燥した皮膚、浮腫のある皮膚へのケア【PR】
どうする? 在宅での乾燥した皮膚、浮腫のある皮膚へのケア【PR】
- 公開日: 2023/2/7
在宅療養者は高齢者が多いこともあり、皮膚が乾燥している人も少なくありません。そういった方にどうアプローチすればよいのかを解説します。また、浮腫のある患者さんへのケアのポイントも紹介します。
 全身乾燥時のボディーローションの選び方を教えてください。また、日常でできる保湿の方法とコツがあれば教えてください。
全身乾燥時のボディーローションの選び方を教えてください。また、日常でできる保湿の方法とコツがあれば教えてください。
 在宅療養者ご本人の意識、意向を確認しながら進めましょう。
在宅療養者ご本人の意識、意向を確認しながら進めましょう。
日常的に保湿してもらうための考え方
在宅療養者ご本人が皮膚の乾燥や保湿についてどのくらい意識しているか、何を求めているかなどにより、どう選択するかが決まってくると思います。皮膚の乾燥を自覚しておらず保湿にも無頓着な方の場合、保湿を受け入れてもらうのはなかなか難しいものです。そういった場合はまず皮膚が乾燥しないようにするためのコツとして、熱いお湯での入浴や長湯、1日に何回もシャワーを浴びるといったことを避けていただくようお話しします。
保湿剤の使用感が悪いと結局すぐにやめてしまうことになるので、まずどんなタイプがよいか、どのようにケアしたいかなどをよく聞いたうえで、入手しやすく、使用感がよく使いやすいものをおすすめします。インターネットや特別な小売店でないと入手できないようなものではなく、近くのドラッグストアなどでも買えるものを提案します。試供品があれば使用感を試してもらうのもよいでしょう。万能に使いやすいのはヘパリン類似物質(ヒルドイドなど)のクリームだと思います。可能であれば医師に処方してもらうとよいでしょう。背中は乾燥しやすいのに自分では保湿剤を塗りにくくなかなか難しい問題ですが、広がりやすいローションなら多少はよいかもしれません。孫の手にコットンを巻いて活用している方もいます。
乾燥を自覚していて、かゆみやカサカサが気になっている方には、保湿剤の使用はもちろんのこと、かゆみや傷に対して抗ヒスタミン薬や抗炎症薬などの外用薬を医師に処方してもらい、スキンケアと併用することもあります。
在宅でも多職種との連携は重要です。薬剤師に皮膚の状態や在宅療養者の要望などを相談すると、医師にアドバイスをしてくれることもあります。副腎皮質ステロイド薬にハッカ油を混ぜて清涼感が得られる工夫や、副腎皮質ステロイド薬にヘパリン類似物質を混ぜて使いやすくするなどの提案をしてくれます。日頃から薬剤師とも密にコンタクトを取っておくと、教わることも多々あります。
 乾燥した皮膚に保湿をしてからフィルムドレッシング材を貼る場合、どのような保湿剤を使用するとよいでしょうか。
乾燥した皮膚に保湿をしてからフィルムドレッシング材を貼る場合、どのような保湿剤を使用するとよいでしょうか。
 フィルムドレッシング材を貼ることができる保護膜形成剤などを使うとよいでしょう。
フィルムドレッシング材を貼ることができる保護膜形成剤などを使うとよいでしょう。
一般的な保湿剤ではフィルムドレッシング材は剥がれる
私もいろいろ試しましたが、市販の一般的な保湿剤を塗った上にフィルムドレッシング材を貼っても必ず剥がれてしまいます。一方、皮膚に保護膜をつくる保護膜形成剤は、上からフィルムドレッシング材を貼ることができるとうたっています。製品としては、アルケアのリモイスコート、セキューラのML、ベーテルの保湿ローションや保湿ウォーター、ピュアバリアのモイストジェルなどがあります。褥瘡予防などのため、保湿剤だけではなくフィルムドレッシング材を併用したほうが有効だと判断した場合には、このようなフィルムドレッシング材が貼れる保湿剤を選択する必要があります。
これらは褥瘡やストーマのケアでも使うので、売店で扱っている病院もあるかもしれませんが、身近なところでは入手できないことも少なくありません。そのような場合は、私たちがインターネットでの購入や小売店とのやりとりを代行することもあります。
そもそもフィルムドレッシング材を貼る目的は何かを明確にする必要があると思います。傷があってフィルムドレッシング材を貼る必要があるなら、保湿より被覆に注力するべきですし、保湿で予防できるのであれば、フィルムドレッシング材を貼りっぱなしにするのではなく、機会があるごとに保湿剤をこまめに塗ってケアするほうがよいと思います。
 心不全や低栄養で浮腫がある患者さんのケアを知りたいです。浮腫があり水疱様になり、少しの刺激で破けてしまいそうでどうケアをすればよいのか困っています。
心不全や低栄養で浮腫がある患者さんのケアを知りたいです。浮腫があり水疱様になり、少しの刺激で破けてしまいそうでどうケアをすればよいのか困っています。
 感染徴候に注意しながらケアを行いましょう。
感染徴候に注意しながらケアを行いましょう。
浮腫改善への対策も行う
浮腫とは皮膚や皮下組織に組織間液が過剰に溜まってしまった状態で、皮膚が薄くなり少しの刺激でも傷つきやすくなっています。浮腫に関してはまずその原因や状態をしっかりアセスメントすることが大切です。浮腫がある場合、末梢の循環障害が起こっていますから、酸素供給不足や栄養不足、皮膚温の低下、免疫力の低下などの問題を伴っています。それらをきちんととらえ、担当医とも相談しながら病態的に浮腫が改善するよう対策を講じながら、静脈の血流を促す弾性ストッキングの着用やスキンケアなど局所のケアを合わせて総合的に考えていく必要があります。
浮腫があると皮膚が傷つきやすく、小さい傷でも細菌感染を起こしやすいので、スキンケアにおいては皮膚の清潔・保湿、損傷の予防が重要になってきます。まず爪を短く切る、周囲を整理整頓して身体をぶつけてしまうようなものを片付けるなど、基本的な安全対策を行います。衣類は皮膚がこすれないように柔らかい素材のものにし、露出を少なくします。また血圧測定や採血のため駆血帯を巻くなどの医療的な手技でも皮膚損傷を起こす可能性がありますから、常にそういった意識をもってケアにあたることも大切です。
いつの間にか傷ができてしまったとき
高齢者の皮膚は脆弱で、さらに浮腫があるとスキン-テアを起こしやすく、訪問時に発見するといったことはよく起こります。そのような場合、まず損傷が広がらないように、また感染を起こさないようにする処置が必要です。できれば洗浄剤で、しみるならお湯で洗浄し、剥けた皮膚が残っていたら傷を覆うように戻します。非固着性のガーゼなどで傷を覆い、テープは使わず、ネット包帯などで固定します。滲出液が多い場合(水疱、リンパ瘻)は、皮膚の浸軟を防ぐ目的で撥水性のクリームをつけるとよいでしょう。
このような一時避難的な処置をして経過をみます。在宅療養者やご家族には、傷の発赤や腫れ、熱をもつ、痛みが強くなるなどの感染徴候があったらすぐに連絡するよう伝えておきます。できれば同じ看護師が訪問するように調整して経過をみつつ、必要があれば速やかに受診するようにします。
在宅療養者のご家族は、自分が怪我をさせてしまったのではないかと自責の念にかられ、自信をなくしてしまうことがあるので、原因を追求することよりも、傷の悪化を防ぎ痛みを緩和する方法をアドバイスし、支えることが大切だと思います。
敏感肌にも使えるミノンシリーズ
ミノン全身シャンプー泡タイプ

顔、身体、頭が一本で洗える泡タイプの全身シャンプー。バリア機能を守って洗う「植物性アミノ酸系洗浄成分」配合。弱酸性、無香料。
[医薬部外品]販売名:ミノン全身シャンプーW
500mL、400mL(つめかえ用)
詳しい製品内容についてはこちら → https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/
がん治療の皮膚ケア情報サイト はだカレッジ

薬物療法の皮膚障害の情報を提供するサイト。
患者・家族向けの情報と医療従事者向けの情報を掲載。
医療従事者向けでは、「皮膚に学ぶ・薬に学ぶ・症例から学ぶ」「外来で役立つ・病棟で役立つ・生活で役立つ」の6つテーマに分けた情報が得られます。