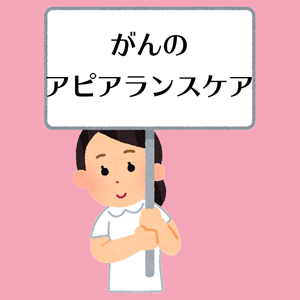困った! 固まって落とせない亜鉛華軟膏【PR】
困った! 固まって落とせない亜鉛華軟膏【PR】
- 公開日: 2023/2/14
在宅でもよく使われる亜鉛華軟膏。固まって取りづらくなってしまった際の対処を解説します。また、糖尿病の患者さんへの在宅でのケアの注意点も紹介します。
 よく落とさずに塗り重ねていたようで亜鉛華軟膏が皮膚の上で石のように固くなってしまっていました。このような場合は、どう洗浄して除去するのがよいでしょうか。
よく落とさずに塗り重ねていたようで亜鉛華軟膏が皮膚の上で石のように固くなってしまっていました。このような場合は、どう洗浄して除去するのがよいでしょうか。
 オリーブオイルなど油性のもので軟化させ取り除きましょう。
オリーブオイルなど油性のもので軟化させ取り除きましょう。
亜鉛華軟膏とは
亜鉛華軟膏は酸化亜鉛を油性基剤と混ぜたものです。皮膚のかぶれやただれ、あせもなどの軽い症状に使われ、患部を保護して炎症を和らげ、滲出液を吸収して乾燥させることで治癒を促す作用があります。長く使っても害が少ないので、在宅ではおむつかぶれなどに使っているケースも多いと思います。
もともと酸化亜鉛は白い粉なので、塗った部分は白くなりますし、皮膚に残った亜鉛華軟膏が固まって落としにくくなることがあります。それを落とそうとしてこすると、その機械的刺激で皮膚に二次損傷を起こしてしまうので注意が必要です。亜鉛華軟膏の基剤は油性ですから水で洗ってもうまく落ちません。ベビーオイルやオリーブオイルなどのオイルを含ませておき、軟らかくしてから拭き取り、その後洗浄するとよいでしょう。
傷の大きさや程度にもよりますが、例えばおむつかぶれなどに亜鉛華軟膏を塗った場合、おむつ交換のたびに全部を落とす必要はないと思います。患部を鎮静化するために亜鉛華軟膏を塗っているのに、1日に何度も落として塗るというのを繰り返して機械的刺激を加えては本末転倒です。1日に1回、陰部洗浄をするときに優しくきれいに取り除いた後、たっぷり亜鉛華軟膏を塗り、その後お通じが出たときは、おむつ交換の際に軟膏の表層部分だけを拭き取り、取り除いた分を上塗りしておくとよいと思います。
 皮膚トラブルを発見したときは薬剤や処置物品が揃っていないこともあり、持っているもので応急処置を行いますが、次回訪問時まで大丈夫かどうか気になります。
皮膚トラブルを発見したときは薬剤や処置物品が揃っていないこともあり、持っているもので応急処置を行いますが、次回訪問時まで大丈夫かどうか気になります。
 次回訪問までの判断は、感染徴候があるかないかで判断しましょう。心配な場合は訪問の間隔を短くすることも考えます。
次回訪問までの判断は、感染徴候があるかないかで判断しましょう。心配な場合は訪問の間隔を短くすることも考えます。
皮膚トラブルへの対応と持っておくとよいもの
表皮剥離やスキン-テアが起きた場合は、感染させないことと二次損傷を起こさないためのケアが必要で、基本は止血、洗浄と、湿潤環境を保つことです。傷はお湯で流すか洗浄剤できれいに洗い、剥がれた皮膚が残っていたら、よれていてもシワになっていてもよいので、元に戻してから保護します。代謝や自然治癒力が低下している高齢者の場合、表皮が剥がれて真皮がむき出しになった部分に新しい皮膚を構築するには時間がかかります。そこで剥がれた皮膚を戻して蓋をすると、それが角化細胞の遊走を助け、傷の治りを促します。患部への刺激を最小限にするため、必ず非固着性のガーゼなどで保護します。普通のガーゼは乾くと貼りつき、それを剥がすときに二次的な損傷を起こしてしまいます。表皮を形成するには、湿潤環境が必要です。湿潤環境を保つように保湿剤や軟膏を使用しますが、軟膏処置は医師の指示がないとできません。基本はワセリンがよいと思います。高齢者は免疫力が低く化膿しやすいため、受診後は外用抗菌薬が処方されたり、痛みや痒みを抑え、傷の治りをよくする非ステロイド系抗炎症薬が処方されることもあります。処置には保湿剤や、包帯などご家庭にあるものも活用しますが、日頃から訪問バッグにいろいろなタイプの保湿剤、非固着性のガーゼやフィルムドレッシング材、肌に優しい包帯やテープ、剥離剤などを入れておくと役に立ちます。保湿剤などの試供品は個包装になっているので便利です。
受診の判断と次回の訪問
現場で受診が必要か否かの判断は訪問看護師がすることになります。スキン-テアなどがあり、出血が続く、滲出液が増える、痛みが強くなる、傷が拡大するといった状況のとき、または縫合を要するような傷などは受診が必要です。訪問診療が入っている方なら、医師に傷の写真を送信して情報共有し、対応を相談します。外来を受診していただく場合は、付きそう人の有無や介護タクシーの必要性などを考慮し、ケアマネジャーとも連絡をとって調整します。そのまま経過をみる場合は、在宅療養者やご家族などに病状を説明し、痛みの増強、発熱などの感染徴候など、変わったことがあったら連絡していただくよう伝えておきます。次回の訪問予定が何日か先で、それより前に観察する必要があると考えられる場合は、ご家族やケアマネジャーと相談し、予定を繰り上げて早く訪問できるように調整します。
 糖尿病の方が多く、皮膚が弱いうえ乾燥しやすく傷になりやすいのでとても気を使います。在宅でのケアの際の注意点を教えてください。
糖尿病の方が多く、皮膚が弱いうえ乾燥しやすく傷になりやすいのでとても気を使います。在宅でのケアの際の注意点を教えてください。
 皮膚を観察することを意識づけましょう
皮膚を観察することを意識づけましょう
糖尿病患者さんへのケアの注意点
糖尿病があると全身に皮膚トラブルを起こしやすく、末梢の循環・神経障害によりしびれや感覚鈍麻が生じていると、小さい傷などに気づかず、感染を起こして潰瘍が広がり、壊疽に至るなど重症化してから見つかることも少なくありません。特に足病変は糖尿病患者さんに起きやすいトラブルで、十分な注意が必要です。在宅療養者には、まず日頃から皮膚をよく観察することの重要性をしっかり意識づけしていくことが大切です。そういう意識が薄いと初期段階の皮膚トラブルを見落としがちです。
予防的ケアとしては皮膚の清潔と観察が重要です。入浴はぬるめのお湯で、刺激の少ない石けんを使い、ゴシゴシ洗わないようにします。また日頃からケガや火傷、日焼けなどをしないよう注意します。冬季に寒い環境にいると末梢循環障害を助長するので、身体が冷えないようにすることも大切です。きつい靴を履き続け、圧迫された足趾に傷ができ潰瘍になってしまった人や、入浴時にかかとのやすり掛けを続けて角質が剥がれてしまい、傷になってしまった人もいます。末梢の感覚が鈍磨していることを在宅療養者やご家族にも認識していただき、靴下を履いてから足に合った靴を履くなどの具体的な指導も大切です。また喫煙も循環障害を悪化させ皮膚にダメージを与えることがあるのでできるだけ控えていただくようお願いします。そして訪問時は全身の皮膚の状態をよく観察します。また歩き方の異変で足病変に気づくこともあります。
そもそも血糖コントロールがうまくいっているかどうかも重要なので、食生活や血糖値の状況を把握し、支援することは基本中の基本だと思います。
敏感肌にも使えるミノンシリーズ
ミノン全身保湿ミルク
ミノン全身保湿クリーム

敏感肌、バリア機能が乱れやすい肌を支える全身に使える「塗るミノン」。広い範囲のケアにはべたつかないミルクタイプ、乾燥のつらい部位にぴたっと密着感のあるクリームタイプ。
[医薬部外品]販売名:DSミルクz・DSクリームz
200mL、400mL(ミルク)、90g(クリーム)
詳しい製品内容についてはこちら → https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon/
がん治療の皮膚ケア情報サイト はだカレッジ

薬物療法の皮膚障害の情報を提供するサイト。
患者・家族向けの情報と医療従事者向けの情報を掲載。
医療従事者向けでは、「皮膚に学ぶ・薬に学ぶ・症例から学ぶ」「外来で役立つ・病棟で役立つ・生活で役立つ」の6つテーマに分けた情報が得られます。