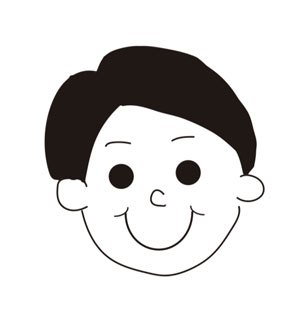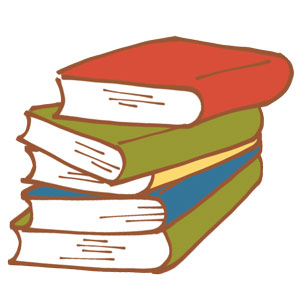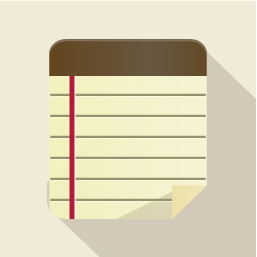多職種で支える! 胆道がん患者さんの意思決定
多職種で支える! 胆道がん患者さんの意思決定
- 公開日: 2025/3/19
胆道がん
安田一朗先生(富山大学学術研究部医学系 内科学第三講座 教授)
胆道とは
胆道とは、胆汁が流れる道のことをいい、胆管・胆嚢・十二指腸乳頭部の3つからなります。
肝臓で生成された胆汁は一時的に胆嚢に蓄えられます。十二指腸乳頭部には、乳頭部を取り囲むように括約筋(オッディ括約筋)が存在しており、食物が十二指腸に入ると、括約筋が緩むと同時に胆嚢が収縮し、胆汁が分泌されます。胆汁の主成分は胆汁酸で、これが脂肪の吸収を助けています。
胆道がんとは
肝臓のなかの胆管に発生する「肝内胆管がん」、肝臓の外の胆管に発生する「胆管がん」、胆嚢に発生する「胆嚢がん」、十二指腸乳頭部に発生する「十二指腸乳頭部がん」、この4つをまとめて「胆道がん」といいます。
胆道がんは高齢者に多いがんです。ほかのがんに比べて罹患数が少ない一方、男女合わせた部位別のがん死亡数は、肺がん、大腸がん、胃がん、膵臓がん、肝臓がんに次いで6番目に多くなっています1)。また、胆道がんの5年生存率は25%ほどで、生存率が低いことで知られる膵がんに次ぐ値です2)。胃がんや大腸がんの5年生存率が大体70%ですので、いかに胆道がんの予後が悪いかがわかるかと思います。
胆道がんの危険因子
胆管がん、胆嚢がん、十二指腸乳頭部がんでそれぞれ危険因子はありますが、明らかになっているのは、胆管がん・胆嚢がんの危険因子である「膵・胆管合流異常」という先天的な奇形です。
通常、膵管と胆管は、十二指腸の出口で合流して1本の管になっています。括約筋の作用により、膵液が胆管に入ったり、胆汁と膵液が混ざったりすることはありませんが、十二指腸より手前で合流してしまうと括約筋の作用が及ばず、膵液が胆管に入ったり、胆汁と膵液が混ざったりして胆道の粘膜に炎症が起こり、がんの発生につながるリスクがあると考えられています。
膵・胆管合流異常以外の危険因子はほとんどわかっておらず、ハイリスクの患者さんを見つけにくいところも、胆道がんの早期発見を難しくしています。
胆道がんの症状
胆道がんのなかで最もよくみられる症状として、黄疸が挙げられます。これは、胆道にできた腫瘍によって胆汁の流れがせき止められ、胆汁が肝臓から血液のほうに逆流するためです。ほかに、一般的ながん症状として、体重減少や腹痛などがみられることもあります。
胆道がんの検査・診断
胆道がんを早期に発見するために、血液検査と腹部超音波検査によるスクリーニング検査を行います。
血液検査では肝・胆道系酵素(AST、ALT、ALP、γGTP、T-Bilなど)の上昇がみられることがあります。腫瘍マーカーも1つの目安になりますが、ほかのがんと同じく、進行した段階でしか数値が上がってこないため、早期の発見は難しいのが現状です。
腹部超音波検査も、胆道がんの発見にある程度の役割を果たしてくれます。特に胆嚢はエコーでも見やすく、胆嚢にポリープが見つかり、よく調べるとがんだったというケースが稀にあります。とはいえ、人間ドッグや健康診断で見つかる胆嚢ポリープはコレステロールポリープであることが多く、そのままにしておいても問題ないケースがほとんどです。
スクリーニング検査などで胆道がんが疑われた場合は、CT検査やMRI検査を行います。CT検査では必ず造影剤を使用します。CT検査は画像が理解しやすく、あらゆる断面で画像が作成できる一方、造影剤アレルギーが起こるリスクや放射線被曝の問題、小さな病変はわかりづらいという課題があります。
MRI検査は被曝の心配がなく、胆管の全体像を詳細に把握することができますが、検査に時間がかかります。体内に金属が入っている患者さんや入れ墨をしている患者さん、閉所恐怖症の患者さんでは実施できず、CT検査と同様に、小さな病変の診断が難しいところも短所として挙げられます。
現在ある画像検査のなかで最も精度が高いのは、超音波内視鏡検査(EUC)です。内視鏡の先端に超音波装置が備わったもので、体外から超音波を当てるよりもはるかに小さな病変まで指摘することができます。
ただ、胆道がんと診断されて手術をしたら、がんではなかったと判明するケースも少なくなく、画像だけで診断するのは難しいといえます。
胆道がんの治療
胆道がんの治療は、比較的早い段階であれば手術を行います。がんの発生部位に応じて、肝臓や胆嚢、膵臓、十二指腸、胆管などを切除します。手術ができない場合は、抗がん剤や放射線による治療を実施します。
また、「プレシジョンメディシン」という、新たに登場した概念があります。がん細胞の遺伝子を解析し、がんの原因となった遺伝子変異を見つけ、その遺伝子変異に効果があるように設計された薬剤(分子標的薬)を使用するといった手法です。胆道がんにみられる遺伝子変異の頻度はそこまで高くないものの、遺伝子変異が見つかればそれに対応した薬剤が使えるように、少しずつですがなってきています。
Shared Decision Making(SDM)とは何か?~EBMの原点からその先~
中山健夫先生(京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野)
エビデンスに基づく医療とは
エビデンスに基づく医療「Evidence-based Medicine(EBM)」は、1991年にカナダの研究者によって発表された論文から生まれました。EBMというと、「臨床家の勘や経験ではなく、科学的な根拠(エビデンス)を重視して行う医療」と説明されることが多いのですが、EBMのパイオニアたちはこのようなことは言っておらず、EBMとは4つの要素の統合であるとしています。
1つ目は「最良の研究によるエビデンス」。私なりに言葉を補うと、エビデンスとは人間集団から疫学的手法で得られた一般論です。2つ目は「臨床的熟練」。これは、貴重な個々の経験の積み重ねに基づく熟練・技能・直感的判断力のことをいいます。そして3つ目は「患者それぞれの価値観」で、患者さんの希望や意向、価値観を指します。
この3つが初めに言われていましたが、EBMの考えが深まって加わったのが、4つ目の要素となる「状況」です。状況には2つの意味があり、1つは患者さんの個別性・多様性で、同じ疾患でも同じ患者さんは2人として存在しないということです。もう1つは医療を行う場です。同じ疾患の同じ患者さんでも、どこで医療を受けるかによってベストが異なるということです。
これらの異なる次元の4点を統合し、患者さんにとって、よりプラスになる意思決定や治療をしていこうというのが、EBMの本来の考え方なのです。
SDMとは
先ほど、EBMは誤解された状態で広まった過去があるとお話ししましたが、このことに心を痛めたパイオニアたちはEBMについて、個々の患者さんのケアに関する意思決定過程に「現在得られる最良の根拠」を「良心的」「明示的」かつ「思慮深く」用いることが大切であると説明した論文を発表しています。
そして、そこにはShared Decision Making(SDM)がなければいけません。SDMとは、協力してヘルスケアの選択を行うため、患者さんと医療者の間で交わす対話を意味します。特に私が強調しているのは、情報・目標・責任の共有を進めることであり、これらの共有を進める基本がコミュニケーションですが、わかっている人間がわかっていない相手に一方的に話すことはコミュニケーションとはいえません。
ICとSDMの違い
SDMと似ていると感じられるものにインフォームドコンセント(IC)がありますが、医療者が専門知識と経験からよいとされる答えを知っていて、「医療者が示す選択肢」への着地が期待されるのがICです。
一方、患者さんも医師もどこに着地するかわからない、エビデンスの確実性が高くない場合に出番となるのがSDMです。双方向のコミュニケーションを通して、目指す目標とそこに近づく方法が共有されていくイメージで、困難な意思決定と合意形成を同時に行うコミュニケーションといえます。
胆道がんにおけるSDMの実態
胆道がん患者さんのSDMについて、アストラゼネカが調査を実施しています。調査対象者は、5年以内に胆道がんと診断されたことのある患者さん、または再発した患者さんで、回答者数は74名です。
胆道がんと診断されてから最初の治療を決めるまで、がんのできた場所や広がり、治療について、半数以上の患者さんが医師から説明を受けたと回答しています。ただ一方で、起こりうる合併症や今後の見通しについて説明を受けたと回答した患者さんは、それぞれ26%と16%でかなり低い結果となりました。これは、医師のほうは説明したと認識しているかもしれませんが、基本的には説明しにくい話ですから、なかなか明確に伝わらない可能性があることが考えられます。そして、患者さんのほうも、どうしても期待が込められた情報、ポジティブな情報を取りますから、ネガティブな情報は耳に入りにくいのかもしれません。
ほかに、意思決定の際、およそ6割の患者さんが主治医以外と話をしておらず、他の医療者の関与はありませんでした。医師が把握できる患者さんの情報は限られており、患者さんによって伝える情報も変えているため、多職種で情報と意識を共有することが欠かせません。医師の力だけでなく、部門や職種を越えて患者さんのために連携することで、初めてSDMは機能します。やる気があり、力もある看護師や薬剤師の方がたくさんいますので、ぜひ相談してみてほしいと思います。
引用文献
2)がん研究振興財団:がんの統計.p.26.(2025年3月6日閲覧) https://ganjoho.jp/public/qa_links/report/statistics/pdf/cancer_statistics_2024_fig_J.pdf