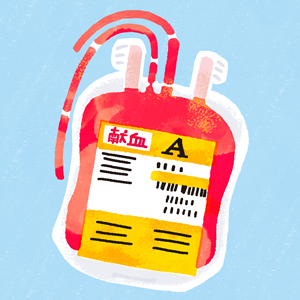 輸血マニュアルはどう作ればいい?|トラブルシューティング
輸血マニュアルはどう作ればいい?|トラブルシューティング
- 公開日: 2025/4/1
安全な輸血を実施するためには、輸血の副反応の予防や輸血過誤の防止が欠かせません。日々の輸血業務の疑問や困ったときに必要になるのが輸血マニュアルです。また、安全で適正な輸血療法の実施を目指すためにも輸血マニュアルが必要です。私たち看護師は輸血業務を患者さんの一番近くで行っています。輸血マニュアルを作成することによって、全ての職員が効率よく安心して業務を行うことができるようになります。施設の輸血マニュアルを確認してみましょう。
ここでは輸血マニュアルの作り方と必要な項目について述べます。
院内に輸血マニュアルがある場合
院内の輸血マニュアルは、院内で働くすべての職種・部門での話し合いをもとに作られているものです。院内に輸血マニュアルがある場合は、それを用いて輸血を実施します。輸血マニュアルの中で、特に輸血実施手順に関連した部分は、患者さんの一番近くで輸血業務を行う看護師こそが安全に行えるようなマニュアルであることが大切です。日々の輸血業務の中で疑問や困ったことがあったときは、適宜マニュアルの見直し、追加、定期的な改訂も必要です。
院内に輸血マニュアルがない場合
院内に輸血マニュアルがない場合、まずは病院・クリニックに掛け合い、きちんとした輸血マニュアルを作ることから始めます。輸血療法は医師、検査部門、輸血部部門、看護師等がかかわる重要な業務です。輸血は臓器移植であり、患者さんにとって効果は大きいですが、患者間違いや血液型間違い、不適切な取り扱い、副反応に対する対応の遅れなどで重篤な状況に陥ります。そのため血液製剤は充分な確認のもと、取り扱う必要があります。患者さんの一番近くで血液製剤を取り扱う看護師が、安全に輸血業務を行えるマニュアルであることが大切です。
「輸血療法の実施に関する指針」平成17年9月(令和2年3月一部改正)をもとに輸血マニュアルを作っていくことをお勧めします。以下に輸血実施手順書に沿って、実践の場でマニュアルに入れたほうがよいと考えるポイントを述べます。
1.輸血同意書の取得
一連の輸血を行うごとに必ず輸血同意書を得ることが必要です。看護師は輸血実施前に輸血同意書が得られており、サインがあることの確認が必要です。輸血に伴う患者さんに対する説明については平成24年保医発0305-1の中で一連の輸血を行うごとに実施すると示されていますが、具体的に同意書を取った日から何日間を有効とするのかは、院内での取り決めがあるとよいでしょう。
2.輸血検査
輸血を実施するまでに患者さんの血液型検査と不規則抗体検査を行います。赤血球輸血の場合には交差適合試験(クロスマッチ)も必要です。 看護師は輸血実施前にカルテの血液型、必要な輸血前検査が施行されていることを確認します。
【関連記事】
輸血検査|血液型検査、不規則抗体検査(スクリーニング検査)、交差適合検査(クロスマッチ)
3.輸血指示の確認
看護師は輸血申し込み伝票と処置指示書を確認します。
4.血液バッグの確認(1患者さんごとに実施)
①血液バッグと交差適合試験適合票、カルテの3つで血液型を照合します。さらに血液バッグと交差適合試験適合票の患者姓名、製造番号が一致し有効期間内であることを確認します。
②放射線照射が医師の指示通り行われているか確認します。
③血液バッグの外観をチェックします(破損、変色、溶血、凝集塊等の異常の有無)。
→この3つの事項を医療従事者2人で声を出して照合し、所定欄にサインをします。
5.患者さんの確認
①患者さん自身から姓名と血液型を言ってもらいます。患者さんの意識がない場合は、ベッドサイドでカルテを用いて医療従事者2人で患者さんの確認を行います。
②患者さんのリストバンドの姓名と血液型が、血液バッグの血液型および交差適合試験適合票の姓名、血液型と一致していることを確認します。携帯端末が利用できる場合には、患者さんのリストバンドと製剤のバーコードをスキャンし実施入力を行います。
血液製剤ごとに使用する輸血ルートに関してもマニュアルに明記するとよいです。
6.交差適合試験適合票にサイン
患者さんと血液バッグの照合後、ベッドサイドで交差適合試験適合票のサイン欄にサインして輸血を開始します。
7.輸血患者さんの観察
輸血前のバイタルを確認、記録します。輸血開始後5分間は患者さんのベッドサイドを離れず状態を観察します。15分後と終了時(15分後~終了時までは適宜)にも観察し、輸血副作用の有無、内容を記録します。重篤な副反応は輸血開始早期に生じるので十分な注意が必要です。観察項目は血圧、脈拍、体温、SpO2です。
8.使用血液の記録
カルテに血液バッグの製造番号(貼付ラベル)を記録します。
輸血マニュアルに必要な項目に関して
看護師は実際に患者さんに輸血するという業務のみではなく、輸血関連検査のための採血、血液の搬送、保管、FFPの融解、患者さんの状態の観察等も担います。そのため、血液製剤ごとの保管方法、期限、FFP融解方法、血液の搬送時の注意事項等もマニュアル内にあるとよいでしょう。 その他マニュアルにあったほうがよい項目を挙げます。
・産科危機的出血への対応指針20222017
https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/shusanki_taioushishin2022.pdf
・危機的出血のガイドライン
https://anesth.or.jp/files/pdf/kikitekiGL2.pdf
・生物由来製品感染等被害救済制度
https://www.pmda.go.jp/relief-services/infections/0001.html
・緊急災害時の輸血業務体制
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5817&dataType=1&pageNo=1
・自己血輸血|メリット・デメリット、適応・禁忌、手順など
https://knowledge.nurse-senka.jp/500912
日勤帯で行う輸血時には、標準のマニュアル通りで困ることはないかもしれません。しかし、緊急輸血時や大量輸血時の対応、異型適合血輸血、夜間・休日等時間外の払い出しから輸血実施までのマニュアルも必要です。病院によって時間外の輸血前検査から払い出しの体制は異なりますので、確認しておくことが大切です。必要であれば、フローチャート等にて整備することをお勧めします。
その他、輸血副反応症状が出現したときの対応に関してもマニュアルに記載することが必要です。アナフィラキシーや、発見時には軽症であっても急激に重症化する副反応もあるので、看護師の初期対応が重要です。また、万が一、ABO不適合輸血が起きてしまった場合の対応についてもマニュアルに示し、日頃から目に届くところに掲示もしくは携帯すると良いでしょう。安全な輸血業務のために、日頃からの備えが大切です。
最後に
輸血マニュアルは、いつだれが見ても安全に輸血業務を行えるマニュアルであるべきです。病院全体で話し合い、あらゆる場面を想定したものが必要です。緊急・大量輸血、ABO不適合輸血や輸血副反応などに備え、安全な輸血業務を行えるマニュアルを作ってください。
参考文献
●日本輸血・細胞治療学会日本赤十字社:輸血療法マニュアル 改訂7版.2018.
●厚生労働省:輸血の実施に関する指針.平成17年9月(令和2年3月一部改正).(2025年2月12日閲覧)http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/073bdbb3a84b80b0c05e0b53f57cb409.pdf.
●厚生労働省:血液製剤の使用指針.平成31年3月.(2025年2月12日閲覧)http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/4753ef28a62e4485cb6b44f92ebad741.pdf.
カテゴリの新着記事

病棟でも外来でも扱う輸血製剤、それぞれの特徴とは?
今回の問題看護師国家試験第112回-午前-一般41 輸血用血液製剤と保存温度の組合せで正しいのはどれか。 1.血小板成分製剤 ── 2〜6℃ 2.赤血球成分製剤 ── 2〜6℃ 3.血漿成分製剤 ── 20〜24℃ 4.全血製剤 ── 20〜24℃
-
-
- 透析時の輸血の手順と注意点を知りたい!|トラブルシューティング
-
-
-
- 血管確保が困難な患者さん! どうしたらいい?|トラブルシューティング
-
-
-
- 輸血中に急変した!どうする?|トラブルシューティング
-
-
-
- 輸血が時間通りに終わらない!|トラブルシューティング
-






