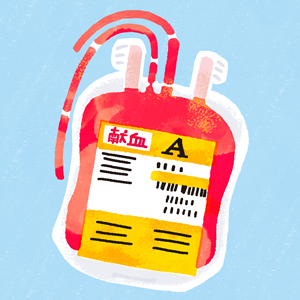 透析時の輸血の手順と注意点を知りたい!|トラブルシューティング
透析時の輸血の手順と注意点を知りたい!|トラブルシューティング
- 公開日: 2025/6/4
血液透析中の輸血療法は、実際にはエビデンスや指針、マニュアルがなく、各施設でいろいろなルールを決めて施行しているのが現状です。しかしながら、透析に伴う血液循環動態の変動などのリスクもある中での輸血療法は、通常の輸血副反応に加えて、体液量の過剰、高カリウム血症にも注意が必要となります。今回は、慢性腎不全の維持透析患者さんに対する輸血の手順、注意点について述べます。重要ポイントは、容量負荷と高カリウム血症対策です。
①輸血の準備:赤血球液の場合、できるだけ有効期限の長い(新しい)血液を使用します。これは、血液の保存・放射線照射により、血液バッグ内のカリウム濃度が経時的に上昇しているためです(表)。
透析患者さんは尿中にカリウムが排泄されないため、高カリウム血症の状態にあります。更なる高カリウム血症が生じないよう注意が必要です。
表 上清カリウム濃度の増加について

②患者さんへの治療:エリスロポエチン製剤やHIF-PH阻害薬の導入、鉄剤治療等を優先して、赤血球液の輸血を回避する努力をします。
③輸血のトリガー値:「血液製剤の使用指針」では、原則として、Hb値≧7g/dLでは輸血は行わず、輸血する場合は必要最小限の輸血とすることを推奨しています。
④輸血の実際:透析時の輸血は、通常の輸血手順に準じて実施します。プライミングでは、通常の輸血セットを使用します。透析膜の前後、どこから接続して輸血を実施するかに関する明確な指針はありません。
〈参考〉
青森県では、県内の維持透析実施35施設でアンケート調査を行いました。その回答では、90%以上の施設では「赤血球液は透析膜の上流から」施行されていました。多くの施設で、血小板輸血は透析中に施行していませんでした。また、輸血量に応じた除水量を設定している施設が多くみられました。
⑤副反応について:透析時の輸血副反応のチェックも、通常と同様に行います。体液量の変動が大きいので、血圧や脈拍の変化、SpO2の変化等には特に注意が必要です。発熱もしばしば認められるので、輸血中にはアレルギーの有無や感染症の可能性を念頭に置き、注意深く観察してください。
参考文献
●日本赤十字社:輸血用血液製剤取り扱いマニュアル2023年5月改訂版,p.10(2025年4月25日閲覧)https://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/handlingmanual2304.pdf
●白戸研一,他:O-14 血液透析患者における輸血療法の実態~青森県合同輸血療法委員会アンケート調査より~.日本輸血細胞治療学会誌 2019;65(2):325.







