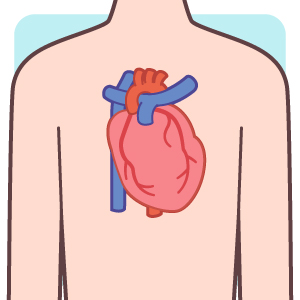 心臓カテーテル検査の前にフロセミドの内服を控えるのはなぜ?
心臓カテーテル検査の前にフロセミドの内服を控えるのはなぜ?
- 公開日: 2025/11/26
フロセミドとは
フロセミドは、ループ利尿薬に分類される強力な利尿薬です。服用後に短時間で大量の尿を排出させるため、体内の水分量が急激に減少する可能性があります。特に高齢者、慢性心不全患者さん、腎機能が低下している患者さんは、もともと体液バランスが不安定であることから、利尿による脱水の影響が現れやすくなります。
造影剤腎症のリスクの回避
心臓カテーテル検査の前にフロセミドの内服を控える最大の理由は、造影剤腎症(CIN)のリスクを回避するためです。
心臓カテーテル検査ではヨード造影剤を使用するため、腎臓に一時的に負担がかかります。体液が不足した状態で造影剤が使用されると腎血流が低下し、造影剤腎症のリスクが高まると考えられているため、検査前はフロセミドの内服を控え、検査後に内服するよう指示されることがあります。
腎機能が低下している患者さんに対しては、検査前日から点滴による補液を行い、腎臓への影響を最小限に抑えるといった対応が取られることもあります。実際に、日本腎臓学会などが策定した『腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン2018』では、「CINのリスクが高いCKD患者ではCINを予防するため、生理食塩液を造影検査の前後に経静脈投与をすることを推奨する」とあり1)、造影剤腎症の予防として、「検査前後の十分な水分補給(ハイドレーション)」が勧められています。このような方針のもとでは、利尿作用のある薬剤の使用を一時的に控えるのが一般的です。
検査中の排尿トラブルの回避
フロセミドには、服用から比較的短時間(30分〜1時間程度)で尿意を催すという特徴があります。そのため、検査前に服用すると、検査中に強い尿意を感じることがあり、患者さんの不快感やストレスにつながります。
鼠径部(大腿動脈)からのアプローチであれば、あらかじめ尿道カテーテルを挿入することが多いため、排尿をある程度コントロールすることが可能です。しかし、手首(橈骨動脈)や肘(上腕動脈)など上肢アプローチの場合は、尿道カテーテルを使用しないケースも多く、排尿が困難になることで、検査の中断や不測の対応が必要になるリスクがあります。
電解質異常、血圧低下への懸念
フロセミドは、ナトリウム(Na)やカリウム(K)といった電解質を尿中に排出する作用があるため、使用後に低カリウム血症などの電解質異常を来すことがあります。これにより、不整脈のリスクが増加する可能性も否定できません。
また、心機能が低下している患者さんでは、利尿による循環血液量の減少で血圧低下を招きやすく、さらにカテーテル操作などで血行動態が不安定になると、循環が破綻し、ショック状態に至る可能性があります。
心臓カテーテル検査では、血圧や脈拍などのモニタリングが継続的に行われますが、予測可能なリスクはあらかじめ回避することが望ましいと考えます。




