【連載】脳神経外科看護のQ&A! 皆さんの疑問にお答えします!
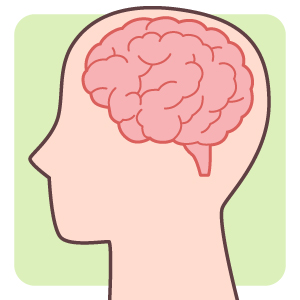 失語症の患者さんとのコミュニケーションで工夫できること、心がけるべきことが知りたい!
失語症の患者さんとのコミュニケーションで工夫できること、心がけるべきことが知りたい!
- 公開日: 2025/11/23
コミュニケーションで大切にしたい姿勢と心がけ
脳神経外科では、失語症を呈する患者さんが少なくありません。患者さんと接する時間が長い看護師はコミュニケーションの難しさに悩むことも多いですが、失語症に限らず、患者さんと良好な関係を築き、相互理解を深めるには、時間がかかること、時間をかけるものであることをまずは認識しましょう。
特に失語症の患者さんは、言いたいことをうまく言葉にできない、思うように伝えることができないことから、人とのかかわりを避けてしまいがちです。しかし、他者に話す、他者の話を聞くというコミュニケーションは、リハビリテーションの1つとしても重要です。
看護師自身も患者さんとの対話を避けてしまうことがないように、患者さんの訴えたいことや気持ちを汲み取りたい、理解したいという姿勢を大切にし、根気強くかかわることを心がけます。
コミュニケーションの工夫ポイント
情報収集
患者さんの情報(出身地、家族構成、趣味など)をあらかじめ収集しておきます。患者さんにとって興味がある話題を提供することができれば、話そうと思ってもらえる可能性が高くなり、コミュニケーションがとりやすくなります。会話を楽しむことはリハビリテーションにもつながるため、コミュニケーションを図る前に、必要な準備をしておくことは大切です。
環境設定
テレビは消すなど、なるべく静かな環境を整えます。注意障害を伴う場合は、周囲に物が少ない状態にし、対話に集中できるようにします。
聞き方・話し方の工夫
患者さんと対話するときは、患者さんの反応を待ち、焦らせないようにします。目線を合わせ、自身の表情にも配慮し、ちゃんと話を聞いていることを示すようにしましょう。
話すときは、ゆっくりとわかりやすい言葉で話すことを心がけます。文章を短く区切って話すようにすると、患者さんに伝わりやすくなります。患者さんが理解できない言葉がある場合は、「体調はいかがですか⇒身体の具合はいかがですか」「生年月日を教えてください⇒誕生日を教えてください」などのように、ほかの言葉で言い換えると伝わることがあります。
また、突然話題を変えると患者さんが混乱するため、「話は変わりますが」「ここから別の話です」といったように、話が変わることを伝えてから違う話題に移るようにします。
非言語的コミュニケーションの活用
言葉で理解するのが難しい場合や患者さんが言葉に詰まってしまったときなどは、ジェスチャー、書字、絵カード、写真、実物などを用いる非言語的コミュニケーションを活用します。例えば、キーワードを書いた紙を見せながら会話したり、質問に対してカードで答えてもらったりすると、コミュニケーションがとりやすくなります。
失語症のタイプに合わせたコミュニケーションの実施
失語症は、運動性失語(ブローカ失語)と感覚性失語(ウェルニッケ失語)に大きく分けられます。脳の障害部位の違いから症状が異なり、それぞれに適したコミュニケーションの方法があるため、患者さんの病態を把握したうえで、適切な方法を検討しましょう(表)。
表 失語症のタイプに合わせたコミュニケーションの方法
| 失語症のタイプ | 脳の障害部位と症状 | コミュニケーションの方法 |
|---|---|---|
| 運動性失語(ブローカ失語) | ●運動性言語野(ブローカ領域)に障害がある場合に生じる ●言葉を聞いて理解できるが、うまく話すことができない ●単語や定型的な表現など、短い言葉であれば話すことができる | ●クローズドクエスチョン(はい・いいえ、首の動きなどで答えられる質問)で質問する ●選択肢を提示する ●スケールを使用し、指で示してもらう |
| 感覚性失語(ウェルニッケ失語) | ●感覚性言語野(ウェルニッケ領域)に障害がある場合に生じる ●相手の話をうまく理解することができない ●流暢に話すことができるが、意図した言葉とは異なる言葉が出てくる(錯語)ため、相手に伝わりにくい ●復唱ができない | ●注意を向けてもらう ●非言語的なコミュニケーションを用いる |
参考文献
●森田秋子,他:フレッシュSTのギモンを解決! 失語リハビリQ&A.医歯薬出版,2022.●森田秋子,他:臨床力up! 動画と音声で学ぶ 失語症の症状とアプローチ.三輪書店,2017.





