【連載】脳神経外科看護のQ&A! 皆さんの疑問にお答えします!
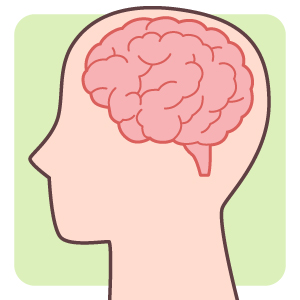 脳血管攣縮(スパズム)の対応ポイントが知りたい!
脳血管攣縮(スパズム)の対応ポイントが知りたい!
- 公開日: 2025/10/23
脳血管攣縮とは
脳血管攣縮は、くも膜下出血後によくみられる合併症です。スパズムとも呼ばれ、脳の血管が可逆的に狭くなります。進行すると脳梗塞を引き起こして、麻痺や失語、意識障害を来すことがあり、患者さんの予後に大きく影響します。
脳血管攣縮は予防が非常に重要で、症状を起こす前から各種の治療が行われます。症状を来さない無症候性の血管攣縮もありますが、予防的な治療を行っていても一定の確率で症状が起こることがあり、そのときは適切に対応しなければなりません。
症状を来したときには、迅速に対応することで回復が期待できる場合もあり、脳血管攣縮後の対応が患者さんの予後の分岐点となるといっても過言ではありません。
脳血管攣縮の治療
脳血管攣縮の予防として、クラゾセンタンナトリウム(ピヴラッツⓇ)や塩酸ファスジル(エリルⓇ)の静脈内投与が行われます。
一方で、脳血管攣縮を来してしまった場合の治療は、症候性か無症候性か、あるいは重症度によっても異なります。当院の場合、中等度や重度、もしくは症候性の脳血管攣縮に対しては、マイクロカテーテルを用いた塩酸ファスジルの選択的動注療法を行ったり、バルーンによる経皮的血管形成術を実施したりします。ただし、塩酸ファスジルによる血管拡張効果は一時的であるため、連日施行される場合もあります。
脳血管攣縮の観察と対応のポイント
脳血管攣縮の発現は、くも膜下出血発症5~14日後とされ1)、特に7~10日がピークとなる傾向があります。この時期に注意深く、慎重な観察を行うことで、脳血管攣縮を早期に発見できる可能性が高まり、迅速な対応につなげることができます。
くも膜下出血後の病態は複雑で、くも膜下出血そのものによる影響、麻酔の影響、電解質異常、脳浮腫、水頭症など、神経症状に影響を及ぼすものが多くあります。脳血管攣縮の症状は血流が減少した部位によって異なりますが、くも膜下出血発症からの時期、意識レベルの変化、神経症状の悪化に注意して観察します(表)。
患者さんが自身の症状を訴えることが難しい場合もあるため、例えば、術後3~4日目には会話ができていた患者さんが6~7日目頃から反応が鈍くなり、傾眠がちになる、ぼーっとしている、呂律が回っていないなど、ベッドサイドにいる看護師が些細な変化をキャッチすることが大切です。
脳血管攣縮が疑われる症状がみられたら、判断に迷う場合であったとしても、直ちに医師に報告します。MRIや脳血管撮影検査で、脳梗塞や血管攣縮の部位、重症度などを評価し、状態に合わせた治療が行われるため、看護師としては、検査・治療がスムーズに進められるよう迅速に準備します。
表 脳血管攣縮の主な観察ポイント
| 主な観察ポイント | |
|---|---|
| くも膜下出血発症からの時期 | くも膜下出血発症5~14日(特に7~10日)である |
| 意識レベルの変化 | 傾眠傾向になる、呼びかけへの反応が悪くなる、刺激に対する反応が鈍くなる、ぼーっとするなど |
| 神経症状の悪化 | ●運動麻痺:片側の手足に力が入らない、動かせない、動きがぎこちなくなるなど ●感覚障害:しびれ、感覚の鈍さなど ●言語障害:言葉が出てこない(失語)、呂律が回らない(構音障害)など |
引用・参考文献
1)A G Harders,et al:Time course of blood velocity changes related to vasospasm in the circle of Willis measured by transcranial Doppler ultrasound.J Neurosurg 1987;66(5):718-28.●Vergouwen MD,et al:Definition of delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage as an outcome event in clinical trials and observational studies: proposal of a multidisciplinary research group.Stroke 2010;41(10):2391-5.
●Tokareva B,et al:Early and recurrent cerebral vasospasms after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: The impact of age.Eur Stroke J. 2024;9(1):172-9.





