【連載】脳神経外科看護のQ&A! 皆さんの疑問にお答えします!
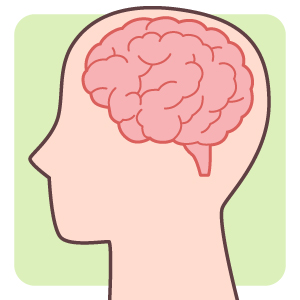 脳腫瘍で人格・性格の変化がみられるのはなぜ? どう対応する?
脳腫瘍で人格・性格の変化がみられるのはなぜ? どう対応する?
- 公開日: 2025/10/27
脳腫瘍で人格・性格の変化がみられる理由
脳腫瘍の患者さんでは、腫瘍の影響や薬剤の副作用などさまざまな要因によって、人格・性格が変化したと捉えられるような言動や感情の変化が現われることがあります。
腫瘍の影響
脳腫瘍は、脳実質内腫瘍(大脳、小脳、脳幹といった脳実質から発生する腫瘍)と脳実質外腫瘍(髄膜、下垂体、脳神経などから発生する腫瘍)とに大別されます。
脳実質内腫瘍では、腫瘍の浸潤により、脳機能に直接的な影響が生じる可能性があり、脳実質外腫瘍では腫瘍が脳を圧迫し、脳機能に影響が及ぶことが考えられます。また、両者ともに、浸潤や圧迫により周囲の脳が浮腫を起こし、脳機能が一時的あるいは持続的に低下することもあります。
障害される部位によって影響は異なりますが、思考、判断、感情などを司り、人格形成や社会性に深く関与している前頭葉に腫瘍ができると、人格・性格の変化とみられる病態が顕著に現れます。ほかに、側頭葉の腫瘍では感情や記憶に影響が出たり、頭頂葉の腫瘍では、認知や判断などの高次脳機能への影響がみられたりします。
薬剤の影響
ステロイドや抗てんかん薬などの薬剤によっては、不眠、易刺激性、多幸感といった精神的な副作用が生じ、言動や感情の変化が現れることがあります。
環境因子
入院、手術、集中治療室など普段と異なる環境下、術後の疼痛や心理的ストレスなどが影響し、せん妄が生じることがあります。せん妄では、意識障害、見当識障害、思考の混乱、妄想、注意力欠如、錯覚、幻覚などから、言動や感情の変化がみられますが、一時的なもので通常は回復します。
精神的要因
病状や治療による身体的な疲労、痛みや不安による睡眠障害、不安・恐怖・抑うつといった精神的な症状から、怒りやすくなる、感情の起伏が激しくなるなどの変化が現れることがあります。
患者さんへのケア
看護師としては、人格・性格の変化が起こったと考えるのではなく、一種の病態であり、症状の1つとして捉えることが大切です。医師や他のスタッフとも相談し、患者さんの変化が脳腫瘍の影響によるものなのか、治療や環境などによる一時的なものなのかを検討したうえでケアを行います。
環境因子や精神的要因の場合は、可能な限りその要因を取り除くように努めます。環境因子の影響が考えられるようであれば、ケア提供者の統一、空調や照明の調整、見当識を維持するためのカレンダーや時計の配置などを行い、患者さんが安心して快適に過ごせる環境を整えます。
精神的要因の可能性が高い場合は、患者さんの不安を受け止め、精神的な負担を軽減できるようなかかわりを心がけ、痛みによる不安や抑うつがみられる患者さんには、適切な疼痛管理が行われるように医師と調整します。薬剤の影響については、投与前にどのような副作用が生じる可能性があるか、患者さんに説明しておきましょう。
ほかに、患者さんの普段の人柄や性格を家族から聴取し、脳腫瘍になる前の患者像を把握しておくことも大切です。
家族への対応
医師とも病態についてよく相談し、一時的なもので以前の状態に戻ると考えられるのか、それとも症状が持続してしまう可能性が高いのか、リハビリテーションが必要になる可能性があるのかなど、現時点での今後の見通しについて考えを共有しましょう。家族には、患者さんの変化の要因と推察されることを説明し、本人の人格や性格が変化しているのではなく、症状の1つであることを理解してもらえるようにします。
ただし、病態や治療などが原因だとわかったとしても、家族には大きな精神的負担がかかります。家族の不安を受け止めて、精神的な支援を行うことも必要です。
参考文献
●van Loon EM,et al:Assessment methods and prevalence of cognitive dysfunction in patients with low-grade glioma: A systematic review.J Rehabil Med 2015;47(6):481-8.●Jenkins LM,et al:Emotional and personality changes following brain tumour resection.J Clin Neurosci 2016;29:128-32.
●Barrash J,et al:Acquired Personality Disturbances After Meningioma Resection Are Strongly Associated With Impaired Quality of Life.Neurosurgery 2020;87(2):276-84.






