記事一覧
15件/4077件

看護職だからこそ!体内リズムの改善で生活の「質」を高めよう【PR】
◆睡眠の「質」が生活の「質」及ぼす影響とは? 体内リズムが生活全般に影響 人生の3分の1を占めるといわれる「睡眠」ですが、日本人の5人に1人は睡眠に対し、不眠などの悩みを抱えているといわれます1)。睡眠時間の不足はもちろんのこと、寝付けない、夜中

アッヴィ、自己免疫疾患アートプロジェクト「第3回 PERSPECTIVES」作品募集を開始<募集期間延長>
アッヴィ合同会社(本社:東京都港区、社長:ジェームス・フェリシアーノ、以下、アッヴィ)は、自己免疫疾患の患者さんを対象としたアートプロジェクト「第3回 PERSPECTIVES」への作品募集を開始します。募集期間は、2020年6月1日より2021年1月15日までです。

動画で学ぶ! 在宅での創傷治療【PR】
2025年には、65歳以上の高齢者は3,657万人となると予測されており、現在、在宅医療が推進されています。 在宅医療を行うためには、病院や多職種との連携は欠かせません。さらに、在宅での治療ならではの気をつけるべきこともあります。 この記事では、現在、創傷専門の在宅療

ねじ子のひみつ手技 動画「心肺蘇生法 #9」
@media screen and (max-width: 980px){.post__header .thumbnail img {width: 100%;}} さて、いよいよ、道ばたで倒れた人に対する救急処置のお話をはじめます。道ばたでピンと来ない人は、ご家族が突然あ

患者さんの保温、どうしてる?―感染対策にも役立つ保温ブランケットについて知ろう!―【PR】
体温調節・体温管理が必要な場面とは? 病院内は一定の温度に保たれていますが、患者さんを保温する必要があるケースがあります。 患者さんの保温が必要なケース 周術期の患者さん カテーテル室で処置を受ける患者さん 悪寒戦慄のある患者さん それぞれの場合

K式スケール、在宅版K式スケール(在宅版褥瘡発生リスクアセスメント・スケール)
1.K式スケール、在宅版K式スケールは何を判断するもの? K式スケールは、前段階要因と引き金要因を、Yes、Noの2択式で評価します。 「金沢大学式褥瘡発生予測尺度」とも呼ばれ、当時金沢大学医学部保健学科教授(現・東京大学大学院医学系研究科教授)の真田弘美

ねじ子のひみつ手技 動画「心肺蘇生法 #8」
@media screen and (max-width: 980px){.post__header .thumbnail img {width: 100%;}} さて、いよいよ、道ばたで倒れた人に対する救急処置のお話をはじめます。道ばたでピンと来ない人は、ご家族が突然あ
第19回 肥厚、爪白癬、変形した爪③〜肥厚した爪のケア
今回で肥厚した爪のケアは最後です。 よくご質問をいただく、肥厚した爪、特に白癬があり爪と皮膚の境目が不明なケースについて詳しくみていきましょう。 これまで、爪切りの前処置として爪周囲の確認と角質や爪にはさまったものを取り除くことで安全にケアができると説明してき

ねじ子のひみつ手技 動画「心肺蘇生法 #7」
@media screen and (max-width: 980px){.post__header .thumbnail img {width: 100%;}} さて、いよいよ、道ばたで倒れた人に対する救急処置のお話をはじめます。道ばたでピンと来ない人は、ご家族が突然あ

厚生労働省危険因子評価表
1.「厚生労働省危険因子評価表」は何を判断するもの? 厚生労働省が提示する「褥瘡対策に関する診療計画書」により定められた、褥瘡発生のリスクを判断するスケールです(図1)。 平成24年度(2012年度)の診療報酬改定から、褥瘡対策が入院基本料の算定要件に組み

ブルンストローム・ステージ(Brunnstrome stage:Brs)
【関連記事】 ●脳出血の治療と看護ケア ●脳卒中(脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血)の基礎と看護の役割 1.このスケールは何を判断するもの? ブルンストローム・ステージ(Brunnstrome stage)とは、主に脳血管障害による片麻痺の回復過程

ねじ子のひみつ手技 動画「心肺蘇生法 #6」
@media screen and (max-width: 980px){.post__header .thumbnail img {width: 100%;}} さて、いよいよ、道ばたで倒れた人に対する救急処置のお話をはじめます。道ばたでピンと来ない人は、ご家族が突然あ
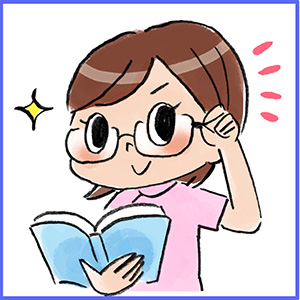
ウロストミー(尿路ストーマ)の基本知識|種類と主な造設例
ここでは、ストーマケアを行うにあたり、まずは知っておきたいウロストミーの基本知識を解説します。 【関連記事】 ● ストーマの種類―造設部位別ストーマ● ストーマ装具交換の手順 ウロストミーとは ウロストミー(尿路ストーマ、人工膀胱)は、正常な尿路(膀
心臓カテーテル検査の看護|手順・合併症ケア・観察項目
【関連記事】 ● 心不全薬の種類・作用機序 ● 連載「循環器科で必要な看護技術を学ぼう!」 心臓カテーテル検査とは 直径1mm程度の細く柔らかい管を、血管内から大動脈や心臓内に挿入して行う検査です。穿刺する場所は大腿の付け根、手首、腕、頸

ねじ子のひみつ手技 動画「心肺蘇生法 #5」
@media screen and (max-width: 980px){.post__header .thumbnail img {width: 100%;}} さて、いよいよ、道ばたで倒れた人に対する救急処置のお話をはじめます。道ばたでピンと来ない人は、ご家族が突然あ


