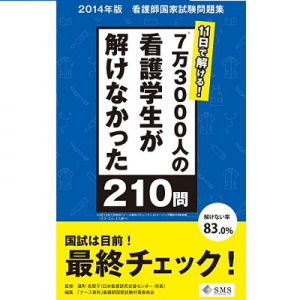CASE16 モルヒネへの恐怖心から疼痛コントロールが図れない
CASE16 モルヒネへの恐怖心から疼痛コントロールが図れない
- 公開日: 2017/6/7
困難事例16 認知症により疼痛コントロールが図りづらいケース
Cさん、80歳男性。膵臓がんが末期の状態で見つかり、手術は不可能なレベルであったため、通院にて内服による対症療法を行い経過観察中である。
認知症があるため、どの程度の痛みがあるのかがはっきりせず、また家族は麻薬を用いた疼痛コントロールに困惑気味である。
高齢なため進行は遅いだろうと医師より言われていたが、最近では食事も摂れないことが増え、急激に体重が減少しており衰弱傾向にある。
カンファレンスの目的
疼痛コントロールのために、麻薬を処方されているものの、認知症により痛みの訴えがわかりづらい。また、家族が麻薬の使用に対して抵抗感をもっており、なかなか効果的な疼痛緩和に踏み切れない現状があった。そこでカンファレンスを開くこととなった。

かな:はじめは弱オピオイド系のトラムセットを1日に朝昼夕寝る前の4回飲むことで落ち着いていたのですが、最近、朝の腹痛が増えてきて朝食が食べられなくなってきているようです。

さき:寝る前の薬は何時に飲んでいて、朝の薬は何時に飲んでいるんですか?

かな:寝る前は21時です。そして朝の薬は7~8時の間なので、そこだけ時間が長く空いてしまうために痛みが出ているのではないかと思います。

さき:1日4回でしたら、だいたい5~6時間ごとに飲む感じになりますよね。夕の薬は18時くらいとして、寝る前の薬は本当は23時くらいに飲むのが理想的ですね。でもCさんは寝てしまうから21時になってしまうのですね。ならば朝、少し早目に起きてもらい、痛みが出る前に飲むかたちにしてみたらどうかしら?

かな:はい。以前にもそのように提案はしたのですが、ご家庭の方に、家族の生活のリズムに合わないから難しいといわれて変えられなかったのです。

りん:在宅は病院とは違い、家族の生活もありますからね。とりあえずアドバイスだけ続けて経過観察をしてみましょうか。
こうして経過をみることとなったが、やはり朝の腹痛が原因で朝食が摂れないことが多く、デイサービスにも行けなくなることが増えてきた。そこで、かなは主治医に状況報告のファックスをすることにした。

かな:主治医に相談をしたところ、レスキューとして朝に追加で飲むようにオプソが処方されました。でもご家族には、麻薬はあまり使わないほうがいいというイメージがあるようで、オプソをモルヒネ系のレスキューであると説明したら、抵抗がある雰囲気でした。

りん:Cさんには認知症があるため、痛いという訴えが痒いに変わってしまったり、聞く相手によって返事も変わってしまって、よけいに痛みを把握しづらいですよね。そこをご家族はどう把握されているのかしら。

かな:はい。はじめは確かにCさんの訴えも曖昧でしたが、最近は「チクチクする」とか「お腹が爆発しそう」など表現が強くなってきています。さらに発言のみられたときには、実際に食事も摂れなくなっているので、本当に痛みが強くなってきているのだと思います。
そこでご家族には、痛みがわかりにくいときは、訴えだけでなく、表情や身体の動き、食欲などもあわせて評価してくださいとお伝えしています。

りん:それで、レスキューは有効に使われている感じですか?

かな:それが・・・。「レスキューは朝の定時処方として出されているから、なるべく食後に飲ませなければ」というイメージが強いらしく、結局は痛みが出てから飲むというタイミングになってしまって、朝食を食べられないことが続いていました。
そこで、痛みの出方がパターン化しているならば、予防的に食事に関係なく、早目に飲むという方法もあることを再度説明したところ、やっと納得してくださったようです。
先日訪問したときは、「あのやり方でやってみたら、朝の痛みの訴えがなく、久しぶりに朝食が摂れました」と喜ばれていました。

たーちん:やはり一般の方にとって、モルヒネは怖いというイメージには根強いものがありますね。使ったら意識がなくなるとか、依存性が高くなるとか、命を縮めるとか。でも、ターミナルの方にとって、痛みを上手に軽減することができるモルヒネは、残された時間を有意義に過ごすための大切なアイテムでもあると思います。激しい痛みは体力を消耗してそれこそ命を縮めてしまいますからね。

かな:病院では麻薬の管理は医療者がするため、家族は安心して受け入れることができても、在宅では、特にご本人に認知症がある場合、ご家族が痛みの評価をせざるをえなくなるため、ご家族のプレッシャーや恐怖心は強いと思います。
そこで、どのような観察項目がありどのように観察すればよいのかとか、医療的な麻薬に対する正しい情報提供などをしっかり行うことで、家族全体への精神的なサポートを行うことが重要になってきますね。

りん:そうですね。今後は痛みの増強により、使う頻度も増えてくることが予想されますし、急変も考えなければいけないと思います。
在宅で看取りになるのか、それともギリギリまで在宅でみてから最後は病院なのかによっても、往診医に切り替える必要があるのか、ホスピスの予約なども検討すべきなのかなど、考えなければなりませんからね。

かな:はい。次回、担当者会議があるので、ケアマネジャーにも相談にのっていただき、今後の具体的な方向についてもみんなで話し合っていきたいと思います。
次回は、主治医の方針が見えない事例について紹介します。
ステーション「よつば」スタッフプロフィール
りん(所長)
訪問8年目(看護歴32年救急他)在宅ケアでの創意工夫の才能はピカイチ。勉強家で人情が厚く面倒見がよい。スーパーポジティブ思考の持ち主。
さき
訪問6年目(看護歴28年オペ室他)
神社仏閣巡りが趣味の歴女。またDIYも得意。面白き事もなき世をおもしろくが座右の銘。夢への妄想パワーは半端なし。
たーちん
訪問11年目(看護歴33年):スーパーグランマナースで超自由人。しかし可愛い笑顔で憎めない。利用者さんの為ならエンヤコラ。テニスから茶道までサラリとこなす我がステーションの親分的存在。
ほのか
訪問1年8カ月(看護歴15年小児科他)老若男女に好かれる天性の明るさの持ち主。癒し系キャラ。現在、スポーツクラブのZUMBA(ダンス)にハマっている。
かな(主任)
訪問5年目(看護歴16年。NICU他)思い込んだら一直線。やや天然ボケあり。訪問看護と猫と執筆活動(この原稿含)と音楽活動をこよなく愛している二児の母。
カテゴリの新着記事
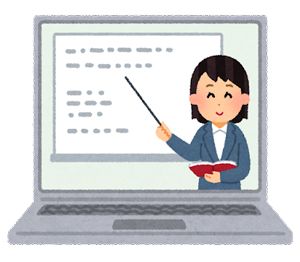
在宅でのスキンケアQ&A|2024年2月開催セミナーレポート【PR】
在宅療養者によくみられるスキントラブルとケア 在宅で療養している人の70%以上が、なんらかのスキントラブルを抱えているという報告があります1)。内訳をみると真菌感染症、湿疹や皮膚炎、IAD(失禁関連皮膚炎)が多く、そのほかにドライスキン、皮膚の浸軟、スキン-テ
-
-
- スキントラブルが起きやすい患者さんのケアで気をつけることは?【PR】
-
-
-
- ワセリンを塗布していて浸軟してしまった皮膚はどうケアする?【PR】
-
-
-
- 褥瘡にポケットがある患者さんへの在宅でできるケアの工夫とは?【PR】
-
-
-
- 清潔ケアへの拒否が強い患者さんへのケア、どうする?【PR】
-