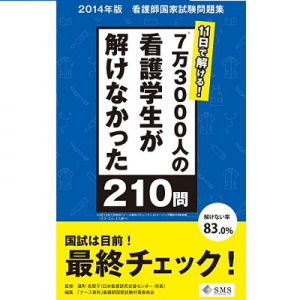肺炎の診断のポイントと看護師の役割は?
肺炎の診断のポイントと看護師の役割は?
- 公開日: 2017/8/21
看護師は問診だけでなく、バイタルサインにも注意!
問診や診察所見、検査から総合的に判断する
肺炎自体の診断は、問診、診察所見、血液検査所見、胸部X線検査で総合的に判断します。
問診(症状や病歴)で重要なのは、発熱、咳嗽、喀痰、呼吸困難、倦怠感(活動性低下、食欲低下)、意識障害、胸痛などで、これらが比較的急性に出現した場合に肺炎を疑います。同じように発熱、咳嗽、喀痰が出現する急性上気道炎(いわゆる風邪症候群)では、倦怠感は軽度で、くしゃみ、鼻水、咽頭痛などの症状が主体となります。
診察所見で重要なのは、バイタルサインと脱水の有無です。バイタルサインの意識レベル、血圧、呼吸数は(肺炎が重症化すると生じる)敗血症の診断に特に重要で、その他、体温、脈拍数、SpO2も測定します。
脱水は皮膚、粘膜の状態から判断しますが、高齢者では見た目では難しい場合が多いため、血液検査でBUNが21mg/dL以上になっていないかどうかも目安とします。
参考になった
-
参考にならなかった
-