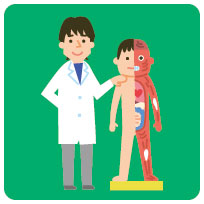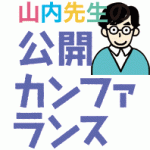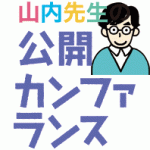 第40回 インスリン注射が必要となった患者さんの課題とゴール
第40回 インスリン注射が必要となった患者さんの課題とゴール
- 公開日: 2017/8/15
入院しているときのことだけでなく、退院後の患者さんの生活までを想像して看護にあたることが大切です。今回は、患者さんを包括的に捉えると、どのようなことが課題となるのかを考えます。
【今月の事例】
一過性脳虚血発作で入院中の80歳代女性。認知症もなく、ADLは自立しています。入院中に糖尿病と診断され、インスリン注射が開始となりました。患者さんは、糖尿病性網膜症で全盲の長男(ADL自立)と2人暮らしで、自宅では長男のインスリン注射は患者さんが行っていました。そのほかに、遠方に住む次男がいます。
患者さんは人から注射をされるのは大丈夫ですが、自分にするのは怖いからできないという方でした。また、食べ物の好みがはっきりしており、喫食率にもムラがあるため、毎食前に血糖値を測定しなければならない状態でしたが、血糖測定も自分では怖くてできませんでした。
→こんなとき、あなたならどうする?
みんなの回答
ナース専科コミュニティの会員に聞きました。回答者数は、83人。
| Q1.この事例で課題となるものはなんでしょうか。 | Q2.Q1で挙げた課題を解決するために、あなたならどのようなアプローチをしますか。 | ニックネーム |
|---|---|---|
| ・血糖のコントロールができていない、・血糖測定やインスリンが自分に対しては施行できないということは、自身の病状を受け入れきれていない可能性がある、・本人のADLが自立しているため、訪問看護などの介入が難しい。また、患者さんを支援できる家族は遠方で同居家族は全盲のため、生活が変化したときに再構築が難しい | ・患者さんの病状理解を深め、血糖コントロールできるよう、食事指導を再々行う、・模型に血糖測定やインスリンの練習をする、・血糖測定等練習するときは、1項目ずつ患者さんがするようにして、徐々に患者さんがする率を増やしていく(初めは針数などのセットだけ、測定する指の決定、消毒、測定器を当てるなど)、・患者さんが今自分でできることは何か一緒に考える(否定ではなく肯定できることを探す)、・もしくは、長男と一緒に手技の再取得を目指す(例えば、準備等は患者さん、血糖測定やインスリンの針を刺すのは長男など) | ゆいさん |
| 代わりに打ってくれる人がいない。患者さん自身がインスリンをなぜ必要となっているのか病状を理解しているかわからない。高齢者でインスリン導入は本当に必要? | 医師に絶対にインスリンが必要か再度確認する。今導入しても継続できるか不安。途中で中断してさらに悪化させてしまう可能性も高い。内服薬でコントロールして外来受診時に血糖測定や、採血でHbA1Cを診ていくのはどうか? | Yumejiさん |
| ・インスリン注射や血糖測定を自己で行うことに恐怖心がある ・インスリン注射ができない恐れがある。患者さんが入院中に長男がインスリン注射が継続できない可能性がある ・食事療法ができない可能性があり、血糖コントロールが図れない恐れがある | ・インスリン注射は皮下注射で、針は蚊の足の太さと変わらないため痛みが少ないことを説明する ・インスリン注射と血糖測定がなぜ自己でできそうにないか、理由を尋ねる ・入院中の長男のインスリン注射はどうしているのかを確認する | こりんさん |
| 自分ではインスリン注射ができないこと、長男が視力障害。近くに、助けてくれる親戚、家族がいない | 訪問看護入れる。毎日クリニックに通う。治療法を検討してもらう | かめさん |
| 患者さん入院中の長男の血糖コントロール。自己血糖測定とインスリン注射 | 全盲の長男の社会資源。障害者手帳確認、訪問看護など利用可能か、MSWにも情報提供し相談。血糖測定とインスリン注射の恐怖心を取り除いていく。何が恐怖なのか、痛みなのか、未経験だからなのかをアセスメントする。はじめは看護師が実施し、恐怖の原因が減ってくれば、自己実施に切り替える | あみ、さん |
| 食事療法とインスリンの自己注射。また、家族の協力が得られえないこと | 食事療法を行うために、栄養指導を受けてもらう。また自己注射に関しては、手技は問題ないと思われるので、徐々に慣らしながら、自分注射できるように見守る。次男の協力を得る | CITYさん |
| 患者さん自身のインスリン注射と食事管理、また患者さん入院中の長男のインスリン注射をどうするのかという課題 | 患者さん本人に対しての食事指導と、訪問看護師の導入 | りんさん |
| 退院後、血糖のコントロールが困難である。食事の習慣を80代で変更するのは難しい。長男が自分でインスリンができない。家族のサポートが弱い | 現状や今度の危険性を理解してもらい、自己注射ができるようにする。食事は譲れるところを見付けて、少しずつ変更してもらう | まなさん |
| 血糖コントロール、自己測定、自己注射、息子の注射 | 在宅に戻る為に必要な事、優先順位を付け考える。自己でどれくらいまでできるかの確認。介護保険サービスも含め検討 | ちょこさん |
| 退院後の自宅での生活における血糖測定とインスリン注射をどのように行うか。脳虚血疾患で後遺症が残った場合の、同居する長男のインスリン注射を今までどお女性が行えるのか? | 自身への血糖測定とインシュリン注射を行えるように、訓練する。脳虚血疾患の後遺症が残らないよう、リハビリを行う | にこさん |
1
2
参考になった
-
参考にならなかった
-