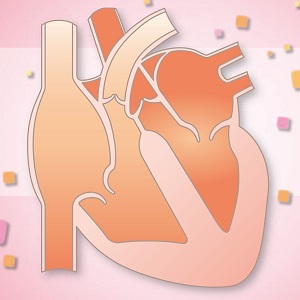健康寿命をおびやかす慢性腰痛〜高齢者に適した運動療法、その効果と課題〜
健康寿命をおびやかす慢性腰痛〜高齢者に適した運動療法、その効果と課題〜
- 公開日: 2020/7/10
2020年3月9日に東京・丸の内にて、日本シグマックス株式会社による慢性腰痛プレスセミナーが開催されました。今回のテーマは「健康寿命をおびやかす慢性腰痛〜高齢者に適した運動療法、その効果と課題〜」。金沢大学整形外科助教の加藤仁志先生が、高齢者に適した運動療法とその効果と課題について講演を行いました。このプレスセミナーについてレポートします。
慢性腰痛の疫学と患者さんを取り巻く現状
厚生労働省の報告によると、腰痛の生涯罹患率は85%です。これは、国民愁訴の男性1位、女性2位となります。
さらに日本で行われた規模住民コホート研究では、40歳以上の腰痛有病率は37.7%、推定患者数は2700万人を超え、まさに腰痛症は国民病ともいえます。
2012年に発刊された腰痛診療ガイドラインでは、腰痛の実に85%が明らかな原因がない「非特異的腰痛」である、とされています1)。しかし、これは米国の総合診療医の情報を統合したデータを基にしたものです。日本では腰痛のある患者さんを診るのは整形外科医であり、2016年には「非特異的腰痛は22%に過ぎなかった」という研究報告もされています2)。ただ、実際のところ非特異的腰痛は腰痛の半数を占めるのではないかとみています。
また、腰痛のほとんどは心配しなくていい腰痛であるものの、「心配がなくても困っている」、「この痛みを何とかしてほしい」という患者さんの希望が多いのが現状です。
今後、慢性腰痛のような慢性疼痛患者さんは増え続けると予測できます。疫学調査によると、その中でも慢性腰痛が最も多く、持続期間も一番長いということが明らかとなっています。
しかし、運動器慢性疼痛の治療に対する満足度をみると、半数以上の患者さんは治療に満足していません。慢性疼痛は長期的な痛みです。治療したときだけ症状が和らぐのではなく、長い期間その痛みが改善されていないといけないため、患者さんは満足しないのです。
慢性腰痛の治療には①薬物療法、②運動療法、③認知行動療法の3つがあります。いずれも高いエビデンスで有効性が示されていますが、この中で大切なのは運動療法です。薬物療法と認知行動療法は受け身の治療法であり、治療したときだけ改善を認めます。それに対し、運動療法は痛みを持続的に軽減し、身体を強く元気にします。
人は、年齢を重ねると運動器の障害によって要介護状態となるリスクが高くなったり(ロコモティブシンドローム:以下ロコモ)心と身体が弱った状態(フレイル)となったりします。このロコモを予防するために実施する運動プログラムにおいて、体幹へのアプローチや慢性腰痛に対する運動アプローチが抜けているのではないかと考えています。
慢性腰痛に対する診療の問題
慢性腰痛に対する治療として、運動療法の高いエビデンスが示され、腰痛診療ガイドラインにも有効であるとされています。しかし、「どのような方法で、どの程度行えばよいかは明らかではない」と書かれています。
腰痛に対する運動療法で大切なのは、①有酸素運動、②体操、ストレッチ、③筋肉強化の3本柱です。腰痛に対する筋トレには、Lumbar stabilization(腹筋主体の運動)である①腹横筋を選択的に収縮させる、つまりお腹を凹ます「ドローイン」と、②腹筋群全体を収縮させる、つまりお腹を固める「プレーシング」があります。
この2種類のうち、高齢者が体幹運動を行う場合はブレーシングに注目すべきです。腹横筋だけにターゲットを絞りエクササイズをしても、運動機能が落ちている患者さんに対しては限界があります。やはり使える体幹筋をすべて総動員して、最低限必要な運動機能をしっかり上げてあげるという意味では、ブレーシングが必要だと考えています。
ただし、高齢者の運動となると、「痛みや脊柱変形、筋力低下で、継続して実施できない」、「効果が出るまでに時間がかかる」などの問題があります。高齢者に理想的な運動療法のポイントは、誰でも実施可能で、痛みが改善される前から早く効果を実感できることです。
より実用的な運動療法の提案
高齢者でも可能な体幹筋強化の方法のポイントは、①痛い腰部に負担をかけないように、座位や立位で可能なこと、②体力や筋力がなくても可能なこと、③体幹筋力を測定できること、の3つです。
この3つを考慮し、シグマックス社と共同で開発したものが体幹運動器具「RECORE」
です。血圧計のカフのようなものをお腹に巻き、空気を注入してお腹に圧力をかけ、その圧力に抵抗することでブレーシングが行えます。
この体幹運動器具は、慢性腰痛や骨粗しょう症がある高齢者でも無理なく体幹筋トレーニングができ、腹筋だけでなく横隔膜や骨盤底筋の運動にもなります。さらに、腹部体幹筋力の測定、トレーニングによる慢性腰痛やロコモの改善、腰椎圧迫骨折や分離症に対して早期から運動介入が行えます。
引用・参考文献
1)日本整形外科学会/日本腰痛学会,監:定義.腰痛診療ガイドライン.南江堂,2012,p.13.
2)Hidenori Suzuki:Diagnosis and Characters of Non-Specific Low Back Pain in Japan: The Yamaguchi Low Back Pain Study.PLoS One 2016;11(8):e0160454