 血糖測定器による血糖測定の手順・注意点
血糖測定器による血糖測定の手順・注意点
- 公開日: 2016/11/10
血糖値の測定は、糖尿病など糖のコントロールが必要な疾患では不可欠な手技。
看護師による測定が適切な血糖コントロール、ひいては糖尿病患者さんのセルフケアの習得にもつながります。
しっかりと手順を確認していきましょう。
【関連記事】
● 糖尿病の看護|分類、治療、合併症、看護計画
● 【糖尿病】血糖コントロールの指標と方法(食事・運動・薬物療法)
必要な物品
※具体的には各施設で定められた手順に従ってください。
・血糖測定器
・測定用チップ
・穿刺器具・穿刺針
・ディスポーザブル手袋
・ディスポーザブルエプロン
・ゴーグル
・アルコール綿
・膿盆(またはゴミを入れる容器)
・感染性廃棄物容器
血糖測定の手順
※具体的な手順は各血糖測定器の説明書に従ってください。
患者さんへの説明
患者さんに血糖を測定することを説明して同意を得ます。
患者さんに手を洗ってもらう
患者さんの手に果物の汁などの糖分が付着していると、測定結果を及ぼすことがあるため、手洗いをしてもらいます。
血糖測定器に電源を入れて、動作確認を行う
手指衛生を実施し手袋を着用する
血液曝露予防のため、必ず手袋・エプロン・ゴーグルを着用しましょう。
穿刺針を装着して、穿刺部位を決める
穿刺部位には、指先、手のひら・前腕などがありますが、基本的には測定値の変動が少なく、穿刺しやすい指先が選択されます(図2)。
手を使う作業が多い、血糖測定が長期にわたっているなど、指の皮膚が硬く厚くなっている場合は、穿刺器具の穿刺強度のダイアルを調整して穿刺の強さを強くするか、指先以外の部位を選択します。
指先では、中央部は痛みを感じやすいため、やや側面に穿刺するとよいでしょう(図1)。
皮膚が硬くなるのを防ぐため、毎回、穿刺する位置を変えるようにします。


穿刺部位をアルコール綿で消毒する
アルコールの成分が残っていると、測定結果に影響を及ぼすことがあるため、アルコールが十分に乾燥してから穿刺を行うようにします。
穿刺をする
穿刺する部位を支えている手をテーブルの上につけるなど、しっかりと固定してから穿刺します(図3)。
穿刺部位が十分に固定さていないと、うまく穿刺ができないこともあります。
指先に穿刺する場合、穿刺前に軽くマッサージをしておくと穿刺後に血液が出やすくなります。

この記事を読んでいる人におすすめ
「血糖」の働きとコントロールの必要性
身体を危険から守る働きをする「血糖」 「血糖」とは、血液中のブドウ糖のことです。私たちは、主要なエネルギー源として、食事により炭水化物を体内に取り込みます。炭水化物はブドウ糖が何千個とつながったもので、身体に入ると消化器官の酵素で分解され、単糖類であるブドウ糖となっ
【糖尿病】血糖コントロールの指標と方法(食事・運動・薬物療法)
糖尿病で怖いのは合併症です。血糖コントロールはその予防につながる大切な要素ですが、ただ単に血糖値を下げればよいというわけではありません。血糖値をコントロール「できない!」トラブルを解決する前に、まずは血糖コントロールの基本をおさらいしていきましょう。 【関連記事】

覚えた? 急変時の採血スピッツ5種類(血算・生化学・凝固・血液型・血糖)
急変時に、医師から「採血して!」と一言で指示を受けた場合。 「どのスピッツを準備すればよいのか」「医師は一体何を調べたいのか」と迷ってしまうことがあります。医師はどんな基準で考え、指示を出しているのかを解説します。 【関連記事】 ● 【採血・注射】血管が逃げる・動
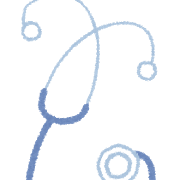
バイタルサインとは|目的と測定の仕方、基準値について
*2019年3月13日改訂 *2020年4月15日改訂 *2022年4月28日改訂 バイタルサインとは バイタルサインとは「生命徴候」のことで、「脈拍」「呼吸」「体温」「血圧」「意識レベル」の5つがバイタルサインの基本です。病院では基本的に朝・昼・晩と1日3

血液媒介病原体曝露防止と曝露時の対応
※ここでは血液媒介病原体の曝露防止策と曝露してしまったときの対応を解説します。実際の対応に際しては、各医療施設で示されている感染対策に従いましょう。 個人防護具の適切な活用 注射針の刺入・抜針、採血時には必ず手袋を使用します。手指に傷がある場合、手袋の着





