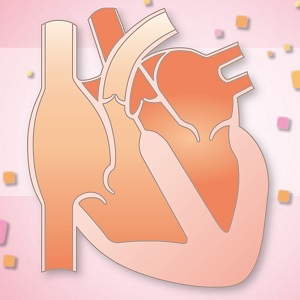 降圧薬の種類・作用機序と使い分け
降圧薬の種類・作用機序と使い分け
- 公開日: 2017/8/2
高血圧に使う薬
「高血圧治療ガイドライン」は、西暦で4と9のついた年、つまり5年ごとに見直されています。2009年に発表されたガイドラインでは、第一選択薬はカルシウム拮抗薬、サイアザイド系利尿薬、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬の5種類でしたが、最新の2014年のガイドラインではβ遮断薬が外れて4種類となりました。しかし、β遮断薬を第一選択薬から外すにあたっては異論もあったようで、上記の4種類にβ遮断薬を加えた5種類を主要降圧薬とする紛らわしいくくりもいまだに残されています。
主な降圧薬を表1に示します。

■作用機序
血圧は、収縮期血圧・拡張期血圧・脈圧(=収縮期血圧-拡張期血圧)に分けて考えましょう。収縮期血圧と拡張期血圧は次のように決まってきます。
収縮期血圧 = 心拍出量 ÷ 動脈のコンプライアンス
拡張期血圧 = 心拍出量 × 末梢血管抵抗
心拍出量は両者に共通なので、収縮期血圧と拡張期血圧の違いは、動脈のコンプライアンスと末梢血管抵抗により生じます。動脈のコンプライアンスと末梢血管抵抗を理解するためには、動脈には弾性血管と筋性血管があることを知る必要があります。弾性血管は、大動脈などの太い血管で弾性線維に富んでいます。動脈のコンプライアンスは、簡単にいうと弾性血管の伸びやすさ(=柔らかさ)です。動脈硬化が進むと、コンプライアンスは小さくなります。したがって、収縮期血圧が高く脈圧が大きいほど動脈硬化が進んでいると考えましょう。








