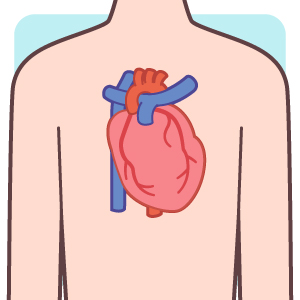第4回 小児の吸入療法|吸入機器の種類・特徴・吸入手順・注意点
第4回 小児の吸入療法|吸入機器の種類・特徴・吸入手順・注意点
- 公開日: 2022/2/5
吸入療法とは
吸入療法は、気道や肺胞に直接薬剤を沈着させ、局所における作用・効果を発揮する治療方法です。内服や点滴に比べて少量で高い即効性が得られ、副作用も少なく、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease:COPD)といった呼吸器疾患の治療に用いられています。
吸入療法により気道を加湿することで、気道粘膜の保護や排痰にも効果があるため、小児科領域では気管支喘息のほかに、重症心身障害児や神経筋疾患児の排痰促進を目的として使用されることもあります。
吸入療法には、さまざまな方式が開発されていますが、間違った手技で行うと本来の効果が得られません。薬剤の選択だけではなく、適切な吸入機器の選択、デモ機などによる吸入手技の実施および吸入手技の指導も非常に重要です。
吸入機器の種類と特徴
小児に行われる吸入療法は大きく分けて、ネブライザー、加圧式定量噴霧吸入器(pressurized metered-dose inhaler:pMDI)、ドライパウダー吸入器(dry powder inhaler:DPI)があります。それぞれ利点・欠点があるため、特性を理解し、患児の病態や疾患、状態に合わせて適切な方法を選択します。
また、吸入機器により薬剤の粒子径が異なります。粒子径は、気道や肺胞への薬剤の分布に影響することも理解しておきましょう(表1)。
表1 エアロゾルの粒子径と沈着部位ネブライザー
薬液を霧状の粒子(エアロゾル)にして噴射し、吸入する方法です。エアロゾル化させる方法により、ジェット式ネブライザー、超音波式ネブライザー、メッシュ式ネブライザーに分けられます(表2)。
ネブライザーは通常の呼吸で吸入可能なため、乳幼児にも使える点がメリットといえます。ただし、使用後は洗浄し、清潔に保つことが重要であり、管理がやや煩雑になります。そのため、医療機関で使用されることが多いですが、小児の場合、管理が簡便な家庭用の製品を購入し、使用することもあります。
表2 ネブライザーの種類と特徴
加圧式定量噴霧器(pressurized metered-dose inhaler:pMDI)
圧力によってボンベから噴射される霧状の薬剤を吸入する方法です。吸気に合わせて薬剤を噴射し、深くゆっくり吸入します。
pMDIの利点として、呼吸機能が低下している患児でも使用しやすいこと、小型で軽量なため、携帯しやすいことなどが挙げられます。一方、吸気のタイミングに合わせてボンベを押して噴射させる必要や、一定の力を入れてボンベを押す必要があり、小児などには扱いが困難な側面があります。
吸気に合わせた吸入が難しい小児の場合、筒状の吸入補助器具(スペーサー)の使用が勧められます(図)。スペーサーの中に事前に吸入薬を噴射して充満させ、その充満した薬剤をゆっくり吸入するため、より効率的に吸入できます。ただし、スペーサーは携帯性に欠けるほか、常に清潔に保つために洗浄などの管理が必要になります。
静電気が発生すると、スペーサー内にエアロゾルが多く沈着し、肺内への沈着が低下するため、静電気が発生しにくいように作られている製品を使用します。
図 スペーサー(製品例)
ドライパウダー吸入器(dry powder inhaler:DPI)
粉状の薬剤を能動的に吸入する方法です。通常、吸入器に1回分の粉状の薬剤を充填させて吸入します。薬剤の入ったカプセルやディスクをセットするタイプや、吸入器内部でカートリッジが回転して薬剤が充填される方法など、メーカーによってさまざまな種類があります。
DPIは、pMDIよりも1回吸入量や残量が管理しやすいうえ、呼吸に同期させる必要がなく、吸入補助具も不要で容易に吸入でき、携帯性にも優れています。一般的には5歳以上であれば使用できるとされていますが、pMDIと比較して強く速く吸入する必要があるため、吸気流速が弱い小児や呼吸機能が低下している患児においては、うまく吸入できない場合があります。
吸入デバイスによって操作性や吸入薬の肺での到達度も異なるため、操作性や特性をよく理解し、患児にとって使いやすく、正しく使用できる吸入デバイスを選択することが重要です。また、吸入薬を変更するとデバイスも変更になることが多い点にも注意します。
吸入機器の使い方、注意点
pMDIを用いた場合
吸入療法で症状が改善しない患児では、吸入方法が間違っているケースが少なくありません。pMDIで正しく機器を使用した際の懸濁タイプの肺内沈着率は10~30%程度、溶液タイプは30~40%程度といわれています1)。吸入方法には、吸入口を唇から3~4cm離すオープンマウス法と、吸入口を軽く噛んでくわえるクローズドマウス法があります。一般的にオープンマウス法のほうが肺内沈着率が高いとされていますが、薬剤によってはクローズドマウス法のほうが肺内沈着率が高い場合もあり、どちらの方法で行うかは各施設や患児の状態によってさまざまです。吸入療法を実施する際に、患児が好む方法や実施しやすい方法を選択するようにしましょう。
通院の際など、看護師が定期的に吸入方法をチェックすることで間違った吸入を避けることもできます。pMDIを用いた場合の吸入手順を示します(表3)。
表3 pMDIを用いた場合の吸入手順
pMDI+スペーサーを使用する場合
吸気に合わせた吸入が難しい場合や、何度指導しても正しく吸入できない患児には、スペーサーの使用を勧めます。スペーサーを使用する際には、まず子どもに触らせてみたり、大人が楽しそうに吸入する姿を見せるなどして、吸入療法への恐怖感を軽減させるようにしましょう。スペーサーに子どもの好きなキャラクターのシールを貼るなどの工夫をしてもよいかもしれません。
小児でスペーサーを使用する場合は、成長に応じてマスクタイプかマウスピースタイプかを選択すると、効果的にpMDIでの吸入療法を行うことができます。乳児など、呼吸をうまく止めることができない場合にはマスクタイプを使用します。マスクタイプを使用する際は、マスクを軽く当てたままにして何度か呼吸をさせることで効果的に薬剤を吸入することができます。
吸入療法について、ある程度理解ができるようになった幼児ではマウスピースを選択し、学童以降は基本的にスペーサーは不要となります。スペーサーを装着した場合の吸入方法について示します(表4)。
表4 pMDI+スペーサーを用いた場合の吸入手順