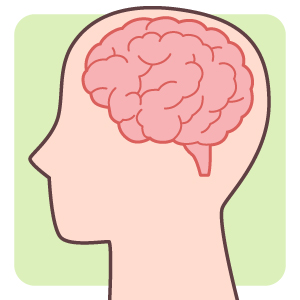原発性胆汁性胆管炎の臨床病期分類
原発性胆汁性胆管炎の臨床病期分類
- 公開日: 2025/4/9
原発性胆汁性胆管炎の臨床病期分類は何を判断するもの?
原発性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis:PBC)の臨床病期分類は、進行の程度を評価するとともに、医療費助成の対象となるかを判断するための指標です。
原発性胆汁性胆管炎は、自己免疫が関与する慢性進行性の胆汁うっ滞性肝疾患です。皮膚掻痒感、黄疸、食道胃静脈瘤、腹水といった肝障害に基づく症状がみられる症候性PBC(sPBC)と、症状を認めない無症候性PBC(aPBC)に大別されます。症候性PBCの場合、症候や肝予備能などに応じた生活指導・食事指導が必要となりますが、無症候性PBCの患者さんについては、無症候性PBCにとどまる限りは予後良好で、日常生活での制限は特にないとされています1)。
PBCの根治的治療法は確立されていませんが、第一選択薬として、ウルソデオキシコール酸(UDCA)が用いられます。ただし、進行例では期待した効果が得られない場合があるほか、肝硬変に進行すると内科的治療では限界が生じるため、肝移植が検討されます1)、2)。また、胆汁うっ滞により、骨粗鬆症や高脂血症を来したり、シェーグレン病、関節リウマチ、慢性甲状腺炎などの自己免疫疾患を合併したりすることもあり、これらに対する治療も必要になります。
PBCは指定難病とされており、一定の基準を満たせば医療費の助成を受けることができます。患者さんの負担を軽減するためにも、医療費助成の対象となるかを判断することが求められます。
原発性胆汁性胆管炎の臨床病期分類はこう使う!
PBCの診断基準を満たしているか確認したうえで臨床病期を評価し、医療費助成の対象となるかを判断します。PBCと診断された患者さんのうち、症候性PBCの患者さんについては医療費助成の対象となります。基準を満たさない患者さんでも、高額な医療の継続が必要な場合は医療費助成の対象と認められることがあります。
<原発性胆汁性肝硬変の診断>次のいずれか1つに該当するものをPBCと診断する。
②抗ミトコンドリア抗体(antimitochondrial antibody:AMA)が陽性で、組織学的にはCNSDCの所見を認めないが、PBCに矛盾しない(compatible)組織像を示すもの。
③組織学的検索の機会はないが、AMAが陽性で、しかも臨床像及び経過からPBCと考えられるもの。
原発性胆汁性肝硬変(PBC)の診療ガイドライン(2012年)における臨床病期症候性PBC(sPBC)を対象とする。
症候性PBC(sPBC):肝障害に基づく自他覚症状を有し、
s1PBC 総ビリルビン値2.0mg/dL未満のもの
s2PBC 総ビリルビン値2.0mg/dL以上のもの
*肝障害に基づく自他覚症状:黄疸、皮膚掻痒感、食道胃静脈瘤、腹水、肝性脳症など
厚生労働省難治性疾患政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班:原発性胆汁性肝硬変(PBC)の診療ガイドライン(2012年).肝臓 2012;53(10):646.より引用
引用文献
2)厚生労働省:93 原発性胆汁性胆管炎(旧称:原発性胆汁性肝硬変).(2025年3月19日閲覧)https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/upload_files/File/093-202404-kijyun.pdf