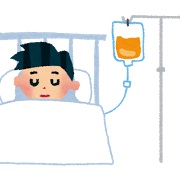厚生労働省危険因子評価表
厚生労働省危険因子評価表
- 公開日: 2020/5/17
1.「厚生労働省危険因子評価表」は何を判断するもの?
厚生労働省が提示する「褥瘡対策に関する診療計画書」により定められた、褥瘡発生のリスクを判断するスケールです(図1)。
平成24年度(2012年度)の診療報酬改定から、褥瘡対策が入院基本料の算定要件に組み込まれました。入院基本料届出の際には、日常生活の自立度によっては、この評価表により、褥瘡予防やケア介入の必要性をスクリーニングすることが必須となっています。そのため病棟看護師であれば、この評価表を必ず理解し、使えるようにしておく必要があります。
また平成30年度(2018年度)の診療報酬・介護報酬改定で、「危険因子の評価」の項目に「皮膚の脆弱性(スキン−テアの保有、既往)」の項目が加えられ、全部で8項目となりました。
この8項目に「あり」「できない」が1つでもあれば、褥瘡対策の医師および専任の看護師が適切な褥瘡対策の診療計画、または看護計画を作成し、実施します。
この評価表の特徴は、危険因子の項目に「病的骨突出」や「関節拘縮」など、高齢者特有の危険因子が含まれているために、高齢患者さんに使いやすいスケールであるということです。
また、高齢者特有の褥瘡スケールとしては「OHスケール」がありますが、入院患者さんに関しては入院時にこの評価表による評価が必須なので、この評価表と「ブレーデンスケール」を組み合わせて、リスクアセスメントをしている施設が多いようです。
このスケールは「ある(できない)」「なし(できる)」しか答えられないので、点数化はできませんが、その分、一般の看護師にも評価しやすいといえるでしょう。
さらにこの評価がケアに生かせることも特徴です。例えば、基本的動作能力の「ベッド上 自力体位変換」が「できない」のであればマットを使う、栄養状態の低下が「あり」であれば、栄養状態の改善を行う、などです。
図1 厚生労働省危険因子評価表
平成30年3月5日付け保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式43より引用
2.「厚生労働省危険因子評価表」はこう使う!
日常生活自立度を評価した後、必要があれば基本的動作能力以降について評価していきます。以下それぞれ、詳しく解説します。
日常生活自立度の評価
まず図1の「日常生活自立度」は、厚生労働省の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(図2)を用いて、自立度を判定します。
図2 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月8日 老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)より引用
この日常生活自立度が「寝たきり」のランクB1~ランクC2に該当する場合のみ、この評価表を用いて評価します。
基本的動作能力の評価
「基本的動作能力」における「ベッド上 自立体位変換」については、患者さんが「痛いけれど動ける」場合は「できない」にします。つまり自力で体位変換ができても、痛みや苦痛のために、長時間同一体位がとれない場合は「できない」とします。これは専門書で勉強していないと間違いやすいところなので、注意してください。
また、「イス上 座位姿勢の保持、除圧」については、自分で座り直したり、姿勢を傾けて苦痛を取り除くことができない、介助があってもズレて座っている人は「できない」とします。
病的骨突出の評価
「病的骨突出」があるかどうかは、一見しただけではわかりにくいので、患者さんの身体を横にしてみたり、背部もしっかり観察することが大切です。「病的」かどうかの判断が難しいと思いますが、臀筋がなく骨が突出している、臀筋よりも骨が出ていたら「あり」とします。
関節拘縮の評価
「関節拘縮」では、関節屈曲可動制限(関節の屈曲拘縮、伸展拘縮、変形など)が1カ所でもあれば「ある」とします。
栄養状態低下の評価
「栄養状態低下」については、何をもって「低下」とするのかが書かれていないので、「血清アルブミン3.5g/dL」以下を目安とします3)。ただし、入院患者さんではアルブミンが3.5g/dL以上ある人はほとんどいないので、体重の減少や摂食量も併せて評価します。
皮膚湿潤の評価
「皮膚湿潤」については、多汗、尿失禁の有無、便失禁の有無を評価します。多汗は多量の汗をかくことを指します。尿失禁は、臀部皮膚が尿でぬれていることを指します。便失禁は便が臀部皮膚についている時間があることを指します。いずれか1つでもあれば、皮膚湿潤は「あり」と評価します。
浮腫の評価
「浮腫」については、褥瘡の部分が浮腫というわけではなく、腕や脚、腹部の浮腫を示します。指で押して圧痕が残れば「あり」とします。
皮膚の脆弱性の評価
「皮膚の脆弱性」ということで「スキン−テア」の概念が入ったことは大きいと思います。スキン−テアとは、摩擦やズレにより皮膚が割けて生じる真皮深層までの損傷をいいますが、これが一般の看護師にはわかりづらいのではないかと思います。体位変換時やぶつけてできた表皮剥離、医療用テープ剥離時の表皮剥離などが原因で発生します。腕を少し引っ張っただけでも皮膚が割けてしまうということは、褥瘡もできやすいということなので、スキン-テアが「ある」か「ないか」は気をつけて見てほしいと思います。
評価は入院時に必ず行いますが、当院では入院後1週間ごとと、術後や病態の変化時にも評価をしています。
3.「厚生労働省危険因子評価表」を看護に活かす!
この評価表のメリットは、危険因子の評価をすることが、ケアに直結する、ケアに活かせることです。
基本的動作能力へのケア
基本的動作能力で、ベッド上で自力体位変換が「できない」のであれば、エアマットや耐圧分散寝具、ウレタンマットなどから、何がよいかを選択していきます。
イス上で座位姿勢の保持や除圧が「できない」のであれば、①患者さんをプッシュアップする、②少しでも姿勢が変わるように介助する、③車イス用のクッションを敷く、などのケアを行います。またリハビリ・スタッフに「どのような体位がよいか」「ここに褥瘡がある場合はどのような姿勢がよいか」「患者さんの身体に合った車椅子の選択やフットレストの調整はできるか」など、相談してみるのもいいでしょう。
病的骨突出や浮腫へのケア
病的骨突出や浮腫が「あり」の場合は、エアマットを選択します。浮腫では皮膚の耐久性が低下しているため、圧が長時間同じところにかからない除圧能力の優れたエアマットがいいでしょう。またエアマットを使っていても、4時間おきの体位変換を行うようにしましょう。そして、体位変換するときも、枕を入れながら、全体で浮かすように行います。
関節拘縮が「あり」であれば、指が重なっているところや、肘や脚が曲がっているところに褥瘡ができるので、そのような箇所がないかをしっかり観察します。そして曲がっているところには小さな枕やクッション、タオルを入れて除圧します。
皮膚湿潤へのケア
皮膚湿潤で「尿失禁」が「あり」の場合、自分で排尿でき、尿器を扱える患者さんには尿器を使ってもらいます。尿器を扱えない患者さんや失禁の患者さんには、排尿量に合わせたパットを使うなど、いろいろな失禁用具を使います。
また「便失禁」が「あり」の場合は、介助により車椅子に移乗できるのであれば、排泄はベッドから離れてポータブルトイレで行うなど、ADLが自立できるようにリハビリを行います。重度で意識がない寝たきりの患者さんで、水様便が何回も出る場合には軟便用のパットを使い、お尻に撥水性のクリームを塗ります。このように皮膚を守るケアと、排泄用具を考えることが大切です。
栄養状態低下へのケア
栄養状態低下が「あり」の場合は、栄養管理を行い栄養状態の改善を目指します。当院では体重減少率、喫食率、血清アルブミン値を定期的に測定し、栄養状態を評価し、NST介入を行います。経口摂取が可能な患者さんの場合は、必要な栄養量を経腸栄養で補給します。経口摂取が不可能な場合は、静脈栄養による補給を行います。水分摂取量が少ない場合には、水分補給を行います。
皮膚の脆弱性(スキン−テア)へのケア
スキン−テアが「あり」の場合は、ベッド周囲に衝撃吸収マットを敷くなどのベッド環境、車椅子移乗時には靴下と靴を着用して足を守る、レッグカバーを着用するなどの安全な環境を整えます。また、摩擦を軽減するためにスライディングシートやスライディンググローブなどの体位変換補助具を使用します。医療用テープの固定方法も安全な方法を検討します。
引用・参考文献
1)平成30年3月5日付け保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」における別紙様式43(2020年5月1日閲覧)https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/18kaitei/bessi/by43180305.pdf#search=%27%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81+%E8%A4%A5%E7%98%A1%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%BA%E7%99%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%27
2) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月8日 老健第102-2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)(2020年5月1日閲覧)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077382.pdf
3) 日本褥瘡学会:褥瘡予防・管理ガイドライン(第4班).褥瘡会誌 2015;17(4):523.