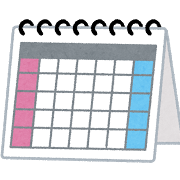第5回 無痛分娩時急変の対策と対応
第5回 無痛分娩時急変の対策と対応
- 公開日: 2021/2/7
無痛分娩の合併症は発生頻度は低くても重篤なものがあり、近年の報道をきっかけに勉強した方も多いのではないかと思います。極端な言い方かもしれませんが、出産は無痛分娩をしなくても可能であり、無痛分娩は余計に一手加える医療行為だからこそ十分な安全管理体制を整えて実施するべきです。この最終回では、無痛分娩による重篤な合併症や安全管理体制について、看護師・助産師として理解すべき重要な内容について解説していきます。
硬膜外麻酔による無痛分娩の重篤な合併症とその予防策
全脊椎麻酔、高位ブロック
全脊椎麻酔、高位ブロックとは麻酔の高さが上がりすぎる(麻酔効果が広がりすぎる)ことによって、上肢の麻痺、徐脈、低血圧など、さらに重症な場合では呼吸停止が起きることをいいます。
■原因
1. 脊髄くも膜下腔へのカテーテル迷入(誤って入ってしまう)
硬膜外腔に入れたつもりの硬膜外カテーテルが硬膜外腔のさらに奥の脊髄くも膜下に迷入(解剖については第1回参照)することで起きることが多いと言われています。脊髄くも膜下麻酔では、硬膜外麻酔よりも少ない薬の量で麻酔が広がりますので、硬膜外麻酔のつもりで薬を入れていると過量となり、麻酔の範囲が広がりすぎてしまいます。
2. 硬膜外腔への過量投与
カテーテルが硬膜外腔に正しく入っていたとしても薬を注入する量が多すぎる場合に麻酔が広がりすぎることがあります。具体的には、無痛分娩中に緊急帝王切開となった場合に注意が必要です。無痛分娩で使用していたカテーテルから、より力価の強い局所麻酔薬を数回追加投与して帝王切開術に耐えられるように麻酔効果範囲を広げます。麻酔効果範囲を広げるために、一度に大量の局所麻酔薬を投与すると麻酔が広がりすぎていることに気づかないことがあります。
局所麻酔薬中毒
局所麻酔薬の血中濃度が急激に上がることによって、耳鳴り、金属味などの症状が出て、さらに血中濃度が上がるとけいれん、不整脈、心停止が起きます。
■原因
1. 血管内へのカテーテル迷入
硬膜外腔に入れたつもりの硬膜外カテーテルが血管の中に迷入することで起きることが多いと言われています。妊娠中は硬膜外腔やその周囲の血管は怒張しているため、迷入の可能性は高くなることがあります。
2. 硬膜外腔への過量投与
カテーテルが硬膜外腔に正しく入っていたとしても、局所麻酔薬の極量(安全量の最大量)を超えて使用した場合に局所麻酔薬中毒の症状が起きると言われています。
予防策ー吸引テストと少量分割投与ー
予防策としては、硬膜外カテーテルから薬を投与する際には必ず「吸引テスト」をします。通常硬膜外腔に入っているカテーテルにシリンジをつけて陰圧をかけても何もひけませんが、カテーテルが脊髄くも膜下腔に迷入した場合は透明な脳脊髄液が、血管内に迷入した場合は血液がひけてくることがあります。
ただしこの「吸引テスト」で何もひけなかったからといって必ずしも硬膜外腔に入っているとは限らないので、薬は少量ずつ分割して投与し、産婦さんの状態に変化がないか注意深く確認しながら行います。