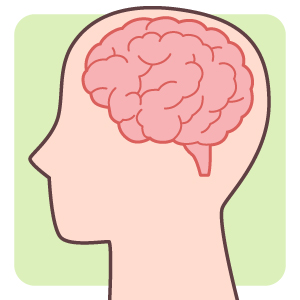SB ドレーン(バック)の挿入と管理
SB ドレーン(バック)の挿入と管理
- 公開日: 2021/5/23
【関連記事】
● 腹腔ドレーンの目的、種類、挿入部位
● 腹腔ドレーンのアセスメントのポイント【排液の量・色・合併症/刺入部】
SBドレーン(バック)とは
SBバックとは体内に留置したドレナージチューブを介し、創部からの出血、滲出液、空気などの排除や減圧を行う携帯用低圧持続吸引器です。術後の排液管理では、陰圧をかけることによって持続的な吸引が行えます。血液や滲出液が溜まりやすい部位にドレーンの先端を留置し、ゴム球を押してバックを膨らませ、陰圧をかけることで排液が促されます。
バックにはメモリがあり、排液量の確認ができます。また、バック内の排液は排液口から排出します。
閉鎖式ドレーンのため、感染性の高い術後に用いられます。
SBドレーンの目的・対象疾患
術後の排液管理(消化器疾患術後、開頭術後、乳がん術後など)
SBチューブ(ドレーン)の管理
管理は以下の目的の元に行います。
<目的>
(1)観察項目
①バイタルサインの観察
・血圧、脈拍は出血性ショックの予兆を捉える指標となるため、特に意識して観察します。
②ドレーン刺入部の観察
・刺入部の状態、滲出液の有無、ドレーンの長さ
③排液の性状
・量・におい・色
※抜去のタイミング
⇒情報ドレーンであれば基本的に1~2日で抜去します。
④バックの陰圧の状態
・排液を吸引する陰圧の強さ(ゴム球のポンピングの程度)は医師の指示に従います。バックの容量いっぱいに排液が溜まると陰圧ではなくなってしまうため、排液量にも注意します。
⑤感染の有無
・縫合部の状態、排液の色、排液の量、バイタルサイン(特に体温・呼吸)
⑥バッグの設置場所
・ベッドサイドに設置する際は創部より低い位置にドレーンバックを設置し、排液の逆流を防ぎます。
・排液が逆流しないように、排液ボトルは立てた状態で使用します。
(2)排液の処理方法
①新たに吸引圧をかける場合
・集液ポートの板クランプを閉じ、排液ボトルの蓋が閉じられていることを確認します。
・吸引ボトルのゴム球をポンピングして、ボトル内のバルーンを膨張させます。
・板クランプを開くと吸引が開始されます。
②排液の方法
・板クランプで集液ポートを閉じます。
・排液口の蓋を開け、排液を排出します。
③排液後の吸引再開
・集液ポートの板クランプを閉じたまま、排液ボトルの蓋を閉じます。
・吸引ボトルのゴム球をポンピングし、バルーンを膨張させます。
・板クランプを開くと吸引を再開されます。
(3)アセスメント
・体温上昇、発汗、ドレーン刺入部痛の増強、排液の性状の変化などがある場合、感染兆候も併せて考えます。
⇒もし感染兆候を認めた場合、医師へ報告し適切な処置を行います。
・排液量の減少を認めた場合、患者さんの体位が影響していないか確認します。ドレーン先端の留置部位が高位置となるよう適宜体位変換を行い、体位変換後は排液量の変化の有無を確かめるようにしましょう。
・排液の性状から、出血の有無も確認します。一般的に、排液は血性から淡血性、そして淡黄色へと変化します。これが血性のまま経過する場合や淡血性でも量が減少しない場合などは出血を疑い、医師へ報告します。
(4)管理時の注意点
吸引器(排液ボトル+吸引ボトル)を傾けたり逆さにしたりすると、排液が吸引ボトル内に入り込み、吸引ボトルの性能に支障をきたします。そのため、吸引器はできるかぎり垂直に保ち、やむを得ず横にする場合は印刷面を上にします。
逆行性感染の可能性があるため、排液時には必ず板クランプを閉じます。
ウーンドドレナージチューブをYコネクターに接続する際は、チューブ先端を45°に切断し、滅菌生理食塩水で濡らしてから差し込むと容易に接続できます。