看護教育・制度
「看護教育・制度」の記事一覧
15件/823件

2006年から2009年に提供した医療安全情報
2010年にも類似事例が発生しています No.1 インスリン含量の誤認~バイアルの「100単位/mL」という表示を誤認し、過量投与に伴い低血糖をきたした事例~ 1件 医師は、インスリン静脈内持続投与の際、「ヒューマリンR50単位+生食50ml(1単位=1ml)1ml
2010/1/4
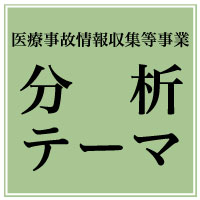
個別テーマについての検討状況|第15回報告書(2008年7月〜9月)④
【4】輸血療法に関連した医療事故 本報告書では、報告された医療事故事例のうち、「事故の概要」及び「事故の内容」のコード情報の中から「輸血」に関するコードを選択した事例、もしくは、それ以外で報告の内容が輸血療法に関連する事例について分析を行った。
2010/1/4

病理診断時の検体取り違え
病理診断において、検体取り違えの事例のうち、別の患者の検体と取り違えた事例が6件報告されています(集計期間:2007年1月1日~2011年2月28日、第22回報告書「個別のテーマの検討状況」に一部を掲載)。 病理診断において、別の患者の検体と取り違えた事例が報告
2010/1/4
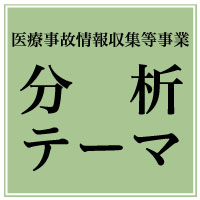
個別テーマについての検討状況|第15回報告書(2008年7月〜9月)③
【3】リハビリテーションに関連した医療事故 平成20年7月1日から平成20年9月30日の間に報告された医療事故事例のうち「発生場所」のコード情報の中から「機能訓練室」で選択されていた事例、及びそれ以外のコードの中から、その報告内容がリハビリテーションに関連する事例のう
2010/1/4

体位変換時の気管・気管切開チューブの偶発的な抜去
人工呼吸器を装着した患者の体位変換を行った際に、気管チューブまたは気管切開チューブが抜けた事例が23件報告されています(集計期間:2007年1月1日~2011年3月31日、第15回、第17回および第19回報告書「個別のテーマの検討状況」に一部を掲載)。 人工呼吸
2010/1/4
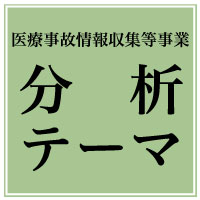
個別テーマについての検討状況|第15回報告書(2008年7月〜9月)
【1】 薬剤に関連した医療事故 平成20年7月1日から平成20年9月30日の間に報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例30件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 薬剤に関連した医療事故情報の概要は図表Ⅲ-2-1の通りである。
2010/1/4

画像診断報告書の確認不足
画像検査を行った際、画像診断報告書が報告されているにもかかわらず、内容を確認しなかったため、想定していなかった診断に気付かず、治療の遅れを生じた可能性のある事例が3件報告されています。(集計期間:2008年1月1日~2011年12月31日、第26回報告書「個別のテーマの
2010/1/4
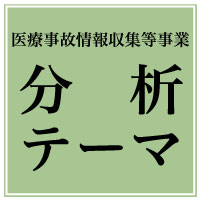
個別テーマについての検討状況|第14回報告書(2008年4月〜6月)④
【4】輸血療法に関連した医療事故 本報告書では、報告された医療事故事例のうち、「事故の概要」及び「事故の内容」のコード情報の中から「輸血」に関するコードを選択した事例、もしくは、それ以外で報告の内容が輸血療法に関連する事例について分析を行った。
2010/1/4

2010年に提供した医療安全情報
2010年1月~12月に医療安全情報No.38~No.49を毎月1回提供いたしました。今一度ご確認ください。 No.38 清潔野における注射器に準備された薬剤の取り違え 心臓カテーテル検査施行時、清潔野には識別情報のない2つのビーカーにヘパリ
2010/1/4
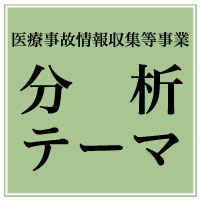
個別テーマについての検討状況|第16回報告書(2008年10月〜12月)
【1】 薬剤に関連した医療事故 平成20年10月1日から平成20年12月31日までに報告された医療事故のうち、薬剤に関連した事例43件について分析を行った。 (1)薬剤に関連した医療事故の現状 薬剤に関連した医療事故情報の概要は図表Ⅲ-2-1の通りである。
2010/1/4

ワルファリンカリウムの内服状況や凝固機能の把握不足
ワルファリンカリウムを使用していた患者の内服状況や凝固機能に関する情報の把握がなされていないため、観血的処置により出血が誘発された事例が5件報告されています(集計期間:2007年1月1日~2010年12月31日、第20回報告書「個別のテーマの検討状況」一部を掲載)。
2010/1/4
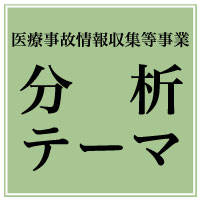
個別テーマについての検討状況|第13回報告書(2008年1月〜3月)⑤
【5】輸血療法に関連した医療事故 本報告書では、報告された医療事故事例のうち、「事故の概要」及び「事故の内容」のコード情報の中から「輸血」に関するコードを選択した事例、もしくは、それ以外で報告の内容が輸血療法に関連する事例について分析を行った。 (1)輸血療法
2010/1/4

抗リウマチ剤(メトトレキサート)の過剰投与に伴う骨髄抑制(第2報)
抗リウマチ剤(メトトレキサート)の過剰投与に伴う骨髄抑制を医療安全情報No.2(2007年1月)で情報提供いたしました。その後、再び類似の事例が2件報告されていますので、再度、情報提供いたします(集計期間:2006年10月1日~2010年6月30日)。 抗リウマ
2010/1/4
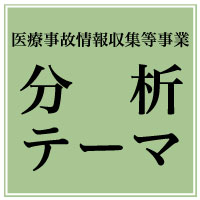
個別テーマについての検討状況|第14回報告書(2008年4月〜6月)②
【2】医療機器の使用に関連した医療事故 平成20年4月1日から平成20年6月30日の間に報告された医療機器に関連した医療事故のうち、人工呼吸器に関連した事例について分析を行った。 (1)人工呼吸器に関連した医療事故の現状 人工呼吸器に関連した医療事故情報は
2010/1/4

手術部位の左右の取り違え(第2報)
手術部位の左右の取り違えを医療安全情報No.8(2007年7月)で情報提供いたしました。その後、再び類似の事例が21件報告されていますので、再度、情報提供いたします(集計期間:2007年1月1日~2010年11月30日)。 手術部位の左右を取り違えた事例が再び報
2010/1/4


