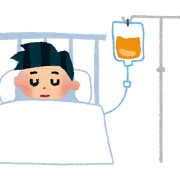IN/OUTバランスがわかると【術後管理】がわかる!
IN/OUTバランスがわかると【術後管理】がわかる!
- 公開日: 2015/2/26
IN/OUTバランスに関係の深い疾患の診断や治療について、輸液の側面からみていきましょう。
疾患と輸液の関係を具体的にみることによって、IN/OUTバランスについてさらに理解を深めましょう。
【関連記事】
●輸液ライン(点滴ライン)作り方 9ステップ
●サーフロー(R)の外筒・内筒を上手に進めるコツ
術後のIN/OUT管理の基本
侵襲期のIN/OUT管理
術後管理においては、INオーバーになることがほとんどです。手術内容によって、一概にいうことはできませんが、術中の不感蒸泄や出血に対して十分な輸液や輸血を行うためです。
術後の侵襲期は、傷を治すため、白血球からさまざまなサイトカインが放出され、リンパ球が炎症部位に誘導されます。
そのため、通常は閉じている血管壁の細胞にすき間ができ、水が血管外に逃げやすくなり、血管壁の透過性が亢進していきます。なおかつ、傷を治そうとしてアルブミンなどのタンパク質がたくさん使われ、血管内の水分がさらに少なくなってしまいます。
このメカニズムにより、水分が血管外に逃げる分、多めに水を入れようというのが、術中から術後、侵襲期までの考え方です。血管外に逃げた水分は、サードスペースに移動します。
【関連記事】
● サードスペースってなに?術後の輸液管理はナゼ難しい?
● 「周術期」への輸液療法|インアウトバランスから見る!
利尿期のIN/OUT管理――サードスペースとリフィリング
細胞内の細胞内液をファーストスペース、細胞外の細胞外液(血漿・間質液)をセカンドスペースといいますが、これらは本来あるべきところにある水です。
しかし、体が侵襲を受けると、いつもとは違う本来体内にはない場所に血漿や間質液が染み出していきます。その外に逃げた水分が貯留する部位を、サードスペースといいます。
侵襲期が過ぎ、血漿量が増え、タンパク質が体内で合成されるようになれば、傷が治り始めます。この時期になれば、サードスペースの水分が、細胞外液に戻ってきます。この現象を「リフィリング」と呼びます。
リフィリングが起こると、腎臓への血流も多くなり、尿の排泄が始まります。これが利尿期です。

図 体液とサードスペース
利尿期は、OUTオーバーになる時期です。余分な水分を尿として体外へ排出しなければ、肺うっ血になる可能性があります。肺うっ血や浮腫が起きると、呼吸困難になったり、傷が治りにくくなることもあります。
しっかりOUTオーバーにして、体液のバランスを正常の状態に戻していく必要があります。
【関連記事】
● 体液(体内水分)の役割
● 【体液量について】体液はどのようにバランスを保っているのか?
● 細胞外液と細胞内液とは?役割と輸液の目的
電解質管理がケアのカギ
術後のケアとしては、侵襲期・利尿期ともに、電解質のチェックが非常に重要です。
侵襲期には、輸液をしてもサードスペースに水が逃げるので、思ったほど体内に水分が残りません。例えば、大量に輸液しているのに、脱水状態で高ナトリウムになっていることもあります。
利尿期には、尿量の増加に伴って血清カリウム値が下がる場合があります。低カリウムになると不整脈を引き起こす危険性があります。
侵襲期と利尿期というのは、実際には、「今から利尿期だ」と、はっきり目に見えてわかるものではなく、例えばレントゲンを確認し、「うっ血が強い、水が戻ってきたかな」と見立てたりします。
利尿期は、術後2~3日後くらいという予測はありますが、微妙な見極めが求められます。また、侵襲が大きければ大きいほど、利尿期に戻るまでの期間は長く、利尿期に至らない場合もあります。
大きな手術や外傷、特に熱傷の場合は、INの量が通常の何倍も必要になるので、体液バランスが正常に戻るまで時間もかかります。
【関連記事】
● 1日当たりの最低必要尿量の基準ってどのくらい?
● 【IN/OUTバランス(水分出納)】1日当たりどのくらいの水と電解質量が必要?
● 電解質とは?身体のしくみと電解質異常
体重の変化を指標にする
体重測定は、さまざまな指標になります。手術前の体重を確認しておけば、たとえ侵襲期に点滴を多く入れても、利尿期に、「もとの体重は●kgだから、○kgまで絞っても大丈夫」「5kg増えているから、少しずつ利尿かな」など、ある程度の根拠をもって管理することができます。
術後の経管栄養と尿量測定
術後の栄養管理では、早期からの経管栄養が重視されています。消化管が使用することが可能ならば、輸液よりも経管栄養を行うことのほうが生理的です。
腸の中に栄養を入れておくことは、腸の粘膜を萎縮させず、腸内細菌のバランスや、消化管の免疫賦活化につながっていきます。
消化管を使わなければ、バクテリアル・トランスロケーション(BacterialTranslocation;BT)といって、腸内細菌が腸の粘膜を通過し、体内に移行してしまい、敗血症の原因となることもあります。
また、術後は、尿量測定をこまめに行うことが大切です。術後急性期には輸液負荷を行うことも多いですが、肺水腫を起こさないように、血管内のボリュームや電解質を細かく評価しながら、輸液量の調節を行います。
水・電解質が苦手なら、心電図と一緒に勉強しよう
水・電解質は、看護師が苦手意識をもっているものの1つだと思います。よく知らなくてもなんとかなるし、難しいから勉強したくないと、いつまでも苦手意識を放置している人も多いと思います。私自身も苦手でした。
この苦手意識を克服する勉強法はいろいろあると思いますが、水・電解質がわかりにくいのは、体の中の見えない仕組みを扱っているということが大きいので、目に見える何かと関連づけて一緒に考えることをオススメします。
例えば、一番身近な見えるものというと心電図です。
私の場合、CCUで先輩に心電図と一緒に勉強するという方法を教えてもらったことで、グッとわかるようになってきました。
心電図は、電解質の異常によって、すぐに形が変わり変化をしていきます。特にカリウム(K)は、不整脈を起こすことでも有名です。
それ以外にも、カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)もあります。これらの目に見えないものを目に見える心電図にリンクさせることで印象も強くなり、覚えやすくなると思います。
「高カリウム血症は気持ち(K)が上がるからテンション(T波)も上がる!」などとこじつけて覚えたりもしました。このように、自分なりに覚えやすくすることも苦手意識を克服する秘訣の1つです。

【関連記事】
●電解質とは?身体のしくみと電解質異常
●低カリウム血症・高カリウム血症|原因・症状・治療ポイント
●輸液管理で見逃しちゃいけないポイントは?
(『ナース専科マガジン』2014年8月号から改変引用)