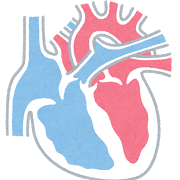 第4回<読み方・対応編②>上室性期外収縮(SVPC)または心房性期外収縮(PAC)
第4回<読み方・対応編②>上室性期外収縮(SVPC)または心房性期外収縮(PAC)
- 公開日: 2016/9/30
(1)心電図波形の特徴
みなさんは、期外収縮という言葉に馴染みがあるでしょうか。
期外収縮とは、次に出現する正常な間隔の波形よりも早く現れるものを指し、別名を早期収縮といいます。今回はこの期外収縮について、QRSの幅から上室性(心房性)を見分ける方法をお話しします。
まず、期外収縮は幅の広いQRS波(3メモリ以上)と幅の狭いQRS波(3メモリ未満:多くは2メモリ)の2つがあります。後者が洞調律のP-QRS波と違うタイミング(期外)で発生する場合、上室性期外収縮(SVPC)もしくは心房性期外収縮(PAC)といいます(図1)。

図1 心房性期外収縮(PAC)の心電図波形
不整脈の勉強をしていると、よく上室性や心房性という言葉が出てきます。ここでも出てきました。正確には意味合いが違うのですが、混乱を避けるため、上室性≒心房性と覚えておいて差し支えありません。
また、この不整脈は心房の中で洞房結節以外のところから発生する不整脈のため、P波の形が違ってきます(P波は、電気を発生した心房のある場所から左房と右房に電気が行き渡ったときにみられる波形であり、P波が発生した場所によって少しずつ形が変わります)。
上室性期外収縮と似たような波形となるものに、洞性不整脈があります。洞房結節は、通常一定のタイミングで電気刺激を発していますが、まれにタイミングを逸することがあります。この場合、同じ場所からの電気刺激なのでP波の形に変化はみられません。これを洞性不整脈といいます(図2)。

図2 洞性不整脈の心電図波形
先ほどの心房性期外収縮のP波と違い、洞性不整脈ではRR間隔がそろっていないのに、P波の形は同じですよね!
上室性期外収縮と洞性不整脈の違いがわかりましたか?
(2)どんな病態?
心臓は普通、洞房結節から発生する電気刺激が刺激伝導系に伝わって、房室結節、ヒス束、右脚および左脚からプルキンエ線維に伝わり、心室が収縮します。しかし、上室性期外収縮では、洞房結節とは違うところから電気刺激が発生するので(図3)、P波の形が異なりますが、この電気刺激は洞房結節を経由して心室に刺激が伝わるので、QRS波は正常のQRS波と同じ形になります。

図3 上室性期外収縮
注)☆が電気刺激の発生場所
(3)緊急度と看護師としての対応
上室性期外収縮(または心房性期外収縮)は、致命的になることはまれな不整脈です。患者さんがもし症状を訴えれば、内服薬を投与することもありますが、基本的は経過観察で様子をみます。
また、上室性期外収縮が頻繁に発生するような場合は、将来的に心房細動や心房粗動に移行する可能性があるので注意が必要です。
患者さんが特に症状を訴えなければ、基本的にドクターコールは不要です。
関連記事
* 心房性(上室性)不整脈の分類と波形の特徴を知ろう
* 心室性不整脈の分類と波形の特徴
* <読み方・対応編⑥>心室期外収縮 (PVC)








