記事一覧
15件/4076件
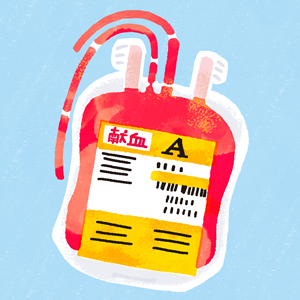
輸血の手順|血液製剤の準備、実施の手順と注意点
輸血事故を防止するための重要なポイント ●血液製剤の準備は一患者さん毎に実施します。 ●照合・確認は、投与開始までに3回行います。 1回目:血液製剤の受け渡し(出庫時)…輸血部門において 2回目:輸血準備時…ナースステーションにおいて 3回目:輸血実施時…ベッドサイ

呼吸困難感に対する看護計画|COPDの患者さん
COPDに伴う呼吸困難感に関する看護計画 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は有害物質を長期に吸入することで生じた肺の炎症性疾患で、喀痰の増加、気道の狭窄、肺胞の破壊などによって呼吸困難感を生じて、呼吸状態だけでなく日常生活に支障が出るため、それらに対する看護計画が必要と考えら

不安に対する看護計画|初期の認知症と告知を受けた患者さん
初期の認知症と告知を受けて今後に不安を感じている患者さん 認知症は血管性、アルツハイマー型、レヴィー小体型など同じ認知症であっても原因、病状の進行度合い、治療方法に違いがあるためそれを踏まえた看護計画を考えました。 POINT観察計画 O-P 認知症の程度を客観的に

日本精神神経学会 第17回記者勉強会|コロナ禍における自殺予防
2022年1月28日、日本精神神経学会による第17回記者勉強会がオンラインで開催されました。テーマは「コロナ禍における自殺予防について」です。「自殺とメディア報道」に焦点を当て、札幌医科大学医学部神経精神医学講座の河西千秋先生と、筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学

脱水の看護計画|脱水で入院してきた高齢の患者さん
脱水で入院してきた高齢の患者さん 脱水には高張性、等張性、低張性の3つに分類でき、それぞれ異なる病態を示します。その発生機序を推測しながら情報収集を行い、適切に介入できるように立案しました。 POINT観察計画 O-P 脱水の程度を知るための情報(口渇感やツルゴール

令和3年度 がん対策推進企業アクション 統括セミナー
2022年3月4日(金)、「令和3年度 がん対策推進企業アクション 統括セミナー」が開催されました。今回は、厚生労働省健康局 がん・疾病対策課課長 中谷裕貴子さん、東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座特任教授 がん対策推進企業アクションアドバイザリーボード議長 中川恵

アセスメントと看護
アセスメントとは 英語のassessmentは、評価という意味になりますが、臨床で看護師が行うアセスメントとは情報を収集し、整理・吟味し、判断する過程のことをいいます。情報の収集では問診で、既往歴、家族歴、服用している薬剤などといった情報とともに、息苦しい、胸が痛い、だる

特定行為に係る看護師の研修制度~行政の動き~
2022年2月16日(水)、「地域医療を支える特定行為研修修了者の活動と期待」をテーマに、「2021年度 特定行為研修シンポジウム」が開催されました。今回は、厚生労働省医政局看護課 看護サービス推進室の講演を中心にレポートします。 医療現場で高まるニーズ 看護師の特

麻酔器を使用したマスク換気|画像で手順を解説
今回は麻酔器を使用したマスク換気方法を解説します。日頃、麻酔科医が行っている気道確保方法を知ることで、麻酔科医の処置介助や急変時の対応など、いざというときに役立ててもらえたら幸いです。麻酔器を使用するには、麻酔器の基本構造を知っていること、麻酔器の始業点検が済んでいることが前

地震が起きていないときにやっておきたい手術室の地震対策
1.日本における災害 日本は災害大国と呼ばれ、豪雨による被害は毎年ニュースで流れています。特に大規模な被害を出した災害としては、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、大津波、原子力発電所事故などが挙げられると思います。その他にも洪水や噴火、豪雪など、多く

片頭痛治療の最新知識|たかが頭痛と思わないで! 頭痛フリーで充実した看護師ライフを
看護師はじめ女性に多い片頭痛。命にかかわらないので軽視されがちですが、実はきちんと治療することが大切なんです。きちんと治療をしないと痛み止めの飲み過ぎによる頭痛に発展して大変な目にあうことも……。今回は頭痛でお悩みの方だけでなく、医療者として知っておくべき頭痛に関する知識を、

不安定狭心症のBraunwald分類(ブラウンワルド分類)
不安定狭心症のBraunwald分類は何を判断するもの? 不安定狭心症のBraunwald分類は、不安定型狭心症の重症度を判定するために、1989年に提唱されたスケールです。このスケールは、臨床経過と病態の2つの要素から重症度を9つに分類し、さらに治療の状況によって重症度を細

急性疼痛に対する看護計画|肺がんの術後の患者さん
肺がん術後の急性疼痛に対する看護計画 手術に伴う侵襲や胸腔ドレーン挿入による侵襲で患者さんの安楽が障害されるリスクを考慮して計画を立案しました。 POINT観察計画 O-P 患者さんの状態を把握するための情報を集める。肺がんの術後のため、留置しているドレーンの観察と

低栄養に対する看護計画|COPDの患者さん
COPDに伴う低栄養に関する看護計画 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は有害物質を長期に吸入曝露することで生じる肺の炎症性疾患です。それによって呼吸困難感を生じさせ、食思不振をまねき低栄養を引き起こすことが考えられるため、それを踏まえた計画を立案しました。 POINT観察

セルフケア不足の看護計画|呼吸困難で清潔を保持できないケース
呼吸困難によるセルフケア不足で清潔を保持できない患者さんの看護計画 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患で、呼吸困難感を生じさせます。症状が進行するにつれて日常生活に支障が出てくる可能性を考慮して計画を立案しました。 P


