リハビリテーション科
リハビリテーション科関連の記事の一覧です。
リハビリテーション科では専門医が診察を行い、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの各専門職にリハビリの指示を出します。リハビリ各専門職が連携して介入することで、多角的なアプローチが可能となります。
看護師は、退院後の生活を見据え、患者さんができることを増やしていけるよう、入院生活のサポートをすることが必要です。また、スムーズなリハビリにつながるよう、それぞれ専門職との橋渡し的な役割も担います。患者さんの退院後の生活のため、必要に応じてソーシャルワーカーと連携することもあります。
リハビリテーション科 記事カテゴリ
「リハビリテーション科」の記事一覧
15件/32件

末梢神経損傷の分類(Seddon分類、Sunderland分類)
末梢神経損傷の分類は何を判断するもの? 末梢神経損傷の分類(Seddon分類、Sunderland分類)とは、末梢神経損傷の重症度を評価するためのスケールです。 神経系は中枢神経系と末梢神経系に大別されます。中枢神経系は脳と脊髄により営まれ、末梢神経系から送られてくる

変形性股関節症で人工股関節節置換術を受けた患者さんに関する看護計画
変形性股関節症で人工股関節節置換術を受けた患者さんに関する看護計画 変形性股関節症は、何らかの要因あるいは加齢に伴う変化によって股関節が変形することで痛みが出現して日常生活に支障をきたす疾患です。治療には保存療法や手術療法がありますが、今回は変形性股関節症で人工股関節置換

疼痛でリハビリが進まない患者さんに関する看護計画|膵頭十二指腸切除後の患者さん
膵頭十二指腸切除術後の疼痛でリハビリが進まない患者さんに関する看護計画 膵頭部に生じた悪性腫瘍は切除可能である場合は膵頭部、十二指腸、胆管、胆嚢を含めて切除する膵頭十二指腸切除術が行われます。状況に応じて胃や血管も切除が検討され、複数箇所におよび切除範囲や手術侵襲から患者
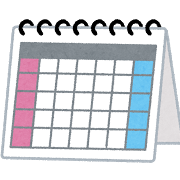
日本リハビリテーション看護学会 第36回学術大会【参加登録者募集】
日本リハビリテーション看護学会 第36回学術大会|ご参加のお願い NPO法人日本リハビリテーション看護学会は、第 36 回学術大会(大会長:原 三紀子 東邦大学看護学部)を開催いたします。 詳細は日本リハビリテーション看護学会 第36回学術大会のページをご覧くださ

長期臥床により筋力が低下した患者さんへの看護計画
脳梗塞による長期臥床で筋力が低下した患者さんに対する看護計画 脳梗塞は何らかの原因で脳の血管が狭窄・閉塞して虚血が起こり、その血管が支配する領域の脳組織が壊死した状態です。今回は脳梗塞で壊死した領域によっては上肢や下肢に麻痺が生じて長期臥床になり筋力低下が起こった患者さん

脳卒中機能障害評価法(SIAS、サイアス)
SIASは何を判断するもの? 脳卒中機能障害評価法(Stroke Impairment Assessment Set:SIAS)は、脳卒中によって身体機能がどの程度ダメージを受けているかを定量的に評価するスケールです。脳卒中患者さんの予後を予測したり、リハビリテーションによる

筋力低下に対する看護計画|長期臥床で筋力が低下した患者さん
長期臥床による筋力低下に関する看護計画 筋力低下は1つあるいは複数の筋肉の力が低下することであり、運動ニューロンの障害や筋・骨格系の機能障害などさまざまな要因で生じます。今回は臨床で遭遇しやすい長期間の臥床によって生じる筋力低下に関して看護計画を立案してみました。

廃用症候群の看護計画|肺がん術後の予防が必要な患者さん
肺がんの術後で廃用症候群予防の内容を含む看護計画 廃用症候群とは「安静や活動低下に伴う身体機能や精神機能の低下」であり、肺がん術後の呼吸機能低下、創痛や無気肺など術後特有の症状に対する介入を念頭に計画を考えます。 POINT観察計画 O-P 廃用症候群の予防は早期離

Barthel Index(バーセルインデックス)
Barthel Indexは何を判断するもの? Barthel Indexとは、「食事」「移乗」「整容」「トイレ動作」「入浴」「歩行」「階段昇降」「着替え」「排便コントロール」「排尿コントロール」という10の基本的な日常生活の能力を点数化して、ADL(日常生活動作)の評価を行

機能的自立度評価法(functional independence measure:FIM)
FIMは何を判断するもの? 機能的自立度評価法(functional independence measure:FIM)とは、1983年に提唱されたADL(身の回りの必要最低限な活動)の評価方法の一つです。主に介助の必要度合いに着目した評価を簡便に行うことができ、介護負担度の

国際生活機能分類―国際障害分類改訂版―
1. この分類は何を判断するもの? 国際生活機能分類は、人間の生活機能と障害の程度を示す分類方法です。病気や加齢による障害の程度を示す分類方法はこれまでにも多くのものが存在していました。しかし、国際生活機能分類は障害の程度を「マイナス面」から捉える従来の評価方法と
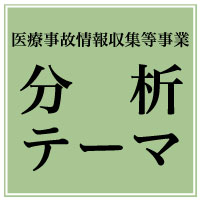
個別テーマについての検討状況|第12回報告書(2007年10月〜12月)④
【4】リハビリテーションに関連した医療事故 平成19年1月1日から平成19年12月31日の間に報告された医療事故事例のうち「発生場所」のコード情報の中から「機能訓練室」で選択されていた事例、及びそれ以外のコードの中から、その報告内容がリハビリテーションに関連する事

呼吸器合併症のリスクが高い患者さんへの対応
今回は食道がんの症例について解説します。 ▼術前・術後の看護について、まとめて読むならコチラ 術前・術後の看護(検査・リハビリテーション・合併症予防など) 事例 呼吸器合併症のリスクが高い患者さん 66歳男性。食べ物のつかえ感が認められ

【腹部に術創がある患者さんの術後リハ】患者さんの背景から必要なことを見極める
今回は直腸がんに伴いストマ造設術を行った患者さんについて解説いたします。症例は58歳男性、現在仕事をしており直腸がんと診断され人工肛門造設術を行う患者さんについて考えていきましょう。 ▼術前・術後の看護について、まとめて読むならコチラ 術前・術後の看護(

【胸部に術創がある患者さんの術後リハ】術後のリスクを想定して行う
開胸手術の代表例として肺がんなどの呼吸器疾患、心臓外科、食道がん手術などが挙げられます。今回は肺がんの患者さんについて解説します。 ▼術前・術後の看護について、まとめて読むならコチラ 術前・術後の看護(検査・リハビリテーション・合併症予防など)


