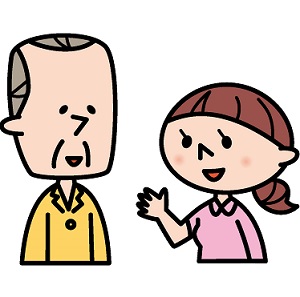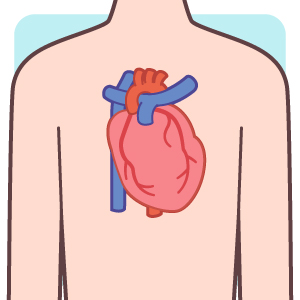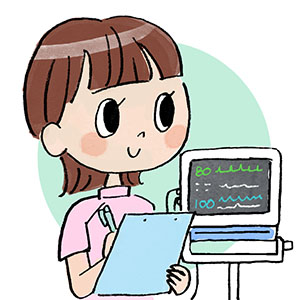 心エコー検査の看護|目的、種類、検査結果の見方など
心エコー検査の看護|目的、種類、検査結果の見方など
- 公開日: 2021/1/14
【関連記事】
● 「心不全」への輸液療法|インアウトバランスから見る!
● 心不全による消化器症状(嘔吐、便秘など)とは?
心臓超音波検査(心エコー検査)とは
心臓超音波検査(以下、心エコー検査)は、心臓近くの胸壁に超音波をあててその反射波を画像化し、心臓の状態を調べる検査です。心エコー検査とも呼ばれます。非侵襲的かつ簡便に心臓の状態、働きを判定できることから、日常診療の場で広く用いられています。
心エコー検査の目的
①心腔内の各部位の形態・大きさを観察します。
②心臓の各部分の動きを観察し、心機能を評価します。
③心腔内の圧や血流を推測し、血行動態を評価します。
心エコー検査の種類と特徴
心エコー検査の種類と特徴は表1のとおりです。目的の①②では心臓の形態・動きをみる心エコー法が、③では血液の流れを可視化するドプラエコー法が用いられます。
表1 心エコー検査の種類・目的・特徴| 種類 | 目的・特徴 | |
|---|---|---|
| 心エコー法 | 断層エコー法 | ・心臓の形態および動態を二次元で表示 |
| Mモード法 | ・超音波ビーム上にある心臓内構造物の動態を表示 ・縦軸はプローブからの距離(観測点の深さ)、横軸は時間を示す ・時間分解能、距離分解能に優れる | |
| ドプラエコー法 | カラードプラ法 | ・血流の方向や速度をカラーで表示 ・定量評価には不向き |
| パルスドプラ法(PW) | ・特定の領域における血流速度の計測が可能 | |
| 連続波ドプラ法(CW) | ・血流の最大速度の計測が可能 ・距離分解能に欠け、血流測定位置の特定はできない | |
心エコー検査の正常値、検査結果の見方、検査結果からわかること
心エコーは、心機能や血行動態の把握、原因疾患の検索、治療効果の判定において中心的な役割を果たしています。表2をはじめとするさまざまな項目がありますが、患者さんの病態を評価・把握するために、特に重要な項目について取り上げます。
表2 心エコー検査の正常値
文献1)、2)を参考に作成
見る項目⇒左室拡張末期径(LVDd)、左室収縮末期径(LVDs)、左室駆出率(LVEF)
わかること⇒左心室の大きさと収縮能(心臓にかかっている負担)
左心室の大きさは左室拡張末期径(left ventricular end-diastolic diameter:LVDd)や左室収縮末期径(left ventricular end-systolic diameter:LVDs)、左心室の収縮能は左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)を見て評価します。
左心室の大きさの変化から、心臓にかかっている負担を評価できます。心臓は最大の役割である「全身に必要な酸素と栄養を届ける」ために、心拍出量を維持しようと努力します。しかし、心臓の収縮力が落ちてしまい維持が難しくなると、心臓を大きくすることでカバーしようとします(フランクスターリングの法則)。
収縮力が低下していることが原因で、咳、息切れ、浮腫、食欲低下といった心不全症状が出ているような状態では、心室は大きくなっています。ここでの心室の大きさとは、左心室が拡張したときの大きさ(LVDd)を指します。正常値と比較するのではなく、心不全症状が治まっているときのサイズと比較しましょう。
治療効果が得られれば、左心室は症状がなかった頃の大きさに戻る可能性がありますが、それとは別に、弁膜症などに伴う長年の圧・量負荷によって経時的に心臓のサイズが大きく変化してきている患者さんもいます。一時点での心エコー結果を見るのではなく、経時的に心臓の変化を捉えることは、患者さんの病気の歴史を捉えるうえでも重要です。