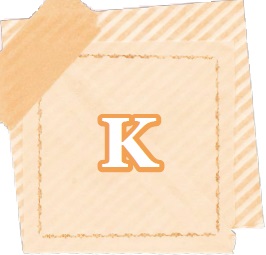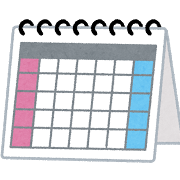看護過程|アセスメント、看護診断、計画立案、看護の実施、評価
看護過程|アセスメント、看護診断、計画立案、看護の実施、評価
- 公開日: 2022/1/29
看護過程とは
看護過程とは看護師が看護を行うプロセスのことをいいます。看護過程は、アセスメント、看護診断、看護計画、看護の実施、評価の5つの要素から成り立っています。この5つの要素はそれぞれが関連し合いながらつながっています。これらの要素は一度実施したら終わりというわけではなく、ケアを行いながら患者さんの状態をアセスメントし、看護計画を考えていくというように繰り返し行っていきます。

看護過程の5つの要素
看護過程には前述したように5つの要素があります。
アセスメント
アセスメントとは情報を収集し、整理・吟味し、判断する過程のことをいいます。ケアを行う前には患者さんの状態を把握するためアセスメントを行い、ケアを実施した後はケアによって患者さんの状態がどう変わったのか、変わらなかったのかを確認するためにアセスメントを行います。看護を行う上で、アセスメントは欠かすことができないものといえます。
情報の収集では、客観的情報と主観的情報を集めます。集めた情報と自身がもっている知識を合わせて情報を整理し、どのようなケアが必要なのかを導き出していきます。
客観的情報 フィジカルアセスメントで得た患者さんの状態、既往歴、検査データなど 収集する情報には患者さんの個人情報なども含まれます。収集した情報については、個人情報の保護、守秘義務の遵守について細心の注意を払う必要があります。看護師の行動指針として日本看護協会は「看護職の倫理綱領」にまとめています。 【関連記事】 アセスメントで得た情報をもとに、治療や療養の際に患者さんが抱えるであろう(抱えている)問題にはどんなものがあるかを抽出します。抽出した問題に、看護診断名をつけます。看護診断名は、NANDA-Iの看護診断やカルペニートの看護診断などを用い、表現を統一します。現在は、NANDA-Iの看護診断が多くの施設で使用されています。 【関連記事】 抽出した看護問題(看護診断)に対して、問題解決の目標と観察計画(O-P)、援助計画(T-P)、教育計画(E-P)を考えます。看護計画として立てたものは、患者さんに同意を得ます。 【関連記事】 看護計画で立案したケアを実施していきます。ケアを行ったことによって変わったことや変わらなかったことなどといったデータも収集します。また、患者さんの状態を見ながらケアを行い、必要があれば計画を修正していきます。 ケアを行ったことで、目標としていた成果が得られたのか、到達できていない場合は継続してどのようなケアの提供が必要かを考えます。必要に応じて新たに患者さんのデータを収集し、ケア実施後の状況と合わせてアセスメントしていきます。 看護理論とは、体系的に看護の考え方や見方をまとめたものになります。情報収集の指針となり、看護学生や新人看護師は看護理論を活用することでよりよい看護を実践することができるといわれています。 看護理論には、ヘンダーソンの14の基本的ニード(欲求)、ゴードンの11の機能的健康パターン、ロイの適応モデルなどがあります。 患者さんが自立して生活するために必要なことを14の項目として挙げています。ヘンダーソンの理論を用いる際は、この14の要素に沿ってアセスメントしていきます。
主観的情報 問診で得られた情報 例:胸が苦しい など
●アセスメントがうまくいく3つのPoint(情報収集など)
●第24回 看護師が知っておきたいアセスメントのコツ
●アセスメントが書けないと看護計画がずれる??
●フィジカルアセスメント看護診断
●看護問題リスト・看護計画の書き方|看護記録書き方のポイント2計画立案
●看護計画に個別性を出すには
●看護問題リスト・看護計画の書き方|看護記録書き方のポイント2看護の実施
評価
看護過程の展開と看護理論
ヘンダーソンの14の基本的ニード
1.正常に呼吸する 2.適切に飲食する 3.身体の老廃物を排泄する 4.活動し、また望ましい姿勢をとる 5.睡眠と休息をとる 6.適切な衣類を選び、来たり脱いだりする 7.衣類の調節と環境の調節により他院を生理的範囲内に維持する 8.身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する 9.環境のさまざまな危険を避け、また他者を傷害しないようにする 10.環境、ニーズ、不安、恐怖、自分の意見などを表現し、他者と交流する 11.自分の信仰に従って礼拝する 12.達成感のある仕事をする 13.遊ぶ、または、さまざまなレクリエーションに参加する 14.正常な成長発達および健康な生活が送れるような学習や、その方法を発見し、好奇心を満たす。または、利用できる保健医療設備・施設を活用する
ゴードンの11の機能的健康パターン
ゴードンは11個の領域に分けて患者さんをアセスメントすることを提唱しています。患者さんの情報を11に分けて整理し、看護問題を抽出していく際に役立てます。
| 1.健康知覚-健康管理 |
| 2.栄養-代謝 |
| 3.排泄 |
| 4.活動-運動 |
| 5.睡眠-休息 |
| 6.認知-知覚 |
| 7.自己知覚-自己概念 |
| 8.役割-関係 |
| 9.セクシュアリティ-生殖 |
| 10.コーピング-ストレス耐性 |
| 11.価値-信念 |