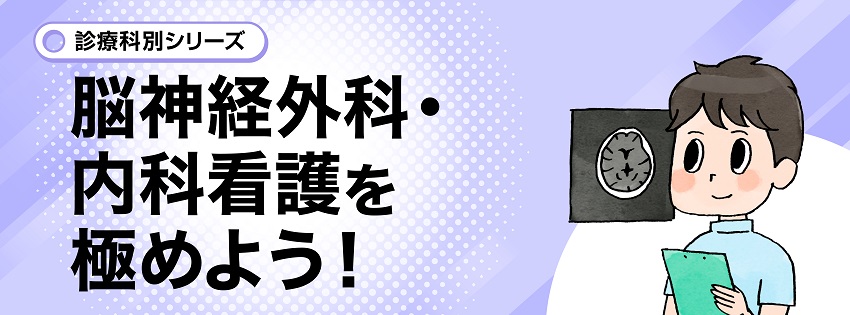脳神経外科
脳神経外科関連の記事の一覧です。
脳神経外科 記事カテゴリ
「脳神経外科」の記事一覧
15件/62件

脳梗塞の再発予防に対する看護計画
脳梗塞の再発予防に対する看護計画 脳梗塞は何らかの原因で脳の血管が狭窄・閉塞が起こり、それ以降で虚血が生じてその血管が支配する領域の脳組織が壊死した状態です。危険因子には高血圧、高脂血症、糖尿病などさまざまなものが挙げられ、再発が起こりやすいと言われています。再発を予防す
2023/1/30

ボディイメージの混乱に対する看護計画|脳梗塞による麻痺がある患者さん
脳梗塞による麻痺でボディイメージの混乱に対する看護計画 脳梗塞は何らかの原因で脳の血管が狭窄・閉塞して虚血が起こり、その血管が支配する領域の脳組織が壊死した状態です。壊死した領域によっては上肢や下肢に麻痺が生じるため看護計画を立案しました。 POINT観察計画 O-
2022/12/30

抗血栓薬を使用している患者さんの注意点
10月の脳卒中月間に合わせ、アストラゼネカが「抗血栓薬を服用中の患者さんに知っておいてほしいこと」と題するメディアセミナーを開催しました。本セミナーに登壇された国立病院機構九州医療センター 脳血管・神経内科、臨床研究センター臨床研究推進部長の矢坂正弘先生と、国際医療福祉大学医
2022/12/21

セルフケア不足に対する看護計画|脳梗塞で片麻痺がある患者さん
脳梗塞による片麻痺に関連したセルフケア不足の看護計画 脳血管障害(脳卒中)には、脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。そのうち脳梗塞は何らかの原因で、脳の血管が狭窄・閉塞し、虚血が起こって、その血管が支配する領域の脳組織が壊死した状態です
2022/9/29

ASIA分類(エイシア分類)
ASIA分類は何を判断するもの? 「脊髄損傷の神経学的分類のための国際基準(ISNCSCI)」は、一般的にASIA分類と呼ばれ、主に急性期の脊髄損傷の重症度を評価するためのスケールです。 脊髄損傷の重症度を判断するためのスケールとして最もよく知られているのはFra
2022/8/1

脳梗塞の看護計画|rt-PA静注療法を実施後患者さん
脳梗塞に対してrt-PA静注療法を実施後の看護計画 脳血管障害(脳卒中)には、脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。そのうちの脳梗塞は何らかの原因で、脳の血管が狭窄・閉塞し、虚血が起こって、その血管が支配する領域の脳組織が壊死した状態にな
2022/7/25

非効果的健康管理に関する看護計画|くも膜下出血の患者さん
くも膜下出血の患者さんの非効果的健康管理に関する看護計画 くも膜下出血は脳血管障害(脳卒中)の一つであり、主に動脈瘤という血管の瘤が破裂して起こります。そして、急速な身体変化が生じた後の生活習慣の獲得や再発予防の為に退院後の生活において、食事や運動・休息、喫煙、飲酒といっ
2022/7/23

脳卒中機能障害評価法(SIAS、サイアス)
SIASは何を判断するもの? 脳卒中機能障害評価法(Stroke Impairment Assessment Set:SIAS)は、脳卒中によって身体機能がどの程度ダメージを受けているかを定量的に評価するスケールです。脳卒中患者さんの予後を予測したり、リハビリテーションによる
2022/7/13

頭蓋内圧亢進の看護|原因・メカニズム、観察項目、ケア、注意点
頭蓋内圧亢進とは 頭蓋内の容積は、脳実質(87%)、脳血液(9%)、髄液(4%)で構成され1)、外気圧に対して一定の圧を保っています。この頭蓋内の圧のことを頭蓋内圧と呼びます。頭蓋内圧は、正常では5~10mmHg程度ですが、何らかの原因で15mmHg以上の状態が持続するこ
2022/7/9

脳卒中の再発予防教育(退院指導)
再発予防教育とは 脳卒中は再発を繰り返す疾患です。これは高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満、腎機能障害、不整脈などとの関連・影響が大きいためです。再発を予防するには、退院後の生活において、食事や運動・休息、喫煙、飲酒、ストレスコントロールといった生活習慣の見直しと是正が課題とな
2022/5/23

頭部CT検査の看護|種類、目的、検査前・検査後の観察項目、注意点
頭部CT検査とは 頭部CT検査とは、頭部にX線を連続的に照射し、X線の吸収値の差をコンピュータ処理することで、頭蓋内の断層画像を得る検査方法です。撮影時間が短く簡便に行えるため、緊急時やスクリーニングに活用でき、広く普及したデジタル画像撮影法といえます。 頭部CT検査
2022/4/29

片頭痛治療の最新知識|たかが頭痛と思わないで! 頭痛フリーで充実した看護師ライフを
看護師はじめ女性に多い片頭痛。命にかかわらないので軽視されがちですが、実はきちんと治療することが大切なんです。きちんと治療をしないと痛み止めの飲み過ぎによる頭痛に発展して大変な目にあうことも……。今回は頭痛でお悩みの方だけでなく、医療者として知っておくべき頭痛に関する知識を、
2022/3/23

脳血管内治療(血管回収療法)の看護|術前術後の観察項目、注意点、合併症
脳血管内治療とは 脳血管内治療とは、血管造影のもと、大腿動脈や上腕動脈などからカテーテルを挿入し、血管内から病変を治療する方法です。 脳血管内治療には、狭窄あるいは閉塞した血管を拡張させる血行再建術と、出血の原因となる血管奇形や動脈瘤をコイルや液体閉塞物質を用いて閉塞
2021/12/3

シャント術(水頭症の治療)の看護|術前・術後の観察項目・注意点、合併症
シャント術とは シャント術は、髄液還流障害による水頭症に対して行われます。 ここで、水頭症について理解しておきましょう。水頭症とは、くも膜下出血や脳内出血などの脳血管疾患、脳腫瘍、頭部外傷、特発性(原因不明)、先天奇形などにより髄液の循環が障害され、髄液が脳室やくも膜
2021/10/19

シンシナティ病院前脳卒中スケール(Cincinnati Prehospital Stroke Scale:CPSS)
CPSSは何を判断するもの? CPSSは、脳卒中の可能性を判定するためのスケールです。 脳卒中の可能性を判定するためのスケールとしては、CPSSのほかにロサンゼルス病院前脳卒中スクリーン(Los Angeles Prehospital Stroke Screen:LA
2021/9/29