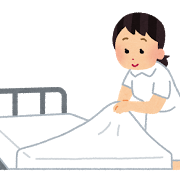 褥瘡とは?褥瘡の看護ケア|原因と分類、評価・予防・治療など
褥瘡とは?褥瘡の看護ケア|原因と分類、評価・予防・治療など
- 公開日: 2016/9/13
- 更新日: 2024/2/29
「褥瘡」に関する記事をまとめました。
*2017年1月12日改訂
*2024年2月29日
褥瘡とは?
褥瘡の定義
褥瘡とは、日本褥瘡学会では「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止される。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害に陥り褥瘡となる」と定義されています。
褥瘡発生には「外力(体位変換や寝具)」「栄養状態(病的骨突出や浮腫)」「湿潤(多汗や失禁)」「自立(ADL低下や関節拘縮)」の4つの要素が大きくかかわっています。
褥瘡発生のメカニズム
褥瘡ができるメカニズムには、発生に直接結びつく、身体の一部にかかる過剰な圧力・応力(静的外力)と、身体がほかの力によって動かされることによって生じる外力(動的外力)の2つがかかわってきます。これら2つの外力が皮膚の同じ部位に長時間加わることで、褥瘡は発生します。
【褥瘡発生のメカニズム記事】
・褥瘡の発生要因・メカニズムをおさらいしよう!
褥瘡の好発部位
褥瘡の好発部位は、骨の突出部です。仰臥位では仙骨部、踵骨部、後頭部に注意が必要で、側臥位では大転子部に発生しやくなります。座位や車いすの場合は坐骨結節部や尾骨部にもみられます。その人が、普段どのような姿勢を取っているのかを確認して、予防していくことが大切です。
図 褥瘡の好発部位

褥瘡のアセスメント
患者さんが入院してきた際には、まず、褥瘡のリスクアセスメントを行います。リスクがあれば、それに沿って看護計画を立てていきます。発赤がある、すでに褥瘡がある場合には、スケールを用いてアセスメントし、必要なケアを行っていきます。褥瘡のリスクや褥瘡そのものをアセスメントするためのスケールには、さまざまなものがあります。何をアセスメントするためのスケールなのかを知っておくことも大切です。
褥瘡の発生リスクを確認する(褥瘡に関する危険因子評価表、ブレーデンスケール、OHスケール、K式スケール)
褥瘡予防は、まず発生リスクを見極めることから始まります。褥瘡のリスクアセスメント・ツールの代表的なものには、褥瘡に関する危険因子評価表、ブレーデンスケール、OHスケール、K式スケールがあります。それぞれのスケールの特徴を知って、自施設にあったものを選択するとよいでしょう。
【リスクアセスメントに関する記事】
・褥瘡予防の第一歩! リスクアセスメント・スケールの使い方
・ブレーデンスケール・OHスケールとは?リスクをアセスメント!
・厚生労働省危険因子評価表
褥瘡の発生のアセスメントと分類
褥瘡発生の初期は、多くの場合、発赤がみられます。ただし、発赤すべてが褥瘡とは限りません。まずは、ガラス板圧診法や指押し法を用いて、褥瘡かどうかを判定していきます。
透明プラスチック板や示指で軽く3秒ほど圧迫し離したあとに、白っぽくなる場合は褥瘡ではないと判定できます。圧迫したあとも発赤が見られる場合は、褥瘡と判定します。
【関連記事】
・発赤とは? 発赤と褥瘡を見分ける『ガラス板圧診法』『指押し法』って?
褥瘡の分類でよく用いられるのが、NPUAPによる褥瘡の分類です。この分類は褥瘡をステージI〜IVとDTI疑い、判定不能の6つに分けています。
ステージIが「通常骨突出部位に限局する消退しない発赤を伴う、損傷のない皮膚」となっています。一番重症となるステージIVは「骨、腱、筋肉の露出を伴う全層組織欠損。黄色または黒色壊死が創底に存在することがある」と定義されています。
【関連記事】
・NPUAP分類|褥瘡の重症度分類
スケールを用いて褥瘡を評価
褥瘡が見られたら、DESIGN-Rなどの評価スケールを用いてアセスメントをしていきますが、圧迫したあとに発赤が消退しない場合は、DESIGN-Rのd1となります。ただし、圧迫後に発赤が消退した場合でも、今後、褥瘡の発生のリスクはあるため、なにが要因となっているのかをアセスメントし、ケアをしていくことが大切です。
褥瘡の重症度の見極めで注意したいのがDTI(深部損傷褥瘡)です。圧迫とずれにより深部の軟部組織が損傷している状態のことで、紫色または栗色への変色が見られます。当初は、軽症に見えるものの時間の経過とともに深い褥瘡へと変化します。
DTIかどうかが判明するのは発赤を発見してから数週間後となるため、DTIが疑われる場合は、DTI疑いとし、継続的なケアと観察が必要となります。現在は、エコーを用いて皮膚の断面をみることで、DTIであるかどうかを判定することもできるようになってきています。
重症度評価のスケール(改定DESIGN-R®2020)
急性期の褥瘡の重症度を評価するアセスメントスケールの代表的なものが、DESIGN-Rです。2020年12月に改訂され、現在は、改定DESIGN-R®2020が用いられています。改定DESIGN-R®2020は、急性期の褥瘡の評価に適しているスケールで、深さ(D)、滲出液(E)、大きさ(S)、炎症/感染(I)、肉芽組織(G)、壊死組織、ポケットの7項目から評価します。重症度が高いものを大文字、軽度のものを小文字で表します。

【急性期の褥瘡に関する記事】
・【急性期の褥瘡】経過観察とケア
・発赤を見つけた! 急性期の褥瘡への対応とケア
褥瘡の状態を把握するためには、改定DESIGN-R®2020のそれぞれの項目をどう判定していくのかを知っておくことが大切です。順番に見ていきましょう。
まずは、発赤を見つけたら、それが褥瘡なのかどうかを判定します。その際に、用いられるのが「ガラス板圧診法」と「指押し法」です。また、発赤の見極めの際には、DTI(深部損傷褥瘡)という油断できない褥瘡の存在も理解しておく必要があります。
【初期の発赤のアセスメントのポイント】
・発赤とは? 発赤と褥瘡を見分ける『ガラス板圧診法』『指押し法』って?
・【急性期の褥瘡】経過観察とケア
褥瘡と判断したら、まずは深さ「D」が浅いか深いかを評価していきます。浅い場合はd、深い場合はDとなります。また、深さがわからないDTIの場合は、DTIとし、壊死組織で覆われていて深さが判定不能の場合は、DUとします。
滲出液「E」の評価はドレッシング材の交換回数で評価します。滲出液が多いと皮膚障害のリスクが高まり、少ないと乾燥によって肉芽形成が阻害される可能性があることを知っておきましょう。
また炎症徴候がある場合は、感染を疑います。局所の炎症徴候がみられたらi、局所の明らかな感染徴候や全身的影響がある場合はIとなります。また、臨界的定着疑いは、3Cと表記します。
サイズ「S」は創面の長径×長径に直行する最大径で判定します。肉芽組織「G」は、良性肉芽50%未満をG、50%以上をgとします。壊死組織が存在する場合はNで表します。褥瘡評価のコツを知って、DESIGN-Rを使いこなせるようになりましょう。
【DESIGN-Rの使い方のコツ】
・DESIGN-R(デザインアール)を用いた褥瘡評価のコツ
・ここが変わった! 改定DESIGN-R®2020
褥瘡のケア
褥瘡のケアには大きく分けて、ドレッシング材の使用、外用剤の使用、体圧分散、ずれ・摩擦防止、スキンケア、栄養管理が挙げられます。それぞれの項目に関する記事を紹介します。
ドレッシング材
ドレッシング材といえば、創に適したドレッシング材をどう選べばよいのかわからないなど、ギモンに思うことがたくさんあるのではないでしょうか。
選び方や貼付の仕方などを解説する前に、まずはドレッシング材について知っておきたい基礎知識を紹介します。
【ドレッシング材使用の注意点】
・この褥瘡に最適なドレッシング材を選ぶ!
ドレッシング材は、創の深さ、感染の有無、創の状態などから選びます。また、適切に選択するためには、ドレッシング材の種類や特性などを知っておくことも大切です。

【ドレッシング材の使い方のコツ】
・【材料一覧】ドレッシング材の種類・特徴と使い分け
・ドレッシング材の特徴・選び方・使い方のポイント5
ドレッシング材を交換する際は、創の洗浄と観察を行います。まず、ドレッシング材を交換する前に、ドレッシング材の外側を観察します。その後、丁寧にドレッシング材を剥がしたあと、ドレッシング材に付着した滲出液の性状や量、周囲に皮膚障害が起こっていないかなどを確認しましょう。
十分に観察を行ったあと、創の洗浄を行います。

【ドレッシング材管理のコツ】
・【写真解説】ドレッシング材の交換と洗浄の手順
ドレッシング材を交換するタイミングについて知りたい人は下記の記事がオススメです。
・褥瘡のドレッシング材を交換する時期(状態)は?
外用剤
褥瘡の治療では外用剤を使用することがよくあります。外用剤の成り立ちからわかる作用を知って、適切に使用することが大切です。
外用剤は、薬効成分の主薬と添加剤に該当する軟膏基剤、賦形剤、溶剤などで構成されています。外用剤は基剤の特性を利用して湿潤管理を行うことにより、最適な湿潤環境をつくり、薬効成分の効果により治癒効率を向上させます。
【外用剤に関する記事】
・【褥瘡ケア】外用剤の目的と塗布のタイミングは?
体圧分散、ずれ・摩擦防止
体圧分散用具(マットレス)などといった用具の使用と、体位変換やポジショニングなどのケアを合わせて行うことで、体圧の分散、ずれ・摩擦を防止します。
体圧分散用具(マットレス)の素材は、エア、ウォーター、ウレタンフォーム、ゲル/ゴム、さらにこれらの素材を2種類以上使用して構成されるハイブリッドがあります。
体圧分散用具は、局所に加わる圧力を分散し、同一体位への長時間の圧迫を減少させることを目的に使用します。患者さんの褥瘡発生リスクに応じて、どういった素材のものを使用するかを選択します。
【体圧分散とマットレスについての記事】
・体圧分散用具の種類と選択のポイント
・【褥瘡】体圧分散マットレス(エアマットレスなど)を選ぶ基準は?
さらに、適切な体位変換とポジショニングで体圧の分散とずれ・摩擦を防止しましょう。
【体位変換とポジショニングの記事】
・ポジショニングを行うときの6つの注意点
・体位変換を2時間から4時間にするためのケアとは?
・体位変換ができない場合の除圧は?
・体位変換後、安楽な姿勢保持と除圧が行える適切なポジショニングは?
スキンケア
褥瘡のスキンケアには、大きく分けて予防的スキンケアと治療的スキンケアがあります。スキンケアの基本は、清潔の保持・保湿・保護。目的に合わせて、皮膚皮膜剤や皮膚保湿剤などを選びましょう。
【スキンケアの注意点に関する記事】
・水様便によるスキントラブルどうする?
・【皮膚の保湿・保護】スキンケア用品の選択のポイント
・皮膚が乾燥すると何がいけないの?
栄養管理
エネルギーやタンパク質が不足して起こる低栄養状態は、褥瘡発生のリスクの1つです。それだけではなく、低栄養であると褥瘡の治癒を遅らせることにもなります。適切に患者さんの状態をアセスメントし、栄養管理を行いましょう。
【栄養管理のコツと注意点に関する記事】
・褥瘡の栄養状態をアセスメントするための血液データ・観察項目は?
・【褥瘡】栄養を補う食品の適切な選び方は?
・栄養管理(栄養剤)の選択のポイント
褥瘡のケアに関する疑問を解決
褥瘡のケアを行っているとちょっとした疑問が湧いてくることもあるのではないでしょうか。そこで、臨床でよくある疑問が解決できる記事を紹介します。
【ケアについてちょっとした疑問が解決できる記事】
・体位変換ができない場合の4つの要因と対処法
・痛みが強く触らせたがらない患者さんの褥瘡ケア
・デブリードマンとは? どんな創に行う? 5つの方法
・褥瘡の洗浄はどんなときでも水道水でよい?
・褥瘡にポケットがある患者さんへの在宅でできるケアの工夫とは?【PR】
・どうするとよい? がんの終末期の褥瘡予防【PR】
・褥瘡発生予防のスキンケアと発生時の対応【PR】
褥瘡に関連した看護計画
褥瘡に関連した看護計画を紹介します。
・褥瘡発生リスクが高い患者さん|低栄養や湿潤環境などによる褥瘡発生リスクが高い患者さん
・褥瘡の看護計画|仙骨部に褥瘡ができた患者さん
・皮膚統合障害への看護計画|踵部に褥瘡がある患者さん
・褥瘡予防に関する看護計画|片麻痺のある患者さん







