症状から探す
「症状から探す」の記事一覧
15件/363件

発赤を見つけた! 急性期の褥瘡への対応とケア
発赤らしきものを見つけたときに、まず行うべきことを知っておきましょう。そして、それ以上悪化させない、新たに褥瘡を作らないケアを実践することが大切です。 褥瘡のまとめ記事 * 褥瘡とは?褥瘡の看護ケア|原因と分類、評価・予防・治療など 急性期の褥瘡ってどんなもの?
2014/6/30

【出血性ショック】検査値の看護への活かし方
検査値が何を示しているのか、また検査データを踏まえてどのような看護を行えばいいのか、実際のデータをもとに読み解いてみましょう。今回は、「出血性ショック」です。 事例 糖尿病で通院していた患者さん(男性52歳)が、意識障害のある状態で救急搬送されました。症状は以下の
2014/6/24
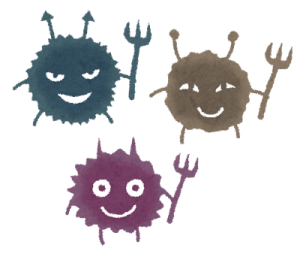
第2回 腸内細菌叢の正常化によって便性・便回数が改善!
経口摂取が難しい患者に対する栄養療法の1つ「経腸栄養」。効率よく栄養を摂取できることに加えて、管理が簡便なことから、医療現場だけでなく介護施設でも重宝されています。しかしその反面、合併症の頻度が多く、医療者を悩ませてきました。 そこで今回は、合併症の代表例である「下痢」
2014/6/23

スクイージングとは? 禁忌は? 排痰効果の上がる方法【写真解説】
排痰ケアで肺理学療法の必要性を理解している看護師さんが「知りたい!」と関心を持っているのが「スクイージング」です。 スクイージングは、「湿度」「重力」「呼吸量と呼気の速度」という排痰法の原理原則のうち、「呼吸量と呼気の速度」にあたり、体位ドレナージとともに排痰を誘導する
2014/6/9

体位ドレナージとは?方法・実施時間・コツ
患者さんへの侵襲の少ない排痰ケアを行っている病棟が増えています。吸引を前提にしない排痰ケアとは、一般に「肺理学療法」を中心にした排痰法です。 理学療法というと、難しそうに感じますが、メカニズムを理解し、練習してコツをつかむことで、安全に行うことができます。 ▼サチ
2014/6/8

【状態別】痰が固くて吸引できない時の加湿の方法
痰が固くてなかなか吸引できない、という声をよく聞きます。そこで重要視すべきは加湿です。 今回は「痰が固い場合にアセスメントすべき項目」と「患者さんの状態別 加湿方法」について紹介します。 アセスメント項目 痰の固さは体内の水分状態に左右されます。痰が固くて吸引で
2014/5/26

痰のアセスメント(貯留部位の特定)5つのポイント
「痰が多量にあるのはわかっているのに、吸引してもあまり引けない」という経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。アセスメントが苦手という人は、特に痰の貯留部位の特定が難しいと感じているようです。 聴診にばかり頼らず、触診や視診も合わせて総合的にアセスメントを行うこと
2014/5/25
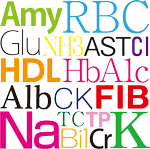
【高血糖の患者さん】事例で見る検査値の活かし方
検査値を患者さんの病態とどうつなげて考えればよいかわからない──。 そんな声に応えて、入院時からの経過と検査値の推移を見ながら、数値の示す意味や看護への活かし方を、4つの事例で検討します。 事例1 高血糖の自覚症状を訴えて教育入院になった患者さん Aさん(55歳
2014/5/17
[せん妄]急変につながる高齢者のリスク
高齢者の急変は、気付いたときには重篤化していた! ということが多いもの。高齢者の心身の機能低下の仕組みを知り、急変リスクへの理解を深めておきましょう。 ▼せん妄についてまとめて読むならコチラ せん妄とは? せん妄の症状と看護 せん妄の要因は? せん妄とは
2014/3/26
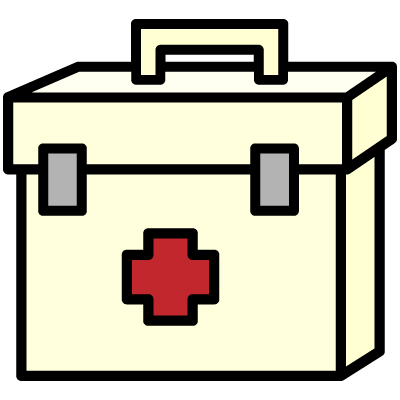
ドライスキンの患者さんのケアのコツ
スキンケアが難しい患者さんへの対応のキホン スキントラブルの原因のベースは、ほとんどが皮膚の乾燥──ドライスキンです。まずはそのメカニズムを理解しておくことが基本です。 皮膚の角質は、外界からの刺激の侵入を防ぐバリア機能とともに、水分保持機能も有しています。角質細胞の
2014/3/23
[窒息]急変につながる高齢者のリスク
高齢者の急変は、気付いたときには重篤化していた! ということが多いもの。高齢者の心身の機能低下の仕組みを知り、急変リスクへの理解を深めておきましょう。 窒息の要因は? 窒息は、口腔内の食べ物や喀痰などが気管へ入る「誤嚥」により発生します。 1 嚥下機能の低下
2014/3/19

拘縮患者さんの清拭・陰部洗浄のコツと注意点
▼体位変換・ポジショニングについて、まとめて読むならコチラ 体位変換とポジショニング 拘縮のある患者さんへの清潔ケアのキホン 清潔の援助は、拘縮の有無にかかわらず日常的なケアであり、実施頻度の高いケアです。片麻痺では健側からのアプローチが可能ですが、拘縮で
2014/3/13

第6回 体位排痰法をマスターしよう!
今回は困難ケースの解説をお休みして、ここで体位排痰法の手順について解説します。 患者さんの全身の状態を十分にアセスメントした上で、手早く実施しましょう。 長期臥床患者さんによくある左下葉貯痰への体位排痰法 術後や意識のない患者さんは、仰臥位で長時間過ごすことによ
2014/2/16

脱水のアセスメント
患者さんの異変を前に、「迷う」「わからない」「判断ができない」……。ここでは、そんな体験をした読者から寄せられた「アセスメントに迷いやすい症状」を5つピックアップしました。 症状ごとに、どのような患者情報を集めたらいいのか、判断するときのポイント、アセスメント手技などに
2014/2/4

浮腫のアセスメント
患者さんの異変を前に、「迷う」「わからない」「判断ができない」……。 ここでは、そんな体験をした読者から寄せられた「アセスメントに迷いやすい症状」を5つピックアップしました。 症状ごとに、どのような患者情報を集めたらいいのか、判断するときのポイント、アセスメント手技な
2014/1/28


