医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1638件

第2回 看護に役立つ単純X線撮影を学ぶ
単純X線撮影とは 今回は単純X線撮影の話です。単純X線撮影は、体の中をX線を通過させてその影を撮る という、最もシンプルな方法です。装置そのものが単純なので、専用の撮影室での撮像以外にも、専用の撮像装置をベッドサイドまで運んで撮像することも可能です。 通常は一
2015/11/1

第25回 ブドウ糖はどう代謝されるのか?
糖質や脂質といった栄養素についての知識は看護師にとって基本的なもののはずですが、これらが摂取・吸収されたあとの行方、つまり「代謝」については、一度は生化学で学んだことがあっても、その意義がよくわからず、無味乾燥に感じられた人も多いことでしょう。 今回はブドウ糖を中心
2015/10/31

第1回 画像診断の基本と注意点
画像診断とは 皆さんは「画像診断」あるいは「画像診断法」という言葉から何を想像するでしょうか。単純x線撮影、超音波、CT、あるいはMRIなどでしょうか。今日これらの画像は、医療現場のみならず、テレビドラマでも、頻繁に目にするようになっています。 このことは、画
2015/10/31
【ヒヤリ・ハット】Case3 経鼻栄養チューブを誤挿入して栄養剤を注入した!
日々の看護場面でドキッとした経験はありませんか?大きな事故につながらなくても、そんな経験は減らしたいもの。2015年10月の医療事故調査制度スタートとともに、いま医療安全の意識が高まっています。この機会に、看護師が遭遇しやすいヒヤリ・ハット事例から、日常に潜む「あぶないケ
2015/10/27
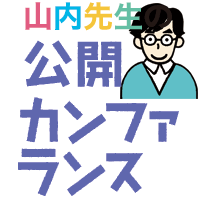
第21回 心窩部痛を訴える患者さん(その1)
今回の事例 [りーさん より提供された事例] 冠動脈バイパス術後のリハビリ期の患者さん。術後創痛があり、ロキソニンを頓用内服していました。ある日、「お腹が痛い、痛み止めがほしい」との訴えがありました。 →この患者さんに起こっていることは?
2015/10/26

第3回 スキンテアの予防法は?
超高齢社会に伴い増加する高齢な患者への看護。高齢者の皮膚は、さまざまな理由から脆弱化し、些細なずれや摩擦によって、スキンテアを起こしやすい状態にあります。しかし、スキンテアの予防や処置の方法をしっかりと確立できている施設は、まだ多くはありません。 そこで、スキンテアを予
2015/10/25

第11回 急変の予兆を知る 意識・精神活動の変化と「お決まりの抵抗手段」⑦「炎症反応と冬眠行動」
はっきりとした予兆もなく、患者さんが急変したり、重篤な疾患が進行していたりする経験があると思います。そのような急変に先立って、先輩の看護師や医師から「あの患者、何かヘンだよね」という直感的な台詞を聞いたことがあるかもしれません。 この連載では、急変前の「何かヘン」と
2015/10/25
【ヒヤリ・ハット】Case2 ICUから転室してきた患者が1人で動いて転倒し、留置中の術後ドレーンが抜けた!
日々の看護場面でドキッとした経験はありませんか?大きな事故につながらなくても、そんな経験は減らしたいもの。2015年10月の医療事故調査制度スタートとともに、いま医療安全の意識が高まっています。この機会に、看護師が遭遇しやすいヒヤリ・ハット事例から、日常に潜む「あぶないケ
2015/10/20
頭頸部がんにおける栄養素のチカラ ―頭頸部外科医の視点から―
がん患者さんは、抗がん薬治療による体重減少・皮膚障害などの副作用が大きな問題となります。また、放射線療法によっても皮膚障害が現れます。がん治療における体重減少や皮膚障害へ適切に対策することで、患者さんのQOLや治療の継続率が高まり、予後を大きく改善します。 本記事で
2015/10/18

第10回 急変の予兆を知る 意識・精神活動の変化と「お決まりの抵抗手段」⑥「炎症反応」
はっきりとした予兆もなく、患者さんが急変したり、重篤な疾患が進行していたりする経験があると思います。そのような急変に先立って、先輩の看護師や医師から「あの患者、何かヘンだよね」という直感的な台詞を聞いたことがあるかもしれません。 この連載では、急変前の「何かヘン」と
2015/10/18
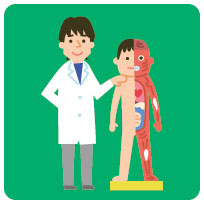
第24回 栄養素の代謝ってどういうこと?
糖質や脂質といった栄養素についての知識は看護師にとって基本的なもののはずですが、これらが摂取・吸収されたあとの行方、つまり「代謝」については、一度は生化学で学んだことがあっても、その意義がよくわからず、無味乾燥に感じられた人も多いことでしょう。 今回はブドウ糖を中心
2015/10/14
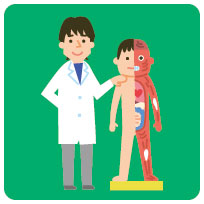
第23回 カルシウムはどう調節されている?
カルシウムは、ナトリウムやカリウムに比べれば臨床検査で測定される頻度が少ないですが、一般には最もよく知られているミネラルと言ってよいでしょう。その血中濃度は厳密に調節され、体内でさまざまな生理作用を発揮します。 また、カルシウムには他のミネラルとは異なった特色が数多
2015/10/13
【ヒヤリ・ハット】Case1 薬剤の投与経路を間違ってしまった!
日々の看護場面でドキッとした経験はありませんか?大きな事故につながらなくても、そんな経験は減らしたいもの。2015年10月の医療事故調査制度スタートとともに、いま医療安全の意識が高まっています。この機会に、看護師が遭遇しやすいヒヤリ・ハット事例から、日常に潜む「あぶないケ
2015/10/13

第22回 電解質―クロール
血清の電解質濃度を調べる際に、Na(ナトリウム)、K(カリウム)とともにセットで測定されるCl(クロール)濃度。皆さんはこのClについて、どれだけのことを知っているでしょうか? 「いつも採血項目に入っているけれど、何のために測っているのかわからない」という人も多いで
2015/10/12

第9回 急変の予兆を知る 意識・精神活動の変化と「お決まりの抵抗手段」⑤「冬眠」行動
はっきりとした予兆もなく、患者さんが急変したり、重篤な疾患が進行していたりする経験があると思います。そのような急変に先立って、先輩の看護師や医師から「あの患者、何かヘンだよね」という直感的な台詞を聞いたことがあるかもしれません。 この連載では、急変前の「何かヘン」と
2015/10/11


