医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1634件

第6回 「薬が飲みにくい」と言われたときの工夫
処方薬の多い現在、正しい服用のためには薬剤師、そして患者さんの最も近くにいる看護師の支援が必要になってきます。内服薬を中心に服薬支援のポイントを紹介します。 患者さんに「薬が飲みにくい」と言われたら 患者さんから薬が飲みにくいという訴えがあれば、飲みや
2014/8/12

ハイリスク薬と配合変化にどう対応する?
輸液管理にはさまざまな確認事項があります。ここでは、輸液を行う看護師が確実に押さえておきたい内容をまとめて解説します。 特に注意が必要な輸液製剤を知っておく 注意が必要な薬剤には「ハイリスク薬」というものがあります。その定義は医療施設により異なりますが
2014/8/12

【問題5】200mlを50ml/h 成人用ルートで投与する時、4秒間の滴下数は?
問題 成人用ルートを使用して、△△輸液200mlを50ml/hで投与する指示を受けました。 4秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約1滴 解説 成人用ルートは1
2014/8/11

腹部の触診、肝臓・腎臓の打診|消化器のフィジカルアセスメント(2)
アセスメントは、患者さんとの会話やケアを通じて全身の状態に目を向け、五感をフルに活用することが大切です。ここでは系統別にフィジカルアセスメントのテクニックをまとめました。普段行っているアセスメントの流れと手技を再確認してみましょう。 関連記事 消化器アセスメント視
2014/8/9
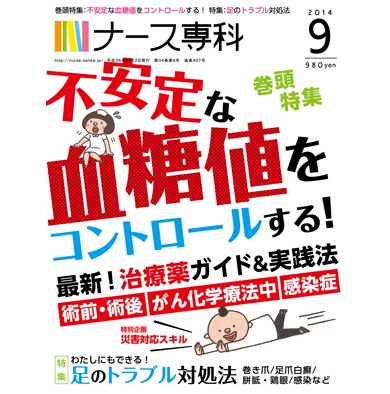
ナース専科2014年9月号『不安定な血糖値をコントロールする!』
書誌情報 発売 2014年8月12日 版型 A4変形判 ページ数 120 定価 907円+税 豪華3本立て! 今月は、特集2本に特別企画をプラスした3本立て! 第1特集
2014/8/7

ショック時に使用する輸液製剤はどれ?
どんなケースにも共通する輸液管理の基本的な考え方について整理しておきましょう。 輸液製剤の種類 輸液製剤には、細胞外液補充液、維持輸液、糖輸液、アミノ酸輸液、脂肪乳剤などの種類があり、目的に合わせて選択することになります。 覚えておきたい
2014/8/7

第5回 薬と持参薬・飲食物との飲み合わせ
処方薬の多い現在、正しい服用のためには薬剤師、そして患者さんの最も近くにいる看護師の支援が必要になってきます。内服薬を中心に服薬支援のポイントを紹介します。 患者さんへの服薬支援で相互作用を防ごう 薬は多くのケースで他の薬と併用されます。その場合、薬の
2014/8/5

【5R】輸液指示を受けるときの看護師の注意点は?
輸液管理にはさまざまな確認事項があります。ここでは、輸液を行う看護師が確実に押さえておきたい内容をまとめて解説します。 誤薬・誤投与を防ぐための「5R」の確認 輸液の指示が出たら、注射箋に記載されている情報を「5R」に基づいて、要点をしっかりと押さえて
2014/8/5
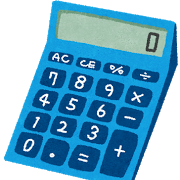
【問題4】500ml×3本を、24時間 小児用ルートで投与する時、10秒間の滴下数は?
問題 小児用ルートを使用して、●●輸液500ml×3本を、24時間で投与する指示を受けました。 10秒間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 約10滴 解説 小児用ル
2014/8/4

皮膚状態・腹部の観察、腹部の聴診法|消化器のフィジカルアセスメント(1)
アセスメントは、患者さんとの会話やケアを通じて全身の状態に目を向け、五感をフルに活用することが大切です。ここでは系統別にフィジカルアセスメントのテクニックをまとめました。普段行っているアセスメントの流れと手技を再確認してみましょう。 消化器のフィジカルアセス
2014/8/2
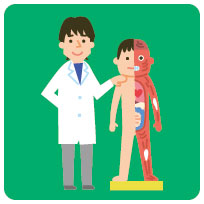
第2回 末梢循環・浸透圧について知って看護に役立てよう
前回(第1回 浮腫とアルブミン)は浮腫やその原因となるメカニズムについて解説してきました。今回は、 浮腫とアルブミンの解説でもたびたび出てきた、末端循環と浸透圧というメカニズムについて詳しく解説していきます。 体液の組成 成人では体重の約60%が体液で占められ
2014/8/2
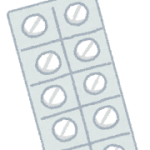
【服薬管理】ケア&対応の5つのワザ
ワザ1 薬がうまく飲めないときは、剤形を変えたり自助具を使って工夫する! 薬物がうまく服用できない患者さんに対しては、その理由に応じた対応を行うことが大切です。 [嚥下に問題がある] 錠剤やカプセル剤が大きくて飲み込めない 散剤や液剤へと患者さんが
2014/8/1

輸液量(成人、小児の場合)は水分喪失予定量が原則
どんなケースにも共通する輸液管理の基本的な考え方について整理しておきましょう。 1日の輸液量=1日の水分喪失予定量 成人の場合 輸液は失われる予定分を補給するのが原則です。 成人の輸液量は、1日の水分喪失量と同じ40mL/kg/日が目安にな
2014/7/31

【問題3】500mlを60ml/h 成人用ルートで投与する時、1分間の滴下数は?
問題 成人用ルートを使用して、○○輸液500mlを60ml/hで投与する指示を受けました。 1分間の滴下数はいくつでしょうか? 解答・解説は次のページです。 解答 20滴 解説 成人用ルートは1ml
2014/7/31

【服薬管理】アセスメントの4つのポイント
治療をスムーズに進めるため、あるいは安全・安楽に支援するために、高齢者特有の症状や機能低下について解説します。 【関連記事】 ● 服薬状況を見える化できる服薬カレンダーと服薬ボックス 【ケア&対応についてはこちら】 ● 【服薬管理】ケア&対応の5つのワザ
2014/7/30


