医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1634件
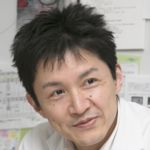
第24回 摂食嚥下障害の臨床Q&A「口腔内が乾燥している患者さんにどう対応すればよい?」
脳梗塞後の77歳女性、口腔内の乾燥が目立ちます。服薬数も多いのですが、どれも止められるものではありません。水分摂取をすすめるもののあまり飲んでもくれません。どうしたらいいですか? 口腔乾燥とは唾液の分泌量が低下し、口腔内が乾燥している状態です。今回は口腔乾燥
2016/8/30
脆弱な高齢者の皮膚を守る ~スモールチェンジエアマットレスの有効性~(3)【PR】
身体を大きく動かす体位変換は安眠を妨げ、摩擦やずれの原因となることから、須釜さんはスモールチェンジによる体位変換を提案します。 スモールチェンジの方法には、1つの小枕を右下肢、右臀部、右肩部……といったように順番に移動させていくものがあります(図1)。
2016/8/29

シンチグラフィ検査(核医学検査)の目的と看護のポイント
シンチグラフィ検査(核医学検査)とは 呼吸器系疾患で行われることも多いシンチグラフィ検査は、各種画像検査とともに広く用いられていますが、一般的なX線写真やCTの撮影とは大きく異なる特徴を持っています。X線撮影は体外からX線ビームを照射し、その透過率の違いを画像イメー
2016/8/25

抗精神病薬の適用外使用について知っておこう
抗認知症薬の機序と特性の理解が必要 特に一般病棟の場合、認知症治療薬は「入院患者さんの持参薬」であることが少なくないでしょう。皆さんは認知症の治療薬について、どのぐらい理解していますか。 現在、抗認知症薬(アルツハイマー型)には、1 ドネペジル(アリセプト®、
2016/8/21

第22回 部位別のエンゼルメイク(4)皮膚に赤黒さや黄疸などがある場合
臨終を迎えた患者さんの人格や尊厳が失われないよう、ご遺体がみなさんの手を離れるまでケアを行なう「エンゼルケア(逝去時ケア)」。本連載ではそのエンゼルケアの実践法を解説します。 ▼エンゼルケアについて、まとめて読むならコチラ エンゼルケア(逝去時ケア)とは?目的
2016/8/20

胸腔穿刺・ドレナージの目的と看護のポイント
胸腔穿刺・ドレナージとは 呼吸器系疾患の検査のなかで、最も頻繁に実施される侵襲的検査が胸腔穿刺です。悪性腫瘍、肺炎、結核、心不全などさまざまな病態で胸水が貯留し、その原疾患の診断のために胸水を採取するのが胸腔穿刺です。比較的安全に実施でき、ベッドサイドで、研修医など
2016/8/18
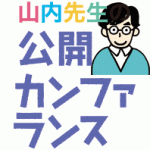
第28回 熱が下がらない患者さんにどんなケアをする?
今回の事例 熱が下がらない患者さん [すがっちさん より提供された事例] 50代男性。昼間は畑仕事をしていましたが、夕方から発熱し熱が下がらないため受診。状況から全身観察したところ腕に何かに噛まれたような跡がうっすらあることから『ツツガムシ病』の診断で入院しまし
2016/8/16
脆弱な高齢者の皮膚を守る ~スモールチェンジエアマットレスの有効性~(2)【PR】
高齢者の皮膚の脆弱性 上出さんは、高齢者にみられる皮膚の機能不全や脆弱性については、皮膚粗鬆症という言葉を用いて概念づけることができるといいます。ここに含まれる症状としては、老人性紫斑、皮膚萎縮、軽微な外傷による皮膚剥離、創傷治癒遅延、難治性萎縮性皮膚潰瘍、皮下深部
2016/8/15

グリセリン浣腸の目的と手順【マンガでわかる!看護技術】
浣腸とは?浣腸を行う目的 今回の手技は「浣腸」です。 病院における浣腸とは、肛門にグリセリン液を入れて排便を促すことを言います。直腸及びS状結腸までの便は、これで出すことが可能です。 便秘で苦しんでいる人に行うのはもちろんのこと、原因のはっきりしない
2016/8/10
脆弱な高齢者の皮膚を守る ~スモールチェンジエアマットレスの有効性~(1)【PR】
2016年6月11日~12日、第25回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会が石川県金沢市で開催されました。12日には、ランチョンセミナー「脆弱な高齢者の皮膚を守る~スモールチェンジエアマットレスの有効性~」が行われ、現在の超高齢社会において看護師が知っておくべきこと
2016/8/5

胸部画像診断(CXR、CT)の目的と看護のポイント
胸部画像診断(CXR、CT)とは 呼吸器領域では、理学所見、肺機能検査に続き重要となるのが、各種画像診断です。この連載でも以前取り扱った気管支鏡検査の実施前にも、まずは画像診断での部位や性状の特定が大変重要となります。そのなかでも最も頻繁に利用されるものが、胸部単純
2016/8/4

子育て世代のがん患者に必要な支援とは?
子育て世代のがん患者が直面する問題 厚生労働省が実施している患者調査によると、がん患者総数(推計)は増加し続け、2002年の128万人から11年には152万6000人を数えるまでになりました。一方、国立がん研究センターの予測による15年のがん罹患数は98万2100人
2016/8/3

第21回 部位別のエンゼルメイク(3)気道切開部やペースメーカー
臨終を迎えた患者さんの人格や尊厳が失われないよう、ご遺体がみなさんの手を離れるまでケアを行なう「エンゼルケア(逝去時ケア)」。本連載ではそのエンゼルケアの実践法を解説します。 今回は「気管切開部」と「ペースメーカー」の対応についてです。気管は、胃腸とともに腐敗が進
2016/7/30

肺機能検査の目的と看護のポイント
肺機能検査とは 循環器疾患で最も重要な生理機能検査が心電図であるように、呼吸器疾患の診断における最も重要な生理機能検査は肺機能検査です。肺機能検査は、呼気と吸気からなる人間の呼吸運動を評価することができ、なおかつたいていの場合非侵襲的です。精密で大掛かりな装置を要
2016/7/28

第20回 部位別のエンゼルメイク(2)外傷・腫瘍・褥瘡・熱傷がある場合
臨終を迎えた患者さんの人格や尊厳が失われないよう、ご遺体がみなさんの手を離れるまでケアを行なう「エンゼルケア(逝去時ケア)」。本連載ではそのエンゼルケアの実践法を解説します。 今回は「顔面の外傷や腫瘍」と「褥瘡や熱傷」の対応についてです。顔に開放性の腫瘍があったり、ケガ
2016/7/23


