医療・看護技術から探す
「医療・看護技術から探す」の記事一覧
15件/1634件
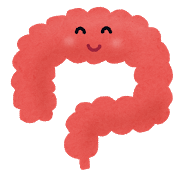
第1回 経管栄養剤による「排便コントロール」改善への取り組み【PR】
経管栄養を行っている患者さんのなかには、下剤多用の弊害として、便秘や下痢の症状を繰り返す人が多く見受けられます。高齢の入院患者さんが多く、療養環境を重視した東京都板橋区にある竹川病院では経管栄養剤を見直すことで下剤使用量に変化がみられ、排便がコントロールしやすくなったとい
2016/5/16

第16回 エンゼルメイク実践編 (4)クリームファンデーションとフェイスパウダー
今回はスキンケアのあとのメイクアップの解説です。前回行った「蒸しタオルと乳液」で整肌後、肌の色を整える「クリームファンデーション」→「フェイスパウダー」を実践していきましょう。 ▼エンゼルケアについて、まとめて読むならコチラ エンゼルケア(逝去時ケア)とは
2016/5/14
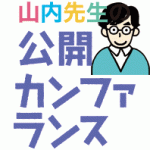
第26回 うまく痰を喀出できない患者さん
今月の事例 うまく痰を喀出できない患者さん [かーこさんから提供された事例] 肺炎で入院してきた70歳代の男性患者さん。痰が絡まっているような音がし、咽頭までは上がってきていますが、口から喀出できない状態だったため、吸引を行い痰を排出していました。 ベッド上臥床で
2016/5/10

向精神薬|日本での使用法と一般病棟でも使用されるリスク
欧米との差が歴然 日本の向精神薬の使用法 薬物療法が治療の中心である精神科医療において、これまでの日本では、向精神薬の「多剤大量処方」が当たり前でした。これは、疾患の特徴からくる患者さんごとの個体差が顕著で、また本人の自覚症状や満足感に依る部分も多いため、一層高い効
2016/5/2

第42回 エストロゲン・ゲスターゲンと月経周期
4ホルモンの推移と卵巣周期 性周期とは、前回紹介した4種のホルモンがどのように推移するのかが核心であると言ってよく、いよいよその詳細を追いかけてみましょう。そのためには、いったん視床下部と子宮のことは忘れて、しばらくは下垂体と卵巣の相互作用に集中すると理解しやすく
2016/5/1

第15回 エンゼルメイク実践編 (3)蒸しタオルと乳液による整肌
前回のクレンジング・マッサージからの続きを実践していきます。今回のエンゼルメイクはクレンジング・マッサージにより皮膚の汚れがとれた後、蒸しタオルと乳液で整肌をします。(今回は女性をモデルとしていますので、男性の髭そりをする場合は「ナースのためのエンゼルケア(学研メディカル
2016/4/30

【マンガでわかる!】JCSの具体的な付け方
JCS(ジャパン・コーマ・スケール)は、患者の意識レベルを9つに分類(大分類:3パターン × 小分類:各3パターン)する測定手法です。意識レベルのアセスメント法についてマンガで詳しく解説します! 【大分類】 Ⅰ:覚醒している Ⅱ:刺激すると覚醒する Ⅲ:刺激し
2016/4/22
おむつをしている患者さんの褥瘡ケアとは?
ナース専科コミュニティ会員にアンケートを実施し、排便や排尿にかかわることで実際に困っていることを集め、皮膚・排泄ケア認定看護師に解説してもらいました。 おむつをしている患者さんの褥瘡ケアとは? 特別なケアは必要ない おむつ内の高温多湿の湿潤環境は
2016/4/22
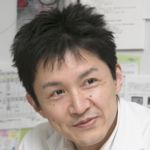
第16回 摂食嚥下障害の臨床Q&A 「嚥下内視鏡検査(VE)や嚥下造影検査(VF)ができないと嚥下機能は評価できない?」
当院では、嚥下造影検査(VF)の設備がなく、嚥下内視鏡検査(VE)を実施できるドクターも現在いません。VFやVEを使用しない嚥下機能評価法はありますか? また、嚥下障害を疑う患者さんにはどのように経口摂取(嚥下訓練)を進めていけばよいでしょうか? VEやVF
2016/4/19

第14回 エンゼルメイク実践編(1)事前準備と全体の流れ(2)顔のクレンジング・マッサージ
これまで「エンゼルケアの基本編」をお話ししてきました。今回より、いよいよエンゼルメイクの実践編に入ります。まずはエンゼルメイクの事前準備と全体の流れを把握しておきましょう。 ▼エンゼルケアについて、まとめて読むならコチラ エンゼルケア(逝去時ケア)とは?目
2016/4/16

第41回 なぜ性周期は難しいのか?
性ホルモンによって精緻にコントロールされる女性の性周期。その概要は生理学の基礎知識のひとつですが、ひとまわりのサイクルを順序立てて説明できる自信のある人は少ないかもしれません。今回は性周期にかかわる内分泌系の知識を、見通し良く整理してみましょう。 卵巣の2つ
2016/4/13
排尿誘導の間隔はどうやって決める?
ナース専科コミュニティ会員にアンケートを実施し、排便や排尿にかかわることで実際に困っていることを集め、皮膚・排泄ケア認定看護師に解説してもらいました。 排尿誘導の間隔はどうやって決める? 排尿パターンを把握して決める 排尿誘導は、膀胱・尿道機能に
2016/4/11
おむつ交換のたびに陰部洗浄は必要?
ナース専科コミュニティ会員にアンケートを実施し、排便や排尿にかかわることで実際に困っていることを集め、皮膚・排泄ケア認定看護師に解説してもらいました。今回はおむつ交換についての質問に回答します。 おむつ交換のたびに陰部洗浄は必要? おむつ交換の陰部洗浄
2016/4/9
在宅でのおむつ交換のタイミングどうする?
ナース専科コミュニティ会員にアンケートを実施し、排便や排尿にかかわることで実際に困っていることを集め、皮膚・排泄ケア認定看護師に解説してもらいました。 在宅でのおむつ交換のタイミングどうする? 排尿パターンを把握してタイミングよく交換 まず排尿日
2016/4/7

第40回 ステロイドはどこに作用する?
今回はステロイドについて解説します。 ステロイドは遺伝子の発現レベルで影響与える では、強力な抗炎症作用を有する副腎皮質ホルモンとして知られる、糖質コルチコイド(いわゆるステロイド)は、炎症プロセスのどこに作用するのでしょうか? その機序はNSAID
2016/4/6


